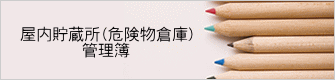
摂南大学薬学部 屋内貯蔵所(危険物倉庫)入出庫管理簿
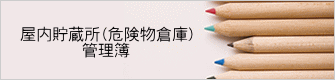
摂南大学薬学部 屋内貯蔵所(危険物倉庫)入出庫管理簿
●屋内貯蔵所(危険物倉庫)管理簿
2015年度から管理簿のオンライン化を進めています。
上のリンクから屋内貯蔵所(危険物倉庫)管理簿にアクセスし、
入庫、出庫等、在庫管理を行ってください。
●危険物取り扱いの手引き(PDF)
●危険物とは
【危険物取り扱いの手引き】
消防法で危険物と定められた化学薬品等については、各実験室、研究室又は
間仕切りのない1つの棟に保管できる量が、消防法で指定数量として規定されている。
危険物の使用は、研究教育上必要なものに限り、その使用量・貯蔵量は研究教育上
必要不可欠な量とし、必要以上に購入・貯蔵しない。
使用・貯蔵にあたっては、消防法、危険物の規制に関する政令を遵守する。
1.危険物と指定数量
消防法で危険物として指定している物質と指定数量は次のとおりである。
第1類 酸化性固体 塩素酸塩類(指定数量 50kg)、過塩素酸塩類(50kg)など
第2類 可燃性固体 硫黄(指定数量 100kg)、鉄粉(500kg)など
第3類 自然発火性物質 ナトリウム(指定数量 10kg)、黄燐(20kg)など
第4類 引火性液体 ジエチルエーテル(指定数量 50L)
ヘキサン・酢酸エチル(指定数量 200L)
アセトン・アルコール類(指定数量 400L)
キシレン・エチルベンゼン(指定数量 1000L)
ニトロベンゼン・アニリン(指定数量 2000L)など
第5類 自己反応性物質 硝酸エステル類(指定数量 10kg)など
第6類 酸化性液体 硝酸(指定数量 300kg)など
2.危険物の保管
消防法で危険物と定められた化学薬品等の貯蔵及び使用については、
法律の定めるところに従わなければならない。
1) 指定数量以上の危険物
指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱う場合は消防法に基づく許可が必要になる。
また、取り扱うときは、危険物取扱者免状を有しているか、危険物取扱者免状を
有している者の立ち会いの下に行わなければならない。
品名を異にする2以上の危険物を同一の場所において貯蔵し、又は取り扱うときは、
当該貯蔵又は取り扱う危険物の品名毎の数量をそれぞれの指定数量で除し、
その商の和が1以上となるときも同様である。
2) 少量危険物指定数量未満でも指定数量の0.2倍以上の危険物を同一の場所において
貯蔵し、または取り扱うときは、当該場所は少量危険物貯蔵所として法の規制を受け、
消防署への届出が必要となる。
品名を異にする2以上の危険物を同一の場所において貯蔵し、または取り扱う場合は、
当該貯蔵または取り扱う危険物の品名毎の数量をそれぞれの指定数量の0.2倍の
数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は少量危険物貯蔵取扱所として
法の規制を受け、消防署への届け出が必要となる。
塗料、ギヤーオイル等も危険物に該当するので注意すること。
例えば
アセトン 20L(指定数量:400L)、エチルアルコール 20L(指定数量:400L)、
ヘキサン 10L(指定数量:200L)、ジエチルエーテル 5L(指定数量::50L)
を保管する場合は、
20/(400×0.2) + 20/(400×0.2) + 10/(200×0.2) + 5/(50×0.2) = 1.25
となり、消防法の規制の対象になる。
3) 指定数量の0.2倍未満の危険物は届出なしで保管できるが、それを保管し、
使用する場合も、消防法を遵守する義務がある。
3.危険物の保管方法
1) 危険物は、原則として危険物屋内貯蔵所(危険物倉庫)に保管すること。
やむを得ず研究室で保管する必要があるときは指定数量の0.2倍未満とし、
薬品戸棚等に適切に保管する。
2) 危険物を保管している場所には標識(白地に黒色文字で「危険物保管庫」と記載)を
見やすい場所に必ず掲示する。
3) 危険物は類ごとに分け、次の表示をして、互いに接触しないようにして保管する。
薬品戸棚等は床又は壁に固定し、直射日光を受けず、温度変化の少ないところに設置する。
4) 衝撃で爆発する可能性のある薬品はなるべく低いところに置き、地震などによって
落下しないように仕切り板の付けた薬品戸棚等に整理整頓して保管する。
5) ラベルの取れたものや、汚れて不明瞭になったものは、直ちに新しいものと取り換える。
6)薬品戸棚等の付近では火気を使用しない。
4.危険物の管理方法
1) 危険物の使用責任者は、危険物の購入、使用の都度定められた様式の
危険物屋内貯蔵所管理簿に記入し、危険物保安監督者に報告しなければならない。
2) 危険物の使用責任者は、毎年3月末に保管している危険物の数量を危険物屋内貯蔵所
管理簿と照合のうえ確認し、危険物保安監督者に報告しなければならない。
3) 危険物屋内貯蔵所は常時施錠し、必要な時のみ開けること。なお、危険物保安監督者が
鍵を管理する。
購入、使用時の立ち入りは、鍵受け渡し簿に氏名、受渡時間ほかを記入し鍵の受け渡しをする。
5.危険物の標識
危険物の使用にあたっては、作業中の安全を確保するため、次に示す標識を
見やすい場所に掲げる。
*区分標識
関係者以外の立ち入りを禁止する場合 赤地に白文字で「関係者以外立入禁止」と記載
火気の使用を禁止する場合 赤地に白文字で「火気厳禁」と記載
爆発物を取り扱う場合 赤地に白文字で「爆発危険」と記載
注水を禁止する場合 青地に白文字で「注水禁止」と記載
6.使用上の注意
1) 使用する薬品の性状、特に発火性、爆発性、毒性の有無を調べてから使用すること。
2) 危険な物質を使用するときは、前もって災害の防護手段を考え、万全の準備をし、作
業は2名以上で行うこと。
3) 消火器、保護具(保護眼鏡、防護面、手袋など)、洗眼器、応急箱を整備しておくこと。
4) 実験に必要な量以上の薬品は、実験台に置かないこと。
5) 引火性物質及び発火性物質を取り扱う場合は、必ず消火設備が設置されていることを
確認すること。
6) 引火性物質及び発火性物質を取り扱う場合は、必ず換気すること。
7) 作業内容を十分熟知のうえ従事すること。
8) 消防法で定められている危険物を指定数量以上扱うときは、危険物取扱者免状を有して
いるか、危険物取扱者免状を有している者の立ち会いの下で行うこと。
7.事故等の際の措置
1) 危険物保安監督者は、貯蔵または取り扱う危険物について、火災、盗難、紛失、流出
その他の事故が生じたときには、必要な応急措置を講ずるとともに、直ちに枚方事務室を
経由し学部長に報告しなければならない。
2) 学部長等は、当該事故の生じた貯蔵所に立ち入り、状況の把握および次の措置を講じな
ければならない
・ 危険物の管理状況を確認する
・ 必要に応じて、関係者に連絡する
・ その他必要な事項
3) 危険物保安監督者は、事故の原因の解明および再発防止の措置を迅速に行い学部長等に
報告しなければならない。
4) 緊急連絡体制を確立し、事故等が生じたときに、速やかな対応を行う。