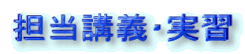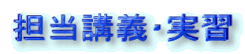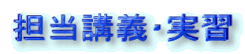
1年次前期
・薬剤師になるために:
本講義の目的は、卒業後、薬学出身者として生命に関わる職業人となることを自覚し、それにふさわしい行動、態度を身につけること、また、薬学生としてのモチベーションを高めるために、薬の専門家として身につけるべき基本的知識、技能、態度を修得し、薬学出身者の活躍する現場を体験することにある。
3年次後期
・薬物治療学a:
種々の疾患の病態生理、臨床症状、診断法と各疾患に対する治療薬の選択、適用法、薬物相互作用などについての知識を習得する。本講義では、悪性腫瘍、骨・関節疾患、中枢神経系疾患について講義する。3年次前期までの履修した「生理解剖学I・ II・ III」、「薬理学I・ II」と「薬物治療b」の知識を基盤として、医薬品の適正使用にあたり必要な知識を取得する。
3年次前期
・薬物治療学b:
薬理活性が強く、且つ使用法が複雑な医薬品の増加、長期投与、また合併症による多剤併用などに伴い、適正に医薬品を使用するための医薬品情報が増加している。それに対応するためには薬剤師が医薬品に対する基礎知識に加えて、薬物治療学、病態生理学、臨床薬理学に関する豊富な知識を持つことが必要不可欠である。本講義では、主として循環器系疾患、消化器系疾患の病態生理、ならびにそれらの疾患に対して実際に医療現場で行われている薬物治療法について習得する。
5年次前期または後期
・臨床薬学演習
本学独自の薬学専門教育
未来型薬剤師
社会保障審議会医療部会の「安心と希望の医療確保ビジョン」で討議されている「医療職の役割分担と連携」において、6年制薬剤師に期待される「社会のニーズ」を具備した薬剤師になるために、薬剤師の新しいスキルに関する基本的知識、技術、態度を身につける。
臨床薬学演習(C14 薬物治療、C15 薬物治療に役立つ情報、セルフメディケーション)
(C14,C15)疾病に伴う症状と臨床検査値の変化などを的確な患者情報を取得し、患者個々に応じた薬の選択、用法、用量の設定および各々の医薬品の「使用上の注意」を考慮した適正な薬物治療に参画できるようになるめに、薬物治療に関する基本的知識と技能を習得する。
(セルフメディケーション)国民の未病・予防・健康維持に貢献できる薬剤師になるために、セルフメディケーションに関する基本的知識と技能を習得する。

3年次後期
・医療薬学実習a,b,c
この実習は、調剤実習、基礎薬剤学実習および臨床薬学実習からなる。調剤実習では、病院薬局あるいは保険薬局で業務として行われている調剤に関する実習を行う。基礎薬剤学実習は、主に生物薬剤学実習で構成され、動物における薬物の体内動態、薬物動態に影響する生体側の因子や薬物の物理化学的な性質について理解する。臨床薬学実習では、コンピューターを用いた薬剤師業務に関する演習、輸液に関する演習、薬理効果の評価に関する実習で構成される。
4年次後期
・臨床実務(スキル)実習
本学独自の薬学専門教育
未来型薬剤師
社会保障審議会医療部会の「安心と希望の医療確保ビジョン」で討議されている「医療職の役割分担と連携」において、6年制薬剤師に期待される「社会のニーズ」を具備した薬剤師になるために、薬剤師の新しいスキルに関する基本的知識、技術、態度を身につける。
臨床実務(スキル)実習
社会保障審議会医療部会の「安心と希望の医療確保ビジョン」で討議されている「医療職の役割分担と連携」において、6年制薬剤師に期待される「社会のニーズ」を具備した薬剤師になるために、検査値やバイタルサインの評価等に関する新しい臨床スキルを身につける。
戻る