洋服業界記者クラブ「日本洋服史刊行委員会」発行
「日本洋服史 一世紀の歩みと未来展望」から抜粋
資料提供:株式会社トクミヤ洋服店(東京都千代田区飯田橋1-6-9)
※ 写真をクリックすると拡大表示されます
慶應3年(1867)年12月万機ご一新の告諭がなされたが、 時局多端で手がまわりかね礼服の制まで一新するに至らなかった。
数日後の布令に「冠以下官服類追々制度立てさせらるべく候得共、まずそれまでの処、従来のまゝ着用これあるべき旨、仰出され候事」
とあり、参内する公家諸侯は衣冠を正とし、御所に入ろうとした当時の軍服すなわち戒装の武士が、皮の刀帯と靴をとがめられ脱がされることもあった。
時局多端で手がまわりかね礼服の制まで一新するに至らなかった。
数日後の布令に「冠以下官服類追々制度立てさせらるべく候得共、まずそれまでの処、従来のまゝ着用これあるべき旨、仰出され候事」
とあり、参内する公家諸侯は衣冠を正とし、御所に入ろうとした当時の軍服すなわち戒装の武士が、皮の刀帯と靴をとがめられ脱がされることもあった。
変わり者というより進歩派であった西園寺公望が、洋服姿で参内し大いに物議をかもし問題となったが、執務に機能的である主張し洋服で押し通したのは有名な話である。 翌4年の9月8日には明治と改元されたが、この時、調練の伝習生、軍艦乗込御用方、蘭学生など一部の人に限られていた洋服の着用が、洋服禁止令の解除により一般の人たちにも許可されるようになった。
「古今ノ沿革ヲ考ヘ、時宜ニ推リ、公議ヲ採リ、一定ノ御制度被為立度、思召ニ付」
と意見を求められたりしたが、新規に制定するにいたらず、上級の官員は衣冠か直垂、下級の官員は麻上下が礼服であった。
明治3年、旅行と非常時用にと官吏の制服ができた。袖口の広い黒ラシャ、一列ボタン、裾長の寛衣、紫打紐の房を肩章とし、金の側章のある鼠ラシャのだぶだぶの長袴。和洋折衷のなんとも珍妙な服であったが、これは明治15年に廃止されている。

明治2年エジンバラ皇子のわが国訪問により、本格的な洋装に刺激されたらしく、街ではトンビ・カッパが流行しはじめた。翌3年春、山城屋和助に聖上の洋服調進の命が下った。和助は外人のベ・ブランド、高橋安吉、三浦鶴吉、三宅半三郎、小沢惣太郎、鈴木篤右ヱ門の6名を加え、宮内省ご用係となった。
この時、服装は大礼の根源として皇国いらいの服装を支持する国粋派と、西洋服を採用しようとする開明派との対立があったが、参議副島種臣が、趙の武霊王の故事をひいて、
「胡服して胡を制す」
と守旧派をおさえた。
明治4年8月9日、官吏および華士族に対し
「散髪、脱刀及び洋式の服を用いること勝手たるべし」
というお沙汰があり、ついで9月4日には服制を改むるの勅諭がなされた。
朕惟フニ風俗ナル者不抜以テ其ノ勢ヲ制ス……朕今断然其服制ヲ更メ其風俗ヲ一新シ祖宗以来尚武ノ国体ヲ立テント欲ス汝近臣其レ朕ガ意ヲ体セヨ
これ以後文武百官の大礼服を定め、洋服をもって正服となし、従来の衣冠束帯(いかんそくたい)烏帽子直垂(えぼしひたたれ)をもって祭服とされたのは、明治5年11月12日であるが、それ以前に天皇をはじめ新政府の大官高官連は洋服を着用するようになっていた。
そして翌5年5月の九州ご巡幸のさい、聖上は、西洋の宮廷服を模した、胸に菊花葉を金繍した燕尾服型の礼服を着用された。
明治大帝は、ご自身が率先して洋服着用の範を示され、おかくれになるまでの40年間ずっと洋服で過された。
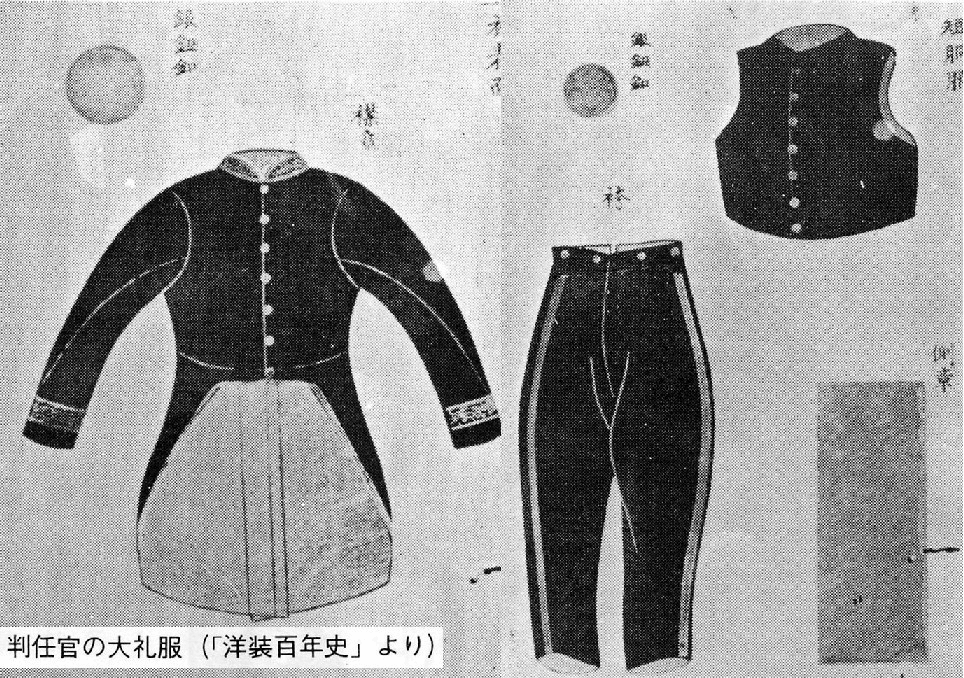 明治4年10月、征韓論が破れ、列国と修交を訂すべく、特命全権大使岩倉具視を長とする一行は、欧米各国訪問の旅に出発。
明治4年10月、征韓論が破れ、列国と修交を訂すべく、特命全権大使岩倉具視を長とする一行は、欧米各国訪問の旅に出発。
まずアメリカに行き、グラント大統領に謁見したときは、烏帽子に直垂の盛装で威儀を正していたが、その宿舎にワシントン府中の官吏と実業家1千名を招待したときは、アメリカの貴顕紳士を驚かすことになるのである。
……大使を初め一行の官吏理事官ことごとくドレスコート(食膳に用うる粧飾の衣服)またデンネルコート(通常礼服と呼ぶもの)を服し羅列して来賓を待つ。(久米邦武著『米欧回覧実記』)
というわけである。
また同行した林董の「後は昔の記」によれば、万事開国主義の折、束帯ではいけないという反省から、ヨーロッパ風の大礼服を制定する議がおこり、年少ではあるが留学の経験のある林が先行して、ロンドンのテーラーに調製させ、イギリスのビクトリア女王謁見のさいには一同初めて洋式の大礼服を着たのであった。
この大礼服は、イギリスの高官が、宮廷での儀式のさいや、使節として信任状奉呈の折に着るドレス、コートとほとんど同一型式で、胸や袖口の金繍文様が、イギリスでは月桂樹と樫の葉であるのに対し、桐花葉と日陰蔓の文様になっている。「日陰蔓(ひかげのかづら)」は大嘗祭の時左肩にかけるものであり、日本の故実にのっとって決めたものであろう。
万機ご一新の告諭いらい念願の大礼服がここに必要に迫られて急きょ制定され、明治5年11月5日大礼服制として、太政官布告(373号)をもって、
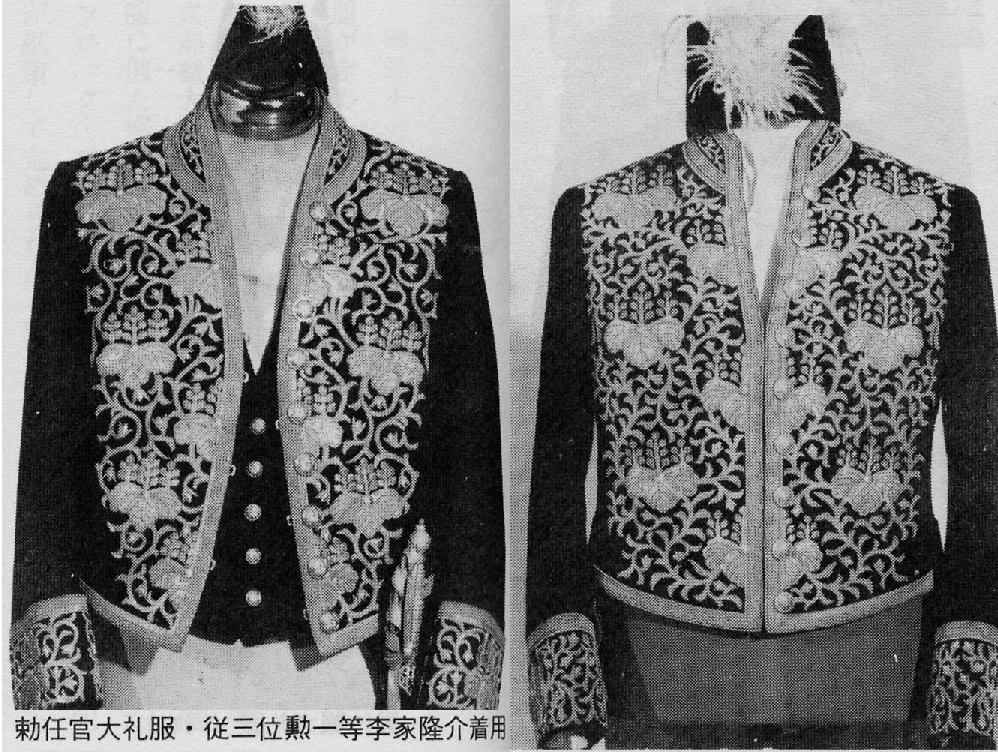 「爾今礼服には洋服を採用す」
「爾今礼服には洋服を採用す」
とされ、このとき大礼服だけではなく、通常礼服、陸軍服、羅卒服も制定されたのであった。
このとき大礼服は勅奏任官および判任官、非役有位者の各大礼服で、一般の通常礼となった。
大礼服の汎則は次の通りである。
- 帽ノ制ハ勅奏判任共同制ト雖モ右側章ノ繍式飾毛ノ有無刺繍ノ有無刺繍ノ精疎鈕釦ノ制ニ於イテ之レヲ大別ス
- 上衣ノ全部各処ノ飾章勅任ハ五七ノ桐ヲ用ヒ加フルニ桐蕾章ヲ稠密ニ絡繍ス。奏任ハ五三ノ桐ヲ用ヒ桐蕾章ハ勅任ニ比スレバ疎判任亦五三ノ桐ヲ用フト雖モ桐蕾章ハ奏任ニ比スレバ疎ナリ。
- 上衣飾章ノ部分勅任ハ襟。背・胸・袖・側襄・背端。奏任ハ襟・袖側襄・背端・判任ハ襟・袖ナリ。以上飾章及ビ上衣ノ周縁ニ勅任ハ雷紋ヲ繍附シ奏判任ハ無地ノ単線ヲ用ユベシ。
- 等級標條ハ両袖ノ飾章ニ繞繍ス其條線ハ巾一分其中間ハ八厘ナリ勅奏判任共各下等ヲ一條トシ上等毎ニ一條ヲ加フ。
- 鈕釦ハ勅任即チ金地ニ五七ノ桐、奏任ハ金地ニ五三ノ桐、判任ハ銀地ニ五三桐ヲ鏤メ而シテ上衣ニ用フルハ巾三厘ノ周縁ヲ凸彫ス。比他帽ノ右側章ニ附スル鈕釦アリ其制上衣ノ鈕銅ト同ジ。
- 等外官ノ服制ハ上下一般通常ノ礼服ヲ用ユ。但シ等外一等ヨリ四等ニ至リ各袖端ニ等級ノ標條ヲ紆フ。
- 非役有位四位以上ノ服制ハ勅任ニ准ジ五位以下ハ奏任ニ准ズ然レドモ飾章ハ御紋ヲ置クノ外桐蕾ノ唐草ヲ合繍セズ又背端章ハ円径二寸ノ御紋一個ヲ附ス。但シ四位以上帽ノ飾毛ハ黒色ヲ用ヒ、袴ノ両側章ハ電紋単章巾五分ヲ用ユベシ。五位以下は上ニ同ジクシテ袴ノ両側章ハ単線巾五分ノモノヲ用ユベシ。
上下一般通常礼服は黒ラシャ製の燕尾服型で、ラベルはショールカラー。チョッキ、ズボンは共に黒ラシャ製、帽は絹帽の指定であった。
何しろ洋服の知識が着る側も作る側も不十分であったから、その注文もむづかしく、また調製上非常に苦労があった。とりわけこれら礼服の調製は格式ある店が指名され、これを縫う職人も一流の腕自慢のものが選ばれた。数物屋(既製品商)と一つ物屋(高等洋服店)の業容もはっきり区別されようになった。

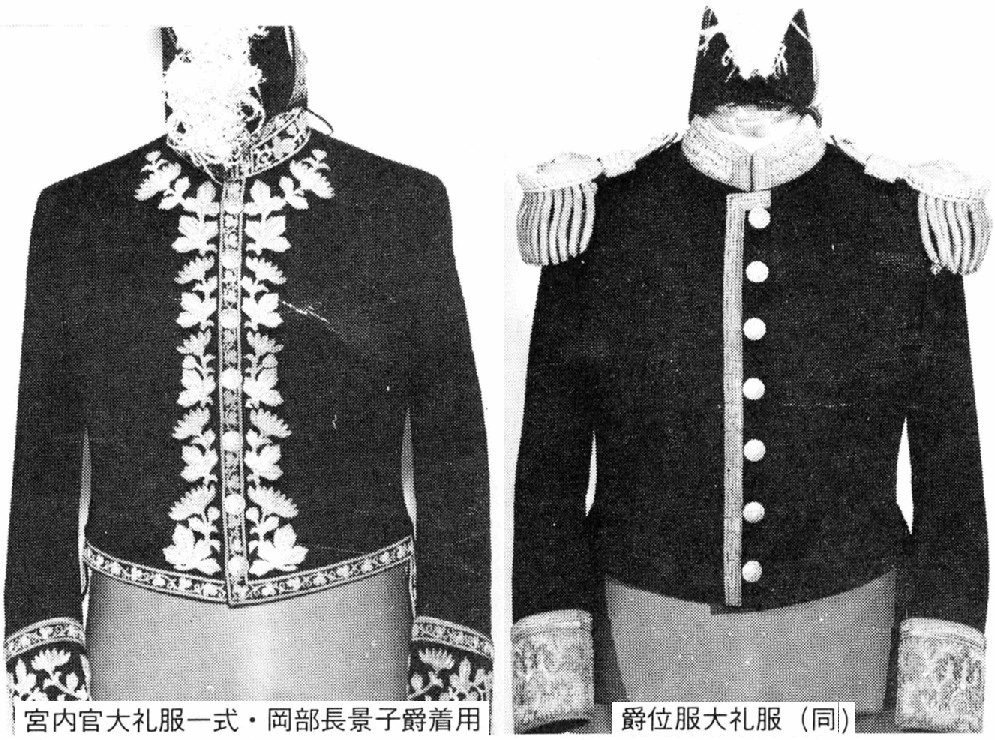 明治17年「爵位令」が発布され、それに伴い有爵者大礼服が定められた。肩にエポレットをつけた燕尾服型で、襟と袖につけた天鵞絨(びろうど)の紫・緋・桃・浅黄・黄の色により、公・侯・子・男の五爵を区分した。またこのとき、侍従職式部職大礼服として、帝政時代のロシアやドイツの文官大礼服に似た裾長のコートに胸から裾まで金モールの刺繍をした
明治17年「爵位令」が発布され、それに伴い有爵者大礼服が定められた。肩にエポレットをつけた燕尾服型で、襟と袖につけた天鵞絨(びろうど)の紫・緋・桃・浅黄・黄の色により、公・侯・子・男の五爵を区分した。またこのとき、侍従職式部職大礼服として、帝政時代のロシアやドイツの文官大礼服に似た裾長のコートに胸から裾まで金モールの刺繍をした フロック・コート型のもので、その豪華なムードを山県有朋が献策して定められたという。文様は菊枝で、勅任官と奏任官とではいく分違っている。この他に燕尾服で金繍のない中礼服、海軍士官の軍服に似た供奉服などがあり、明治44年に「宮内官服制令」として集大成された。昭和3年、大礼服には燕尾服型立襟、金繍の部分の少ない簡素なものになり、これは、爵位服、皇族服、文官大礼服とともに第二次大戦後廃止となった。
フロック・コート型のもので、その豪華なムードを山県有朋が献策して定められたという。文様は菊枝で、勅任官と奏任官とではいく分違っている。この他に燕尾服で金繍のない中礼服、海軍士官の軍服に似た供奉服などがあり、明治44年に「宮内官服制令」として集大成された。昭和3年、大礼服には燕尾服型立襟、金繍の部分の少ない簡素なものになり、これは、爵位服、皇族服、文官大礼服とともに第二次大戦後廃止となった。