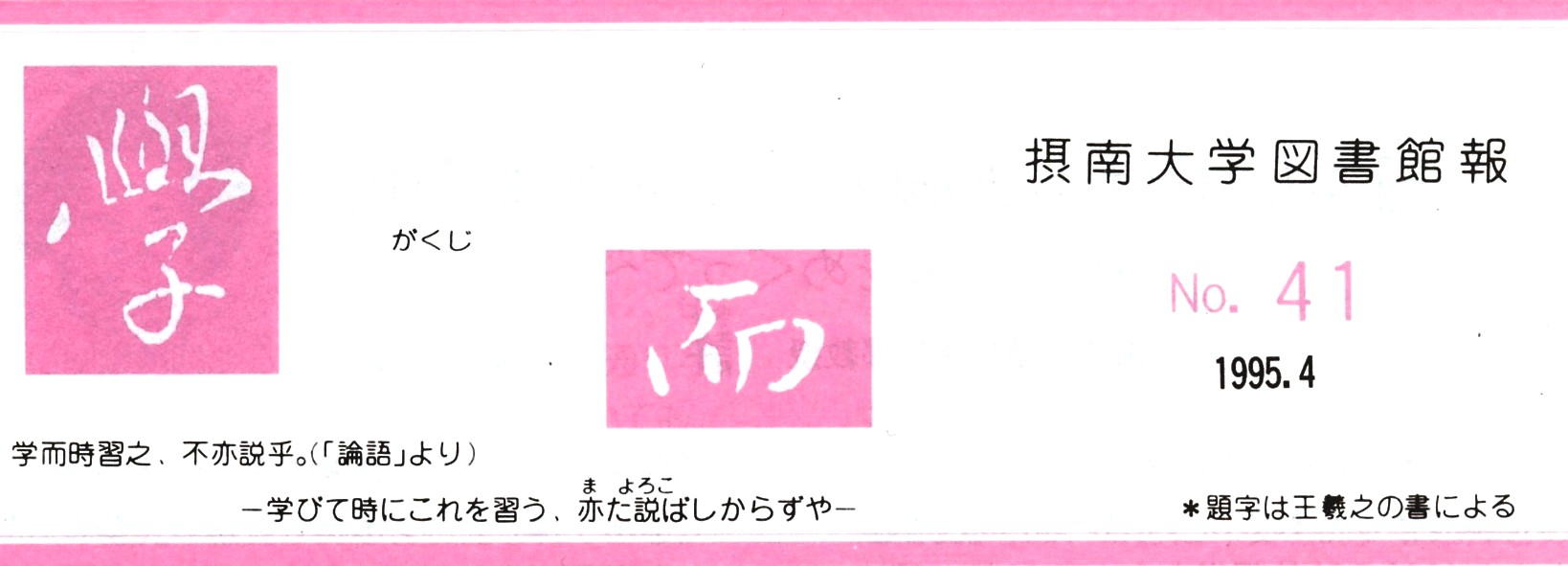
←前号 次号→
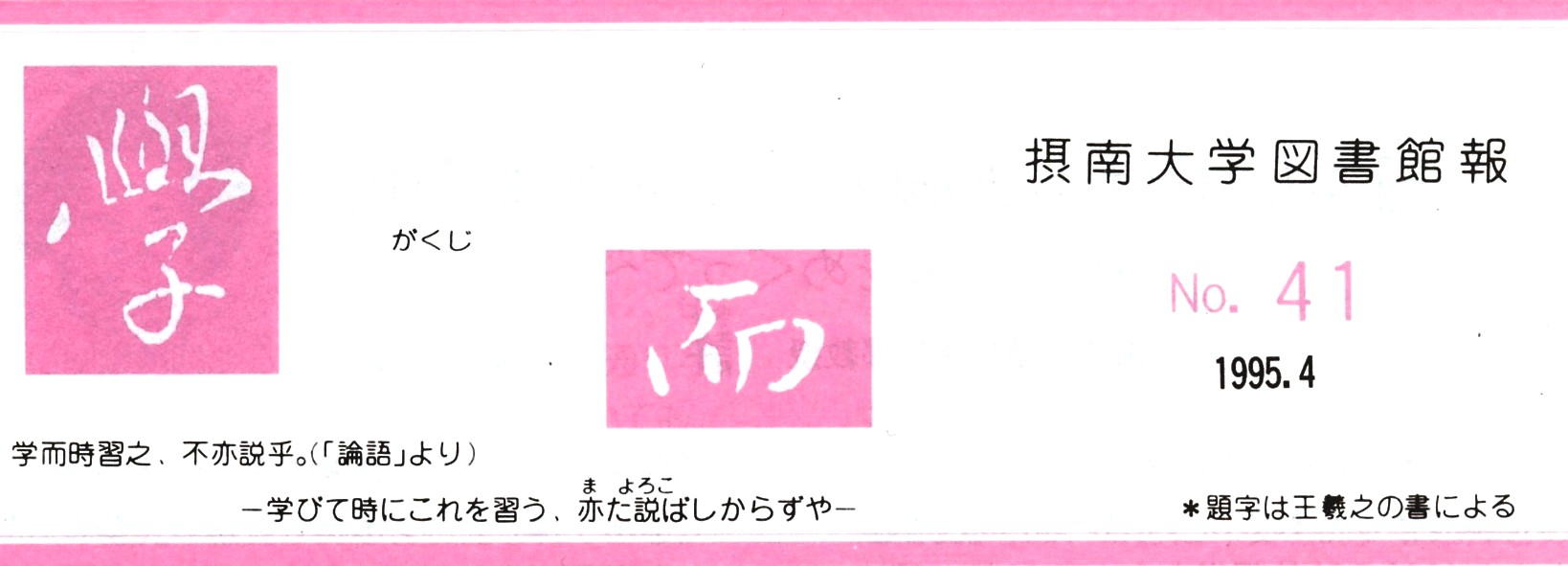
★ CONTENTS ★
今春の新入生へ

図書館長 田中 吉之助
(工学部機械工学科 教授)
新入生諸君、入学おめでとう。入学試験の難関を突破して、入学の歓びのなかに大学生活への希望に燃えていることと思います。
しかしながら、今春に限っては、その歓びに浸りきることのできない何かがあるのではないでしょうか。戦後50年の節目として新しい抱負を掲げて出発した1995年でしたが、その松の内が明けてすぐ、1月17日早朝、兵庫県南部大地震が発生しました。阪神大震災であります。乙亥(きのとい)の年に起こったこのたびの大震災は、1923年葵亥(みずのとい)の年に起こり、多数の犠牲者を出した、かの関東大震災から72年目にあたります。皆さんの中には身近な方を亡くした方もありましょう。負傷した人もありましょう。家屋に大きな被害を受けた方も多くありましょう。この原稿を書いている現在、地震発生以来1ヵ月になりますが、未だに20万人からの方々が避難所で過ごしております。このような時期に入学された皆さん方は、復興の意気に燃えるととともに、ますます学問に情熱を燃やしていただきたいと思います。
1991年4月のこの「学而」において田村満穂館長が、「フレッシュマンを迎えて」と題してFrancis Baconの随想録(Essays or Counsels Civil and Moral)の「学問について」の項に書かれている読書や読書法を紹介し、読書の目的は「熟考し熟慮するため」であり、また、読書は「充実した人間を作る」などとしておられます。同書のその「学問について」の項で、学問の必要性について、「熟練した人は仕事をひとつひとつ片づけ、おそらく細かい点について判断を下せるであろうが、全般にわたる勧告、業務の計画および整備は、学問のある人々から最も適切に出されるからである」と述べており、また「すばしこい人間は学問を軽蔑し、単純な人間はこれを感嘆し、賢い人間はそれを利用する」とも述べております。読書についても学問についてもたいへん示唆に富む含蓄深いことばであると思います。
昨年度、大学の後援会から刊行されましたUniversity Guideのなかで、私は「大学に入学し大学生となられましたからには、学問や大学生活に貪欲であってほしい、いや貪欲でなければならない」と新入生の方に申し上げました。その後、貪欲(トンヨク むさぼり)は、瞋恚(シンニ いかり)および愚痴(グチ おろか)とともに三毒のひとつであり、知恵を持って消すものであると教えられました。しかし、皆さんは学問や大学生活に対して強い強い意欲をもってほしいものを思います。そして、また、図書館もできるかぎり、有効に利用してほしいと思います。この大震災の年に入学された皆さんが、この災害に打ち克って、人の悲しみや苦しみをわかち合い、お互い扶け合いながら、一層の勉学に励まれて本当に意義ある大学生活を過ごされることを心から希望いたします。
CONTENTSへ
![]()
日本における外国人の受容と国際化
――勅令352号をめぐって――

国際言語文化学部 教授
許 淑真
外国人不法就労者の摘発が、マスコミで盛んに取り上げられるようになった80年代、わたしはその法的根拠となっている明治32(1899)年発布の勅令352号と施行細則省令42号の成立過程および成立当初の世論に関する資料を探し求めて、各地の資料館、図書館をハシゴしてまわっていた。1世紀近い歳月を経て、今なお堅持されている法令は、筆者の強い関心を引かずにおられなかったのである。
国立公文書館のマイクロフィルム収蔵目録のなかから、勅令352号に関する枢密院討議記録関係資料を発見したときは、静かな閲覧室のなかであやうく歓声を挙げるところだった。
明治32年は、欧米諸国との改正条約発効の年にあたり、これによって治外法権撤廃、内地雑居承認など、条約国国民の処遇は規定されたが、無条約国、清国、無籍国国民に対して、新たな法令を設定する必要に迫られた。清国人の処遇については、日清戦争宣戦布告の3日後(明治27年8月4日)、発布された勅令137号があったが、交戦国国民として、防諜的意図を含む、居住営業に制限を加えたものだったので、これに代わる法令の制定は焦眉の急となった。内務省は、清国人の処遇に関する新たな勅令案を草し、幾度か修正を加えながら、閣議請議を求めた。内務省が、清国人の居住営業等に対して、制限を幾分か将来に存続させる理由として挙げたのは、要旨次のとおりである。(1)清国において、日本人の居住その他に関し制限をおいている。(2)清国人は低賃金に甘んじているから、在日の欧米の会社は清国人を雇用している。日本の経営者にも影響するであろう。(3)日本の労働者の供給が、すでに受容を超過する趨勢にあるので、日本における労働問題が社会問題となる。(4)清国人は偽造貨幣の製造行使、贓物故買、紙牌賭博、幼女誘拐、人身売買、一夫多妻、居住衣服不潔、アヘン吸飲、守法の習慣の欠如など犯罪が多いので、日本の労働者と混交させると、悪習に染まる。(5)いったん雑居を許可すれば、他日弊害露見し、禁止しようとしても、利益既得の資本家の反対に遭う。
これに対して、外務省は異なる意見をもち、外相・青木周蔵は国際法・国際関係の見地から、反対の意見書を首相宛提出、請議を求めた。青木は清国において、日本人に対する居住等の制限は、日本人がかの地において治外法権・領事裁判権を有するためであり、領事裁判権を有しない清国人に対しては改正条約国の欧米諸国国民同様、内地雑居を認めるべきこと、労働上商業上の競争には、勇気と実力をもってこれに対抗すべきこと、日本の通商貿易上、日本商品最大の顧客となる清国人排斥の政策は執るべきでないことなどを反対の理由として挙げ、「欧米人といえども、必ずしも上等人ならざるがごとく、清国人といえどもことごとく下等人にあらず」と意見した。
明治日本においては、卑屈なまでに欧米に対して劣者意識をもち(例えば、内地雑居の可否をめぐって、賛成論者は白人と混血すれば、種族改良できると考えた)、脱亜入欧は社会的風潮となっていたが、青木のように中国に対して、伝統的な畏敬の念を抱いている者も少なからずいた。最終的に、閣議において、清国人全般を規制するのは峻厳に過ぎるので、規制範囲を労働者および行商に特定し、また、清国人と明示することは、対清感情上面白くないので、広義の文字を選んで、「条約若シクハ慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル外国人ノ居住及営業等ニ関スル件」として枢密院の議に付されるよう上奏された。
枢密院では、中国に関わったことがある外交官出身の副島種臣、大鳥圭介などは、清国の侮りがたきことと善隣友誼の必要を訴え、清国人にも欧米人同様開放すべき論を発したが、枢密官多数が内務省の意見に賛成し、わずかに制限範囲から行商を削除、別表のとおり可決された。付言しておくと、現在においても、政府レベルでは、法務省・労働省と外務省に類似の意見の相違があると伝えられている。
内務省は主として、労働市場問題と「文明」と相関する治安維持のふたつの側面から清国人労働者に対して受容を拒否し、外務省は国際的な見地から、異論を唱えた。現在においては、いわゆる3Kの職場には、労働市場の一般的状況とは無関係に、日本人労働者が就職したがらない事情があり、建て前上、国策として外国人労働者の受け入れを拒否、または取り締まりながらも、実際には、これに頼らざるを得ない事情があるのである。詳述は避けるが、実は、このような受容の仕方は、歴史的な日本の外国人に対する受容の形態を出ていないのである。つまり、幕府鎖国以来、日本では常に日本の社会構成上、空白名部分をおいてのみ外国人の進出を許容してきた。外国人をどのように受容しているかは、その国の国際化を計るバロメーターであり、十分な討議がなされるべき問題であると考える。
明治日本の対外意識は、常に西洋対東洋、文明対非文明の構図であり、その意識は、現在にいたっても大同小異であるといえよう。勅令352号は、まさに「文明的」な西洋との改正条約発効を目前にし、自己を「文明」側に位置づけた明治日本が、「非文明的」な東洋に対して、その受容態度を明らかにしたものである。
参考文献
(1) 国立公文書館マイクロフィルム公文類聚第23編2A-11類851
(2) 外交資料館所蔵外務省記録「大正13年帝国労働政策及法規関係雑件」M.T.3.7.1.5-1
(3) 許淑真「日本における労働移民禁止法の成立」『東アジアの法と社会』汲古書院1990
(4) 許淑真「労働移民禁止法の施行をめぐって」『社会学雑誌』7 1990
| 勅令352号 第一条 外国人ハ条約若ハ慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル者ト雖従前ノ居留地以外に於テ居住、移転、営業其ノ他行為ヲ為スコトヲ得但シ労働者ハ特ニ行政官庁ノ許可ヲ受クルニ非サレハ従前ノ居留地及雑居地以外ニ於テ居住シ又ハ其業務ヲ行フコトヲ得ス 労働者ノ種類及本令施行ニ関スル細則ハ内務大臣之ヲ定ム 第二条 前条第一項但書ニ違反シタル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス 附則 第三条 本令ハ明治三二年八月四日ヨリ施行ス 第四条 明治二七年勅令第137号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス |
| 省令42号 七月二四日 1.明治三二年勅令第三百五十二号第一条ノ行政庁ハ庁府県長官トスル事 2.明治三二年勅令第三百五十二号第一条ノ労働者ハ農業漁業鉱業土木建築製造運搬挽車仲仕業其ノ他雑役ニ関スル労働ニ従事スル者ヲ云フ事但家事ニ使用セラレ又ハ炊爨若クハ給仕ニ従事スル者ハ此限ニ在ラス 3.労働者ニ与ヘタル許可ハ庁府県長官ニ於テ公益上必要アリト認ムルトキハ之ヲ取消スコトヲ得ル事 |
あそび感覚図書館利用法
 オンライン検索
オンライン検索
参考文献は「○○○○」。
さあ、この本探さなきゃ。どこにある?
そんなとき、所在の有無は5F、6Fのオンライン検索機でスピーディに。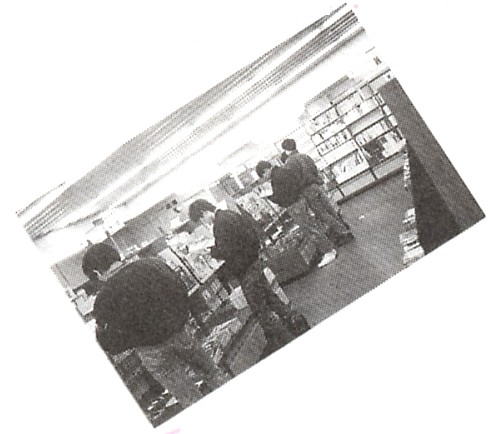
ワープロの達人
この4年間にワープロはぜひ上級者になっておきたいもの。
4Fで自由に使えるし、
貸し出しも受け付けています。
 読みたい本を買ってもらえるらしい
読みたい本を買ってもらえるらしい
ブックセンターで、読みたい本を発見。
カウンターで申し込んでくれれば、
10分で貸出OKの「速図くん」制度をはじめとする「希望図書購入制度」があります。
くわしくは係員にきいてね。
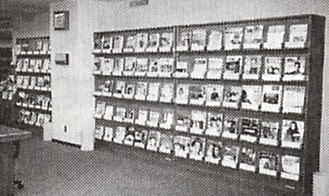 軽雑誌もあるよ
軽雑誌もあるよ
勉強ばかりが図書館利用法じゃない。
5F軽雑誌コーナーの本でこの春流行の服や
ロードショウをチェック!
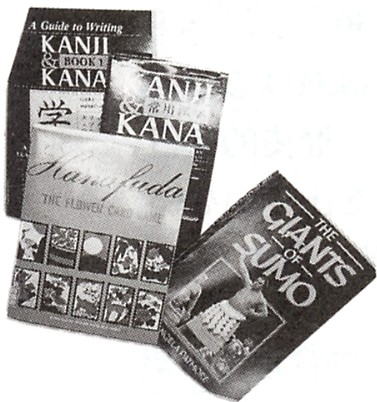 留学生のみなさんも
留学生のみなさんも
しっかりバックアップ
6F日本語・日本事情コーナーには外国語を併記し、
日本についてわかりやすく紹介した本を数多くそろえています。
グループ学習
さあ、いつものメンバーで試験勉強するよ、というときは、
3Fの閲覧室(自習室)で。
予約しておけば、貸切OKの部屋もあるので、
ゼミなどのミーティングなどにもご利用ください。
文献複写・相互貸借
学外の資料は、手に入らないものと思っている人が意外に多い。
あきらめないで、
係員がNACSIS-ILLを駆使して、
図書館間ネットワークで取り寄せましょう。
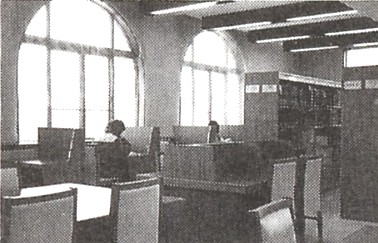
枚 方 分 館
薬学部の学生は2年生からこちらへ。
ぐっと落ち着いた雰囲気とアーチ窓がステキな分館が待っています。
CD-ROMで情報にアクセス
近頃話題のCD-ROMが操作できるんだから、
これは利用しない手はない。
例えば、膨大な新聞記事の中から知りたい事項に
キー操作ひとつでアクセスしたり。

休みだ! 旅行の計画だ!
学生の特権。
それはいつでも旅行に行けること
(ウラヤマシー)。
4Fのビデオ版「地球の歩き方」でシミュレーションした後は、
6Fのガイドブックコーナーの本をウエストポーチに、
いってらっしゃーい!
ついでに5Fには「時刻表」もあるという念の入れよう。
ニューメディアコーナー
コンピュータの時代にも、
ちゃんと用意のあるわが図書館。
6Fではフロッピー付きの図書も貸し出しています。
目印は本の背のパンダちゃんマーク。

就職戦線突破して、
立派な社会人になってね
昨年度より好評を博している就職図書コーナー。
職業選びの水先案内から、
実践ハウツーものまで、
いま6Fで一番回転していると
係員もオススメのコーナーです。
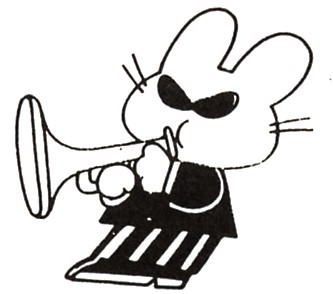
 AVルームで気分転換
AVルームで気分転換
4F視聴覚室ではCD、カセット、ビデオなどを観たり聴いたりもできます。
授業の合い間にコルトレーンもオシャレでしょう。
語学の教材もあります。
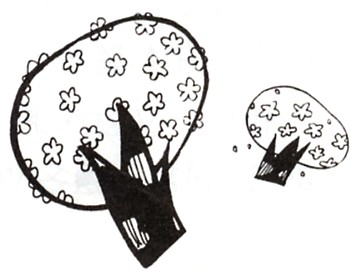 風 景
風 景
これがいいのもわが図書館の自慢のひとつ。
日当たりのいい、
お気に入りの席をみつけておいてください。
生駒山も見えるよ。
(S.Y.)
卒業生からのアドバイス
――私の図書館利用法――
図書館――この快適な空間――
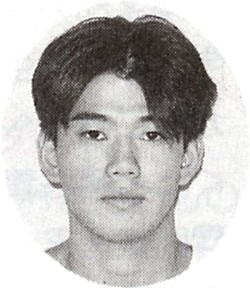
工学部建築学科 95年卒
木村 浩司
私が図書館を利用したのは、レポート、自由設計、卒業研究などの調べものをする場合がほとんどでした。適度な室温、座り心地抜群の椅子、それに大きな机。勉強をするには最適の場所で、あまりの心地良さに眠ってしまうことも1度や2度ではありません。
普段、講義の空き時間などに雑誌を読みに行ったときは、わりと空いていますが、テスト前や期間中になると結構混んでいて席がない場合がほとんどでした。そんなときは、本を借りるだけですぐ図書館を後にしましたが、専門書などは分厚いものが多く、3冊も借りるとやたら鞄が重くなるので、できるだけ図書館の中で用を済ませたほうが楽だと思います。
また、読みたい本があるけれど、本屋で買うのはもったいない、でも読みたい。そんなときに図書館に頼めば購入してもらえるので一銭も失うことなく読みたい本が読めます。これもひとつの利用法ではないでしょうか。
私の大学生活にとって、快適な空間と親切なお姉さんのいる図書館は、勉強の場であり、憩いの場であり、睡眠の場でありました。新入生の皆さんも図書館をうまく利用して、充実した大学生活を送ってください。
文献の探し方
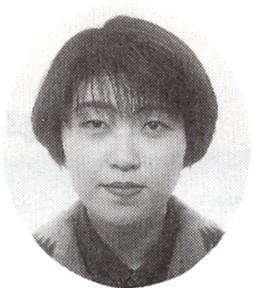
国際言語文化学部 95年卒
高瀬 八重
自分の論文やレポートのテーマにあった文献があるのか、それは本校にない場合どこにあるのかといったことに対して検索方法を知らない人が多い。口述する方法は、文献を探すのにたいへん役に立つものだと思うので覚えておいてください。
まず従来からある文献目録から探す方法である。これは国立国会図書館をはじめ、さまざまな研究所などが発行しており、科学、人文などの分野別で検索できる。図書の題名や著者がわかっている場合や、自分のテーマのキーワードさけでも探すことができる。そこで、テーマにあった題名のものを多数見つけることができ、またその所在も確認できるだろう。しかし、もっと新しい文献を調べるにはナクシスが有効である。図書の題名や著者がわかっている場合、探すのは容易である。ナクシスは、他大学の図書館とも協力しているので、所蔵大学すべてを確認できる。そして、一番近い大学に貸出を依頼するか、直接出向いて閲覧させてもらうかのどちらかの方法になる。貸出の依頼は、ある程度時間がかかるので、所蔵大学が近い場合は大学に直接出向いたほうが早い。その場合、依頼書を必要とされるが、カウンターに申し出れば発行してくれる。学部生はナクシスを利用する場合、カウンターに申し出ると図書館員が代行してくれる。私はこういったシステムを最大限に利用して、よい卒論を仕上げることができた。
お世話になった図書館
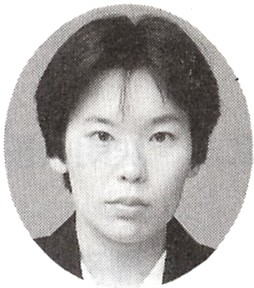
経営情報学部経営情報学科 95年卒
波多 千代子
テーマが書いてある小さな紙切れ1枚を手に、図書館で本を必死に探す――NTTを大学推薦で受験するための学内選考を数十分後に控えた私の姿です。学内選考は、グループに分かれて討論を行うというものだったので、図書館に行って本を探し、何を話すのかについて話し合いました。これが私がNTTに入るための第一歩です。
この時以外にも図書館では、いろいろとお世話になりました。本学の図書館には、新聞、雑誌をはじめあらゆる分野の本が並んでいます。自分の探している本は、コンピュータ検索できますし、大工大の図書館からも学生証を提示するだけで本を借りることができます。大学のレポートは、高校の宿題と違って自分で資料を探さなくてはなりません。私もレポートが出る度に図書館を利用していました。大抵の本は揃っていました。要望としては、経済・経営関係に関してはもっと新刊を入れてほしいということです。
また、テスト期間中は、テスト勉強のために、個人用の机をよく利用しました。他にも休講などで時間が空くと、音楽を聴いたり、ビデオを観たり、ワープロを借りてレポートを作成したりといろいろ活用させていただきました。
しかし、もっと有効に図書館を活用すれば、自分にとって有用な本に出会えたと思います。そう思うと非常に残念です。新入生の皆さん、自分なりの図書館活用法を見つけて、自分なりの図書館活用法を見つけて、まめに図書館へ足を運んでくださいね。
図書館で一味違う大学生活を!
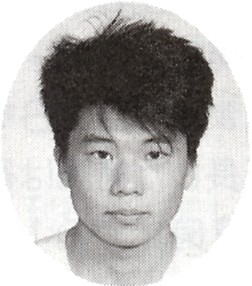
法学部 95年卒
入江 拓也
私が図書館へ頻繁に足を運ぶようになったのは、3年生からでした。講義と講義の間の空き時間を利用して、資格、就職試験の自習や、ゼミのレポートを作成していました。特にゼミのレポートに関してですが、どうしてもその専門書が必要となってきます。自分で購入するにはたいへんお高い買い物となってしまいます。そこで、図書館の利用となるのですね。私の所属している法学部の専門書に関しては、ゼミの参考文献には十分な内容と量が所蔵されていると思います。他学部においても同じ傾向にあるようですから、専門、一般教養に関係なく、レポートの課題が出れば、迷わず図書館に行きましょう。
また、卒業論文作成において、主題の一部であった臓器移植の法律部門の専門書が、なかなか大型書店にもなかったのですが、本学図書館には5冊もの専門書があり、たいへん助けられました。
また、難しい本ばかりではなく、週刊誌やスポーツ新聞といったものまで置かれています。通学の時間を利用して、図書館で借りた本で時間つぶしという利用法もあります。大学生活というものは、自己の意思でどうにでも変わってしまいます。図書館へ足を運べば運ぶほど、そのよさがわかってくると思います。空き時間に友人と食堂や教室でおしゃべりも悪くはないですが、図書館で一味違う大学生活を見つけてはいかがでしょうか。
CONTENTSへ
94年度 本学教員からの寄贈著書
94年度中に本学教員から寄贈いただいた著書は次のとおりです(敬称略)。
ご厚意に感謝するとともに厚く御礼申し上げます。
武吉次朗(国際)
「盲流」(東方書店。1993)
「現代中国30章」(大修館書店、1994)
高島邦子(国際)
「20世紀アメリカ演劇」(国書刊行会、1993)
篠原愛人(国際)
「カリブ海植民者の眼差し」(岩波書店、1994)
依田千百子(国際)
「金徳順昔話集」(三弥井書店、1994)
宍戸通庸(国際)
「言語学習ストラテジー」(凡人社、1994)
光藤景皎(法)
「口述刑事訴訟法<上・中>」(成文堂、1992、1994)
「ワークブック刑事訴訟法」(有斐閣、1994)
安藤哲行(国際)
「老いぼれグリンゴ」(集英社、1994)
岡田 定(経情)
「効果のみえる情報システム」(共立出版、1994)
井上 治(工)
「新版 例題解説 構造力学」(理工図書、1995)
CONTENTSへ
開館時間延長実施結果
94年度後期試験期の開館時間延長は、当初1月17日から実施予定でしたが、17日に発生した阪神・淡路大震災のため日程を変更し、本館・分館とも1月19日から30日までの土曜日を除く8日間実施しました。延長した時間は従来どおり本館が18時から19時までの1時間、分館が20時までの2時間でした。期間中の利用状況は、別表のとおりです。1日平均の利用者は本館約53人、分館約151人で、93年度の後期試験期の本館約71人、分館約133人に比べると、本館は減少し、分館は増加という結果になっています。
| 開館時間延長期間中の延長時間帯の利用者 | ||
| 実施日 | 本館(人) | 分館(人) |
| 1 | 35 | 127 |
| 2 | 26 | 130 |
| 3 | 46 | 189 |
| 4 | 71 | 169 |
| 5 | 54 | 150 |
| 6 | 78 | 184 |
| 7 | 92 | 143 |
| 8 | 24 | 123 |
| 合 計 | 426 | 1215 |
| 1日平均 | 53 | 151 |