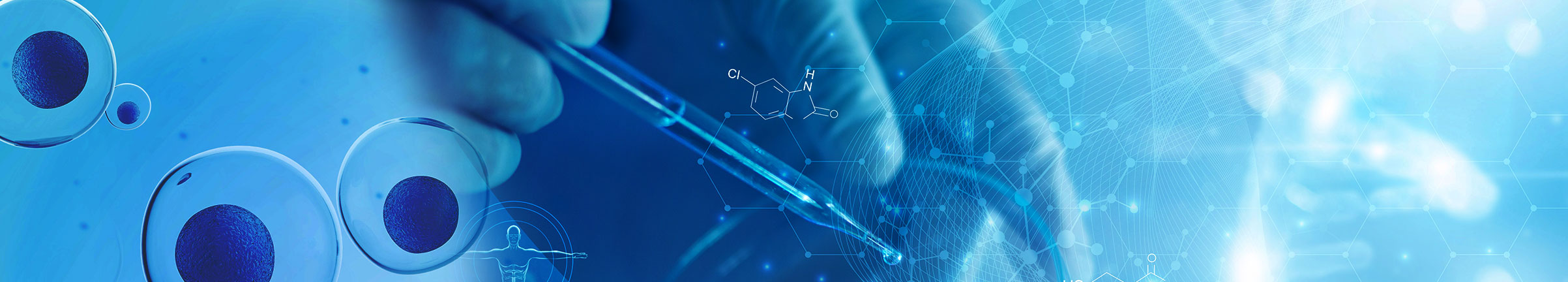
第15・16回ライフサイエンスセミナーのお知らせ
生命科学科主催のライフサイエンスセミナーが、2018年1/9(火)と1/16(火)にプチテアトルで開催されます。ご興味のある方は是非ご参加ください。 下記にご講演の要旨を掲載いたします。
「マウス精子形成における特異的転写活性化メカニズム」
北海道大学大学院理学研究院 生物科学部門
生殖発生生物学講座 木村敦
京都府立大学生命環境科学研究科 佐藤雅彦
虫こぶ(plant gall)とは,昆虫が自身のすみかや餌とするためにホスト植物に形成させた異常組織である。虫こぶは,本来の植物には見られない高度な組織形態を持っていることから,昆虫の分泌する何らかの誘導物質により,植物の発生プログラムをハッキングすることで,植物の形態形成を高度に制御していると考えられる。しかしながら虫こぶ形成は,野外で行われることや虫こぶ形成昆虫の宿主選好性のため,実験室内でモデル植物を用いての研究がほぼ不可能であり,その形成メカニズムの分子生物学的な理解は,ほとんど進んでいない。
我々は,シロイヌナズナ幼植物にゴール形成昆虫の虫体破砕液を処理した時の形態変化に注目し,モデル植物シロイヌナズナを用いた植物におけるゴール形成メカニズムの解析法の開発を試み,虫こぶ形成メカニズムを総合的に解析する手法,Ab-GALFA(Arabidopsis based-Gall Formation Assay)法の開発に成功した。Ab-GALFA法は,ゴール形成過程の昆虫個体の虫体破砕液(虫液)を作成し,虫液をシロイヌナズナ幼植物に処理した後,細胞の形態変化をオルガネラマーカー,植物ホルモンマーカー,細胞骨格マーカーなど様々な蛍光タンパク質マーカー発現植物を用いて,共焦点レーザー顕微鏡で観察,更に,次世代シークエンサーを用いて原因遺伝子産物の発現様式を網羅的に解析することによりゴール形成メカニズムを分子生物学的に解析する方法である。
本講演では,リーフマイナーからゴール形成者に転換し,カンコノキ(コミカンソウ科, Glochidion obovatum)に膨らみのあるゴールを形成するタマホソガ(ホソガ科, Caloptilia cecidophora),ヒサカキ(モッコク科, Eurya japonica)に平たいゴールを形成するヒサカキホソガ(ホソガ科,Borboryctis euryae)とヌルデ(ウルシ科, Rhus javanica)に五倍子と呼ばれる巨大な虫こぶを形成するヌルデシロアブラムシ(アブラムシ科, Schlechtendalia chinensis)を解析に用いることで,Ab-GALFA法によって明らかとなった虫こぶ形成の分子メカニズムの実体について解説する。

