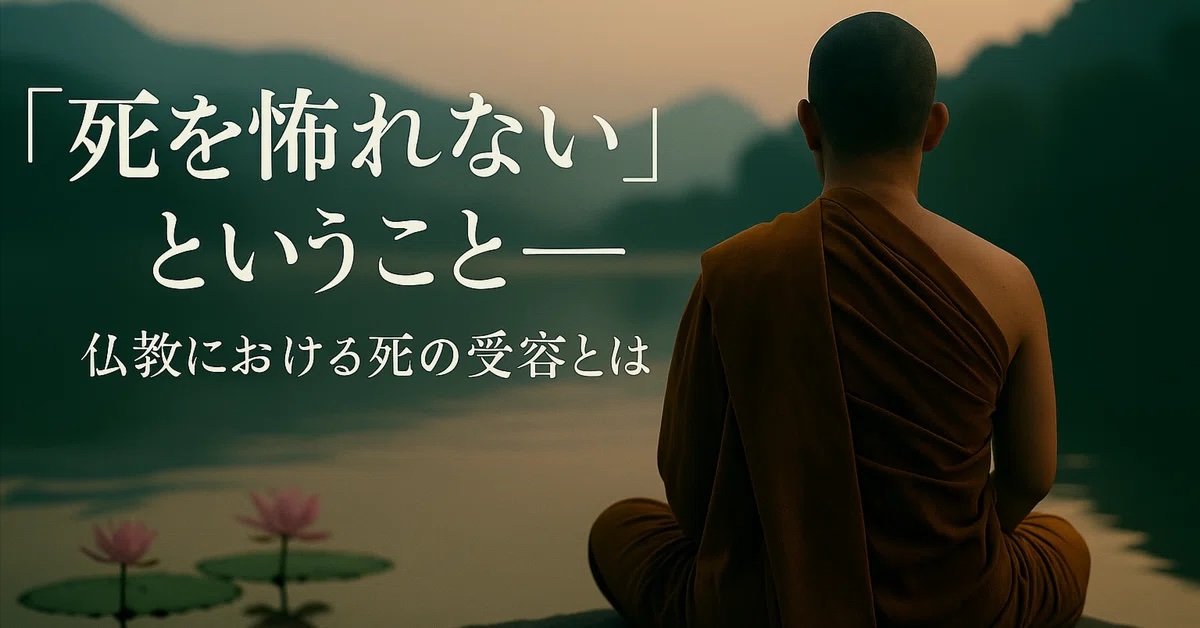
人間にとって「死」は、避けられない現実であると同時に、最も強く恐れを抱く対象でもあります。医学の進歩によって寿命は延び、痛みを軽減する手段も増えましたが、「死」という存在そのものに対する根源的な不安や恐怖は、むしろ現代社会において深まっているようにも見えます。私たちは、この「死への恐れ」とどう向き合えば良いのでしょうか? 仏教は、この問いに対し、時代を超えて私たちに静かなまなざしを向けてきました。

避けられない問い。私たちはこの「死」とどう向き合うのか。
「無常」「無我」「縁起」「空」――死への根本的なまなざし
仏教の教えの根本には、「無常」「無我」「縁起」「空」といった、この世界のありようを深く見つめる思想があります。
まず、**「無常(むじょう)」**とは、この世のあらゆるものは常に変化し続け、永遠不変のものは何一つないという真理です。私たちの命もまた、その例外ではありません。「死」は特別な終わりではなく、生の一部としてあらかじめ組み込まれている、ごく自然な現象であると仏教は教えます。
私たちは「死」を、すべてが失われる「終わり」だと捉えがちです。しかし仏教では、「私(自己)」という存在もまた、固定した実体を持たないと説きます(**「無我(むが)」**)。私たちは「自分」という確固たる存在があり、それが死によって失われることを恐れます。けれども、仏教の視点では、「私」は五蘊(ごうん)――色(身体)、受(感受)、想(イメージ)、行(意思)、識(意識)――という要素の集合に過ぎず、それは常に変化しているものです。「私」が死によって完全に消滅するというよりも、「私」そのものが常に流動的で、変化の中にある、と捉えるのです。
さらに、**「縁起(えんぎ)」**とは、すべての存在は他の存在との関係性によって生まれ、存在しているという教えです。つまり、私の命もまた、他者や自然、そして過去から続く無数の因縁のつながりの中にあり、孤立したものではありません。死は、私という個の終焉ではなく、ひとつの関係の形が変化するだけ――そう捉えることも可能です。そして、**「空(くう)」**の思想は、これらすべての存在が固有の実体を持たず、相互依存の中で成り立っているという、さらに深い智慧へと私たちを導きます。

移ろいゆくもの。その中に、いのちの真理が宿る。
「死を観る」実践――恐れと親しむ仏教の修行
こうした仏教の教えを、単なる知識としてではなく、実践の中で深く体得する方法として、「死を観る」修行があります。例えば、タイやミャンマーのテーラワーダ仏教では、遺体を観察する「屍観(しがん)」や、日々死を思念する「死随念(しずいねん)」といった修行が行われます。これらは死を怖れる心を克服するためではなく、むしろ死を日常的に受け入れ、親しみ、命の儚さや尊さを深く観じるための実践なのです。
日本の禅僧・良寛は、「うらを見せ おもてを見せて 散るもみじ」という有名な句を残しました。これは、人生の表も裏も、喜びも悲しみもすべて見せたまま散っていく紅葉のように、死もまた自然の一部として受け入れ、生と死を分けない心を象徴しています。

静かに、ただ見つめる。恐れと共に、いのちの儚さを観じる。
死を恐れることを否定しない仏教のまなざし
たとえ理屈として「死は自然なものであり、受け入れられるはずだ」と理解していても、いざその瞬間が近づいたとき、あるいは大切な人を失ったとき、私たちの心は簡単には納得できません。恐れや悲しみ、不安や喪失感が、理屈を超えて激しく押し寄せてくるのです。それは決して弱さではなく、人として当然の、自然な反応だと仏教は考えます。
仏教の道は、そうした感情を「排除すべきもの」として扱いません。むしろ、押し寄せる恐れや悲しみと共に静かに坐り、それらを無理に追い払うことなく、ただ「あるがまま」に見つめることが修行のひとつなのです。呼吸とともに心を落ち着け、揺れる心のままに「いま、ここ」に身を置く。そうした丁寧な実践のなかに、死と生を対立させない、深い受容のまなざしが育まれていくのです。

恐れを抱く、そのままで。仏のまなざしは、すべてを受け入れる。
死を受け入れるとは、いのち全体へのうなずき
「死を怖れない」とは、死を完全に克服し、感情を麻痺させるという意味ではありません。それはむしろ、死を含めたこの命の全体に深くうなずき、ありのままを受け入れていくこと。死があるからこそ、今ここに生きているこの一瞬一瞬が、かけがえのない輝きを放つのだと、仏教はそっと語りかけてくれます。
「死を怖れない」ことは可能か? その問いに対する仏教の答えは、「死を怖れてもよい。ただ、その恐れや悲しみの奥にある、いのちの静けさに触れてごらん」というような、やさしく、しかし深い智慧に満ちたものなのです。
公開日: 2025年7月30日
著者: 大塚 正人