経済学部
FACULTY OF
ECONOMICS
FACULTY OF
ECONOMICS
経済学部で身につけられる経済学的思考は幅広い業界で必要とされています。摂南大学の経済学部は、講義での学びだけでなく、実社会に飛び出し、フィールドワークをはじめとした体験型学修を軸に実践力を高めていきます。また学生の興味関心に合わせて5つのコースからいずれかを選択し、専門性を磨きます。
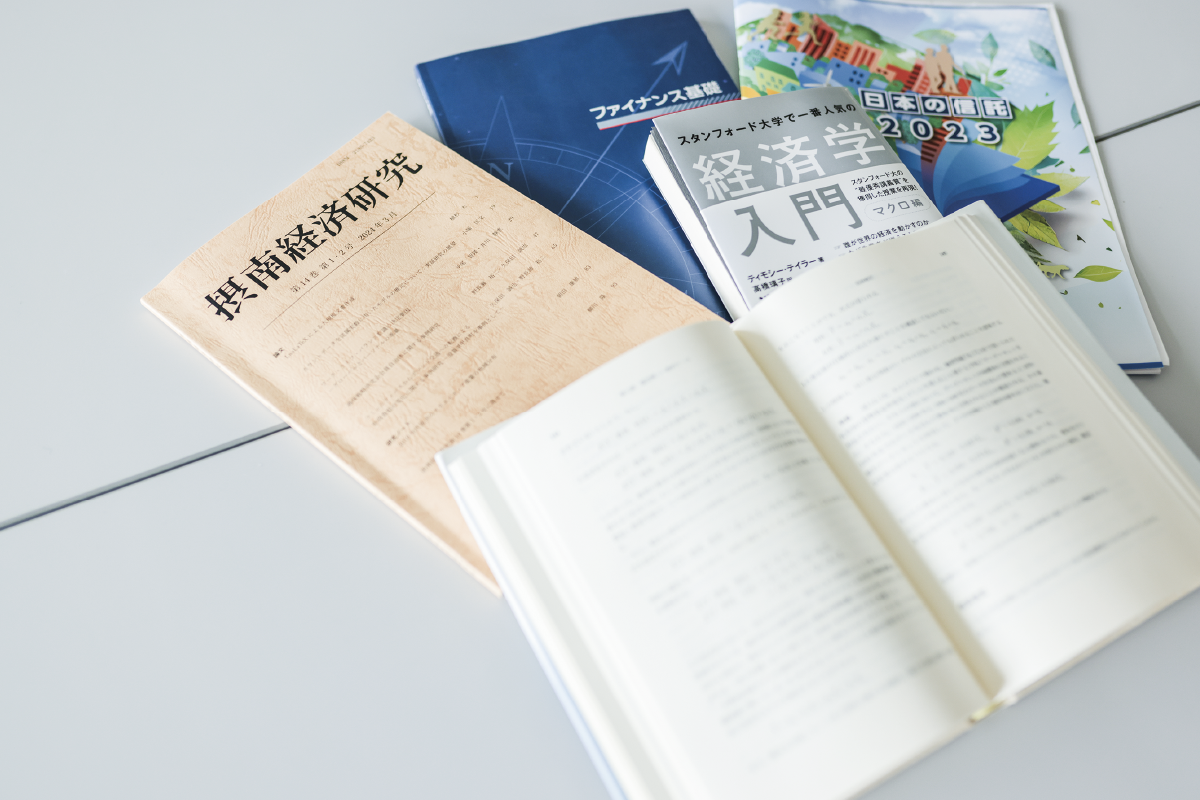
経済学科の特長
経済学科
国際経済コース 地域経済コース 観光経済コース ビジネス経済コース 金融・不動産経済コース
経済学部では、ゼミ活動やフィールドワークで最新の理論を実践的に学び、社会の問題を解決に導く人材を育成します。2年次から自分の興味関心や将来の進路を見据え、5コースのいずれかに所属し、専門性を高めます。なお、他コースの科目を履修することも可能です。さらに、コースでの学びに加え、データ分析や AIスキル等を身につけるため「経済データサイエンスプログラム」も履修できます。IT関連資格の取得とともに情報通信・IT関連業への就職を支援します。このほか、ファイナンシャル・プランナー(FP)、簿記、宅地建物取引士等の資格取得や公務員試験に役立つ授業も提供し、学生の成長を促します。
摂南経済ゲストレクチャー

経済・社会の第一線で活躍されているゲスト講師をお招きして、各分野の現状や課題について学びます。講演を通じて、現実の経済・社会の動向を知るとともに、卒業後の自身のキャリア形成のイメージが持てるようになります。これまで、外交官や企業の経営者、自治体の行政担当者や市長、テレビ局のプロデューサーなど多彩な分野のゲストをお迎えしています。
経済実践演習

実地教育をさらに実りあるものにしているのが、各コースの経済実践演習です。コースの学びの領域に合わせた体験学修として、課題解決型の演習を実施します。国内の企業、ものづくり工場、ホテル、自治体等でのフィールド調査を通じて、経済活動の理解を深めるとともに問題解決を探ります。また、国内のみならず、海外の大学やグローバル企業を訪問し、現地の経済情勢や異文化への理解を深めるプログラムもあります。
在学生
「大学で成長したい」という想いを胸に、多彩なフィールドワークや
さまざまな資格試験に挑戦しています
藤井 愛弓さん
経済学部 経済学科
4年次(京都府/西城陽高校出身)
経済を学ぶことは社会に出てからも役に立つと考えて経済学部を志望しました。摂南大学の経済学部は1年次に基礎をじっくり学んだうえで、2年次からのコースを選択できるので、入学前に興味ある分野がまだ定まっていない人にもピッタリです。私は1年次の「地域経済入門」で学んだ地方創生や地域財政の話が身近でおもしろいと感じ、地域経済コースを選択しました。授業で印象深いのは、文化政策の経済的側面に焦点を当てる「文化政策論」です。中間レポートでは各自が選んだ美術館や博物館などを訪れ、「展示の充実度」「地域イメージや街づくり・観光への貢献度」といった観点から2つの施設を比較しました。美術館などの施設について地域経済の視点で考えるというのは新鮮で、視野が広がったと感じます。ゼミではゼミ長を務め、愛知県岡崎市の観光伝道師として活躍する人気YouTuberが観光に与える効果を経済学的視点で考察したり、東京上野の美術館を訪れて美術館の地域における役割を考えたりと多彩なフィールドワークをとおして地域経済について学修しました。3年次の2月にはイタリア海外研修に参加し、欧州の経済や文化産業について学びました。また、摂南大学を選んだ決め手の1つに「資格試験サポートの手厚さ」があります。実際に資格サポートセンターの資格試験対策講座などを利用し、宅建や秘書検定といった資格を取得できました。
内定者
プロスポーツチームとの合同研究で得られたリーダーシップと
マネジメント力が、就職活動での大きな武器になりました
清水建設株式会社 内定
森下 拓海さん
経済学部 経済学科
2024年3月卒業(大阪府/清風高校出身)
摂南大学の経済学部のゼミでは、企業やプロスポーツチームと合同で研究ができます。私はプロスポーツチームと研究ができるゼミに所属しました。観客動員数増加を目標とした研究で、実際の観戦者を対象にアンケートを実施して「目に見える」形でのデータを分析したり、心理学を応用した行動経済学を用いて「目に見えない」行動要因の分析を行ったりしました。そんな経済学の手法と理論を用いた多角的な調査をもとに具体的施策の提案まで経験することができました。3年次にはゼミでリーダーも務め、学部の研究発表会では最優秀賞もいただけました。また、私は教職課程も並行して履修し、教育実習にも全力で取り組みました。そのなかで「聞く力」や「伝える力」がより磨かれたと思います。就職活動では、ゼミ活動や教職課程で身につけたリーダーシップとマネジメント力を生かせる企業を探した結果、内定先を志望しました。実際に合同研究や教育実習の経験は、就職時の強いアピールポイントになったと感じます。入社後は、信頼関係を築き上げながら「森下だから任せられる」と言ってもらえるような人材になり、地域や国のシンボルとなる現場に携わりたいです。そのためにも、一人ひとりの個性を生かしながらチームとしてのバランスを取りつつ、最大限のパフォーマンスを引き出すことのできるリーダーへと成長していきます。
卒業生
摂南大学の豊富なグループワークで磨いたディベート力を生かして、
全従業員中1位の成績をおさめることできました
株式会社南都銀行
吉田 裕哉さん
経済学部 経済学科
2020年3月卒業
現在は銀行の本店営業部にて、法人渉外や個人渉外などを行っています。法人渉外では1人で300社近くを担当しています。会社の決算書や経営計画などから将来の収益性を分析して融資をしたり、企業と企業をマッチングしたり、不動産の紹介を行ったりと多彩な施策を実行します。ときには数十億円のお金を動かすこともあり、非常にやりがいを感じられる仕事です。また2023年度は保険販売部門で全従業員中1位になりました。入行後すぐに結果を出せたのは、摂南大学の授業やゼミでグループワークやディスカッションをたくさん行い、プレゼンテーションスキルやディベート力を培えたことも要因だと感じます。現職を志望したのは、高校時代からでした。そのため、大学入学時から銀行への就職を目標として勉強していました。特に利用したのは摂南大学の資格サポートセンターです。少人数制かつ資格試験のプロの先生が丁寧に教えてくださる資格試験のセミナーのおかげで、簿記2級やファイナンシャル・プランナー2級といった就職後にも生かせる資格を取得できました。なにより、「学ぶ習慣」を身につけられたことは大きな成長につながったと感じます。この習慣は、金融業界で働くうえで欠かせない専門知識の継続的なインプットに繋がっています。
ゼミ紹介
植杉 大教授
地域経済と空間データサイエンス
本ゼミでは、地域経済・観光等に関するトピックスを広く研究しています。特に、地域を研究対象とするうえで欠かせない空間データを収集、加工、分析するための実践的演習を通じて、プログラミング能力およびデータ分析能力を養います。また、学外におけるフィールドワークや社会連携活動を積極的に行い、具体的な問題発見・解決能力を高め、地域の発展に貢献できる「データサイエンス人材」を育成することを目的としています。
郭 進教授
社会調査とデータ分析による経済学の実践
社会調査の実習を通じて、経済理論だけでなく現実の経済に対する理解を深め、地域が抱える課題などを経済学の視点で解決することをめざす。さらに、統計学の知識を活用し、コンピューターを使用して各種データを分析するスキルを習得することを目的とする。
小塚 匡文教授
地域振興と観光
地域振興や観光業に関する出来事を取り上げ、それらについて学んでいきます。グループごとに地域振興や観光業について調査・研究した成果は、他大学との合同共催で発表します。また、これらの学びに関連するものとして、京町家を活用した旅館でフィールドワークを実施します。このフィールドワークでは旅館の見学だけでなく、実際に就業体験もします。民間企業が携わる町おこしのあり方、そして宿泊業の現場について、理解を深めることができます。
田井 義人教授
経済学の視点からの地域医療・
福祉政策及び地域創生(振興)の研究
少子高齢化社会において持続可能な経済社会を支える仕組みとしての公共サービスや地域医療・福祉政策、地域創生(振興)政策及び観光政策について研究する。その際、経済学の基本的な理論を踏まえたうえで、現場の課題を抽出し、対応策の実践とプロセスに注目し研究する。
野長瀬 裕二教授
地域産業と企業家活動
経済のグローバル化、日本の少子高齢化という環境下で、中小ベンチャー企業や大企業の事業創造が、どのように地域産業の活性化をもたらすのか。
企業家活動を通じた地域産業活性化、地域の行政や金融機関によるその支援などについて学ぶ。
野村 佳子教授
様々な観光事象と観光振興
情報のあり方が変化し、情報量が飛躍的に増えるなか、観光業においても顧客のニーズが多様化してさまざまな観光の事象が発生しています。コロナ禍で観光は大きな打撃を受けましたが、需要は戻りつつあり、コロナ収束後の観光振興について最適解を考えていく必要があります。本ゼミでは、様々な観光事象について考察を行い、地域活性化に資する観光のあり方をテーマとして研究を進めていきます。
朴 景淑教授
戦略的経営と財務分析
私たちの身近な環境から経済学・経営学へアプローチします。新製品(新サービス)の開発戦略や企業分析、業界の戦略分析など、テーマは多様です。理論的な学習だけではなく、ケーススタディやフィールドワークを重視した実践的な演習を中心に、グループワーク・ディスカッション・プレゼンテーションなどを行うことでコミュニケーション能力を高めます。
原田 裕治教授
日本経済の制度分析
現代経済の動きをよく観察すると,市場取引のための行動だけでなく,さまざまな制度によって影響を受けた人々の行動が経済において重要な役割を果たしていることが見て取れます。例えば日本では新入社員の新卒一括採用が制度的に行われ,大学生は3年次の終盤から一斉に本格的な就職活動を始めます。また新卒採用市場では,求人・求職活動の支援を行う企業が活発な競争を展開します。さらに求人企業は時間とコストをかけて新卒社員の採用活動を行うだけでなく,採用した新入社員の訓練や人員配置を工夫しながら企業の競争力を高めていきます。こうした仕組みは日本独自のものです。社会特有の制度やルールが経済の動きに大きな影響を与えているわけです。
このゼミでは,こうした各種制度の役割に着目して日本経済で生じているさまざまな課題について考えていきます。
平尾 智隆教授
キャリアの経済学
ゼミでは,教育,労働,社会保障といった我々の人生(キャリア)に関わる諸問題を経済学の側面から理解し,学習していきます。教育,労働,社会保障に関わる諸問題を自身のキャリア形成上の問題であると同時に社会の大きな問題として考え,研究を進めていきます。
持永 政人教授
学外活動を活用した地域・観光産業の研究
本演習では実際に活動している地域産業や観光産業において、主に学外での調査・事例研究をとおし、地域・観光に関わる産業・企業のあり方を実践的に研究することを目的とする。
柳川 隆教授
デジタル化社会のビジネス(プラットフォームビジネス)
デジタル化社会の到来とともに、「プラットフォームビジネス」と呼ばれる、ユーザーや関連事業者を結び付けるイノベーションを起こすビジネスが急速に成長している。プラットフォームビジネスは、Google、Apple、Meta(旧Facebook)、Amazon、Microsoft(GAFAM)をはじめとしてアメリカを中心に繁栄しており、これがアメリカ経済の繁栄と日本経済の停滞の一因である。他方、近年では欧州を中心にプラットフォームビジネスへの規制も進んでいる。そこで、プラットフォームビジネスの歴史・現状・課題について学び、日本を中心にプラットフォームビジネスの成功・失敗や課題、あるいは欧米や日本でのプラットフォームビジネスへの規制のあり方などをテーマとして研究する。
朝田 康禎准教授
日本の地域経済における観光・旅行による地域活性化策を探る
コロナ禍前まで日本は世界でも類を見ないほどの勢いで外国人観光客が急増していました。そのため観光・旅行は日本経済の活性化策として注目されています。しかし、観光経済があまりにも急激に成長してきたため、観光が経済全体に与える影響についての分析や調査は不十分なところがあります。この演習では観光経済に対する現実的な理解を深め、フィールドワークなどをとおして実践的な調査方法を身につけます。
道和 孝治郎准教授
日本に関わる国際経済の問題について考える
近年、円ドルレートの円安化が進み、それが物価を高騰させているように、日本経済に悪影響をもたらしている状況がある。他方、TPPへの参加やインバウンド需要の拡大といった状況は、日本経済に対して一般的に好都合なものといえる。本ゼミは、こういった日本に関わる国際経済の問題について研究する。
名方 佳寿子准教授
日本経済の問題点を考える
現在の日本ではさまざまな問題が生じています。例えば、国レベルでみていくと、オーバーツーリズム、人材不足や長時間労働問題、少子高齢化、所得格差、男女格差、地域の過疎化、財政赤字、個人レベルでみていくと、子供の貧困、待機児童問題、非正規雇用、失業、生活保護の受給、年金問題などがあげられます。学生には自分の興味のある課題について調べ、原因・対策(経済政策)を考えていってほしいと思います。
野口 義直准教授
地球環境問題と経済社会の未来
現在、気候変動、プラスチック海洋汚染、生物多様性の減少など、さまざまな環境問題が地球規模で深刻化しています。地球環境問題の多くは、18世紀の産業革命以来の化石燃料の大量消費、さらには20世紀半ばからの人間の経済活動の急拡大を原因としています。21世紀の現在、環境保護と人間の経済活動を両立する「持続可能な発展」が求められています。環境保護と経済活動の両立を実現するために、経済社会をどのように変化させていけばよいのか。このゼミでは、地球環境問題と人類の経済社会の過去・現在・未来について考察していきます。
村瀬 憲昭准教授
実践的な学びを通じて、課題解決を探る。
経済のグローバル化が進み、国境を越えた人や物の行き来が活発になるにつれて、地球温暖化や自然破壊、貧富の差の拡大など地球規模で取り組むべき課題が増えています。このゼミでは、主に急速な経済発展を遂げつつあるアジアの開発途上国が抱えている経済的・社会的格差や環境悪化に関する課題に着目し、各国の政府・企業・市民による取り組みと、それを支援する国際協力について研究しています。また、開発途上国へのスタディツアーも行っています。
若城 康伸准教授
問題解決にデータと分析で挑む
いまも世界のどこかで起きている戦争・紛争など、人々の対立が解消されない理由のひとつに、「何を問題と考えるか」が文化や立場によって異なることが挙げられます。価値観や感情を共有することは難しくとも、「事実」と「論理」なら文化・立場の違いを超えて共有できるかもしれません。本ゼミでは、事実を「データ」で、論理を「分析」で積み重ねて問題解決に取り組む基礎力を養い、より適用範囲が広く、現実的な解決策について研究します。
羅 鵬飛講師
世界経済におけるタイムリーな諸課題の研究
当ゼミでは、世界経済におけるさまざまな課題について研究を進めます。国際経済状況を把握しながら,国際金融市場のタイムリーな変化をフォローします。現在足元で起こっているタイムリーな課題を扱うことで、今皆さんが生きている「現在の」世界経済への理解を深めていきたいと考えています。
経済学部
詳しくはこちら