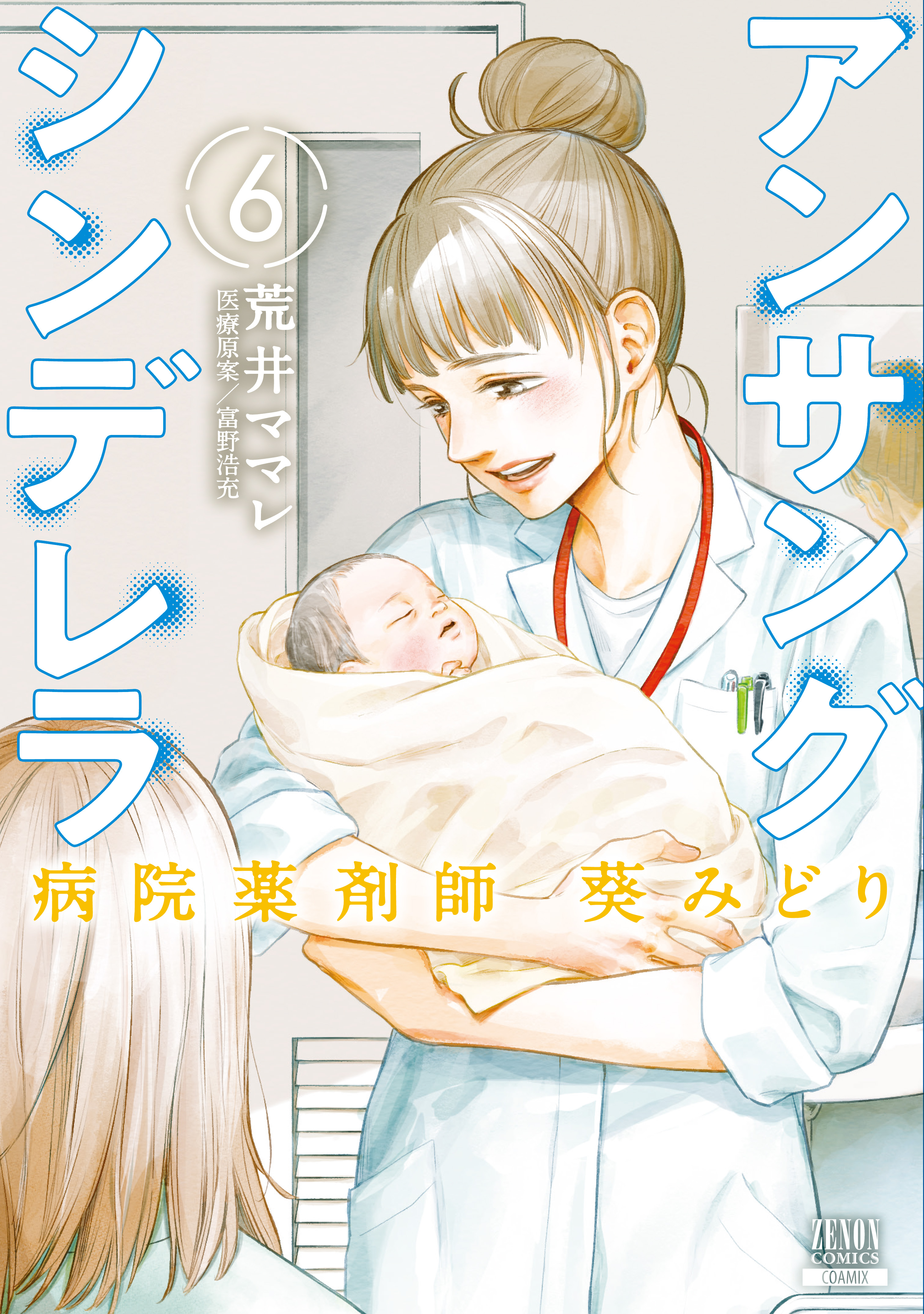6卷 44〜46ページ(第27話)
① 薬学のアイデンティティ
(第1話、第27話)
パネルディスカッションにて
6卷 44〜46ページ(第27話)
白坂善之さん(1998年4月入学)
富野先生の方向性として、アンサングシンデレラでは「薬剤師は必要なもの」ということを題材に、【薬剤師の存在意義】がテーマということはよくわかっています。漫画を読んでいて、一般の人たちも『薬剤師ってちょっとキラキラしたいい感じ』と思って見ているのかなと思いました。一方、何か既視感というか、単なるヒューマンドラマというか、結局、薬剤師がいるのか、いらないのかも、一般の人にとっては『なんとなく薬剤師がいる方がいいんだ』という感じになっていると思うのです。自分の性格上、漫画をネガティブに読んでしまうのですが、コミュニケーションということを一つの言い訳にしながら、薬剤師の存在と職能をありきたりなものにしているのではないか、と。アンサングシンデレラはどこに向かってるのかな、と。富野先生、アンサングシンデレラという漫画のゴールは何でしょうか。
富野浩充先生
「実は私はストーリーに口出ししないのです。ストーリーは原作者の荒井ママレさんが描きたいものがあります。漫画の内容がヒューマンドラマに拠っていると思うこともあります。その一方で私は、『薬剤師がまず一般に認識されれば良いな』というゴールを目指していたのですが、この漫画がドラマ化もされて薬剤師が一般に認識されたので、もう思惑通りです。でも、その先の話ですよね。恐らくこの漫画に対して、薬剤師の玄人の人たちに対してもそうなのですが、どこに向かって──薬剤師の職能も含めて──薬剤師の存在意義、考えていなかったですね。どこに向かって…」
白坂善之さん
「その『薬剤師の存在意義』という流れで、私のような大学教員が与えられた使命としての質問に入ってくるのですが。私の専門は薬物動態で、大学では学生に対して、『薬剤師になるにあたって、薬学のアイデンティティは薬物動態だ。薬物動態ができない者は薬剤師になれない。』とかむちゃくちゃなことを言いながら授業しています。その中で第1話から薬物動態の話が出てきたり、第27話ではデパケンの母乳中への移行の話があり、あれは我々にとってのADMEに当たるところなのですが、第27話の中で薬剤師が「今の服薬を続けても母乳を通して乳児への影響は考慮しなくても良い」との趣旨のセリフがありました。あれは本当の意味でいうと、サイエンスに基づいてその寄与率とか色々なものを我々は打ち出してやってきているのです。薬物動態は多分薬剤師の仕事に直結していて、エビデンスベースドになるのですが、ほとんどの薬剤師は本当の意味でそれを知っているのだろうかと思うのです。
6卷 44〜46ページ(第27話)
富野浩充先生
研究者と現場は役割が違うところがありますね。現場で働いていると研究者の成果を利用させていただいているという立場ではあるのですけれども。結局、本当の意味でエビデンスベースドができているのかと聞かれるとどうなのかなって。ただ、データを引っ張ってきているだけなのですかね。
白坂善之さん
ですからという意味ではないのですが、これから医師や歯科医師との圧倒的な差を見せていく時に、これから医療が個別化療法というところに発展していく中で、「データを引っ張ってきているだけ」ではなく、サイエンティストの域に入った薬剤師として、数値的に、パラメーター的に、きちんと理論的に議論して、医師とは異なる次元の領域の能力を持っていくというところが薬剤師の生き残る道の一つではないかと。薬剤師がいなくなったら絶対に大変なことになるというところが、今でもTDMとかもありますけど、そういう部分が重要ですよねっていうことを思いました。
在校生(上村凌太、2019年4月入学)が考えたこと・感じたこと
薬の投与において代謝・排泄という要素は、体内の薬の消失に関わる重要な点であるが、特に代謝は大きな個人差の発生する要素といえます。医療が発達してきた現代において、薬物動態の概念は過去に比べてより重要になってきていると考えます。遺伝子検査をすることで代謝能力の判定を行うこともできるため、患者一人ひとりに対してより適切な医療を提供することができます。このように個別化した医療が行われている現場において、薬剤師が薬の専門家として活躍するには薬物動態学を理解しておく必要があるのではないかと考えました。
<語句説明>
・薬物動態学:服用した薬がどのように体内でどのような動きをするのかを数学的に解析を行う学問。
・ADME:吸収、分布、代謝、排泄を総称したもの。これらは全ての薬が体内で受ける過程であり、薬物動態を考える上で最も基本的なものとなる。
・エビデンスベースド:エビデンスベースドメディスンのこと。科学的に証明されているデータを根拠としておこなわれる治療を指す。
・TDM:治療薬物モニタリングのこと。体内の薬物濃度の少しの違いで、薬の効果や副作用の発現が大きく変わる薬に関して、実際に薬を使用する患者一人ひとりの肝機能や腎機能を考慮したうえで、適切な量の薬が使用されているかをモニタリングするというもの。
<参考文献>
書籍名:図解薬剤学 改訂6版
著者名:森本擁憲 他
出版社名:南山堂

メールでのお問い合わせは24時間365日受付中!
電話対応時間:平日9:00~17:00(定休:土日祝日)