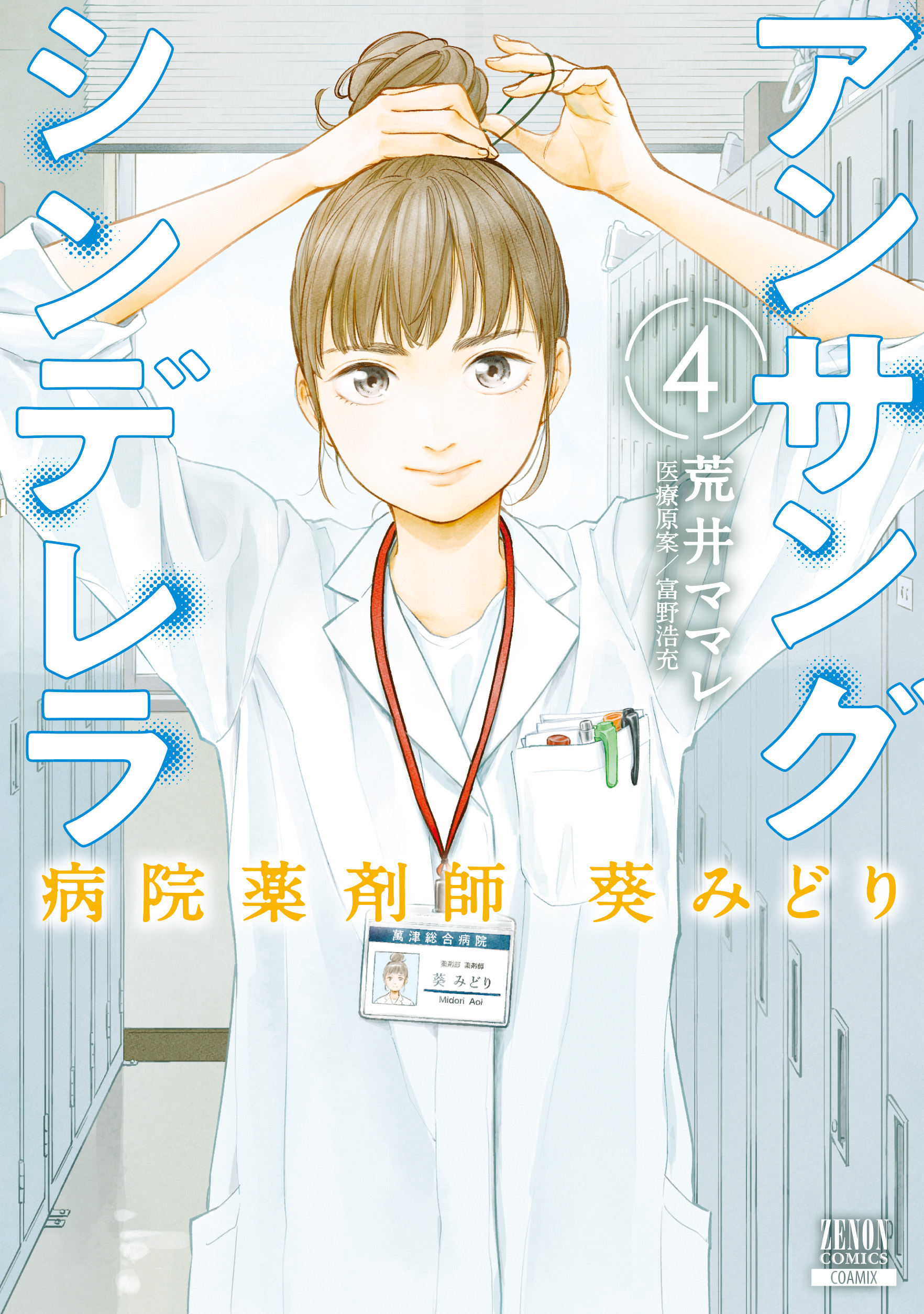4卷 147〜148ページ(第20話)
⑦ 地域医療に役立つ薬局
(第20話)
パネルディスカッションにて
4卷 147〜148ページ(第20話)
松永光樹さん(2002年4月入学)
私は3年ほど前に独立という形で薬局を作らせていただきまして、ちょうど4年目に入りました。今、私を含めて薬剤師が10名いて、事務員も6名雇用して、枚方の地域医療に貢献できるように、外来と在宅医療の業務を真剣にさせていただいています。第20話に出てくる笹の葉薬局の社長の「その地域社会に必要な薬局と、もう胸を張って言える」というコメントがありましたが、まさに私自身がそういう薬局を目指しており、この話を読んだ時に、自分のモチベーションがすごく上がって、もっと頑張っていこうと思いました。富野先生が第20話の医療原案の依頼をいただいた時に、薬剤師として何かエピソードがあったならば、お聞かせください。私自身、笹の葉薬局の話がすごく好きなので、富野先生にそういうエピソードがあるのかなと思ったので、お聞きしたいです。
4卷 147〜148ページ(第20話)
富野浩充先生
いや、難しいですね。まず、笹の葉薬局はモデルがあります。漫画で取り上げている話の中で私が絡んでいるのは1~2割くらいです。例外的に当直の話は私が書いたものが8~9割使われましたが、医療的な部分以外は私が考えるよりも漫画家の荒井ママレさんが考えた方が感動する話ができるので、任せています。ほかに、第1話の薬物動態の副作用の話は入れて良かったと思います。連載を始めた頃の方が結構、試行錯誤していたので、思い入れは強いですね。
白坂善之さん(1998年4月入学)
薬局と病院の繋がりを取り上げている回があると思います。どういう思惑であの話を入れたのかということと、連携は本当にどれぐらいできているのかなと気になりました。確かに病院で治療された方を最終的には近くの薬局でみていくようになるとは思うのですが、どれぐらい連携をとれているのかな、と。
富野浩充先生
うちの病院はそれほど多分取れていないです。漫画では合同カンファレンスみたいなシーンを作ったのですが、編集さんから「理想を言ってくれていいよ」というふうに言われて、そういう話をちょっと練っているときに、日本薬剤師会学術大会とかで、知り合いの全国の人と話をしていて、調査してみたりして、うちは全然できていないとか、うちはできているみたいという話になりました。
松永光樹さん
うちの薬局は病院の薬剤部と連絡を取るというより、地域連携との連絡が正直多いですね。退院された方の在宅医療において、訪問看護を選んで、あと薬局はどこを選ぶかという時に、地域連携の方から「ちょっとお願いできないでしょうか」という依頼が多いですね。
富野浩充先生
確かにうちの病院もそこを通してやっていますね。地域連携という部署があり、そこの担当者が主体になっています。
松永光樹さん
後はソーシャルワーカーとお付き合いが多いというのが、私の現状と思います。
在校生(植田健太、2019年4月入学)が考えたこと・感じたこと
4卷 170〜172ページ(第20話)
4卷 170〜172ページ(第20話)
パネルディスカッションの中で出てきた笹の葉薬局は、第20話、『長く「看る」こと』で登場する薬局です。主な患者は終末期や認知症、歩行が困難な高齢者で、在宅医療に特化した薬局です。笹の葉薬局の社長は、地域の医師、訪問看護師、ケアマネジャーなどと連携を取り合い、患者を診て退院後も安心して家で過ごせるような環境を作ることで、「地域社会に必要な薬局だと胸を張って言える」というように発言しました。
医療ソーシャルワーカー(MSW)とは、保健医療機関等において患者や家族の相談にのり、社会福祉の立場から経済的・心理的・社会的問題の解決、調整、社会復帰を支援する方のことを指します。相談援助を行う仕事は他にも、ケアマネジャー、保健師、社会福祉士、民生委員、生活相談員などがありますが、介護はケアマネジャー、保険指導や健康診断は保健師、地域住民の相談は民生委員、特別養護老人ホームなどに配置されているのが生活相談員ということになり、役割はそれぞれ異なります。医療ソーシャルワーカーは、怪我をしたり、病気になったり、高齢者が要介護状態になった場合、その後のことについて誰に相談したら良いか分からないというような方に、必要な情報提供を行ったり援助を行う仕事です。近年では高齢化社会が進み、療養や障害によって支援を必要とする人が急増しており、医療ソーシャルワーカーに対する社会的なニーズは極めて高くなりつつあります。
近年、高齢化社会の急速な進行に伴い、在宅医療のニーズが高まってきています。実際に、少し前のデータにはなりますが、平成26年に厚生労働省が行った調査によると、最期を迎えたい場所は自宅が49.5%、病院が17.9%であるのに対して、実際に最期を迎える場所は自宅が12.6%、病院が80.3%となっており、住み慣れた場所で最期を迎えられていない人が多いのが実情です。そのため、他の医療従事者や医療ソーシャルワーカーなどと連携をとることで在宅医療を行い、終末期医療に関わることで少しでも多くの人が住み慣れた場所で最期を迎えることのできる環境を作ることができる薬局が地域医療に役立つ薬局であると私は考えます。他にも、病気にかかる前の患者、いわゆる未病期の患者に対してセルフメディケーションや運動面、食事面でのアドバイスも行うことで、地域の人々の健康に貢献したり、地域の人々が24時間相談できるような環境がある薬局についても、地域医療に役立つ薬局であると私は考えます。
【参考文献】
・医療ソーシャルワーカー - 職業詳細 - Job Tag - 厚生労働省