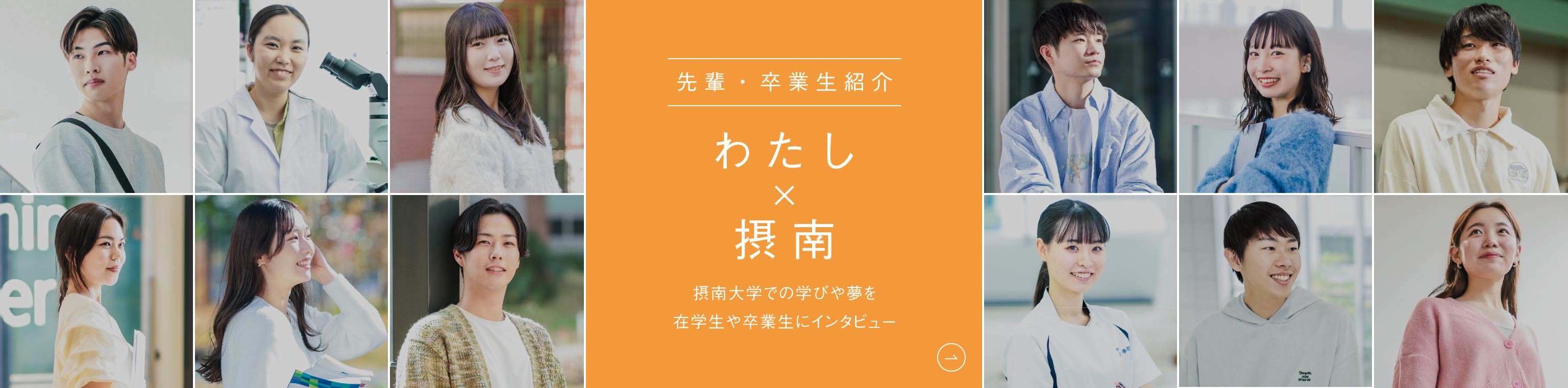教育研究上の目的
分子生命科学や生体生命科学を修得し、医療、環境、食糧等の分野において、高度な専門能力を持つ人材を養成することを目的とする。
3つのポリシー
ディプロマ・ポリシー(DP:学位授与の方針)
所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けたうえ、次の要件を満たし、かつ、修士論文の審査および最終試験に合格した者に修士(理学)の学位を授与します。
科学技術者倫理
[DP1]
社会人として規範やマナーを守り、生命を扱うものとしての高い倫理観を有している。
専門実践力・数理能力
[DP2]
生命科学に関する幅広い基礎知識と学際的な視野を身につけ、社会に貢献できる。
コミュニケーション力
[DP3]
英語の文献や資料から情報を的確に得て研究できる能力や、英語の講演を傾聴できるコミュニケーション能力を有している。
[DP4]
研究成果を学会で発表するプレゼンテーション能力を有している。
課題解決能力
[DP5]
分子レベルで生命現象をとらえ、解析や応用ができる知識・能力を有している(分子生命科学系)。
[DP6]
細胞や生体レベルで生命現象をとらえ、解析や応用ができる知識・能力を有している(生体生命科学系)。
[DP7]
課題に関する情報の収集とその分析、問題解決のための計画の立案などができる思考力や創造力を身につけている。
カリキュラム・ポリシー(CP:教育課程編成・実施の方針)
ディプロマ・ポリシーに掲げる目標を達成するため、次のとおり教育課程を編成・実施します。
科学技術者倫理
[CP1]
生命科学の研究を通じて研究成果の適切な取扱いや倫理観、社会人としての規範やマナーを身につけるために「理工学特別研究」を配置する。
専門実践力・数理能力
[CP2]
基礎科目では、卒業した学部で生命科学を学習していない学生や学習したが能力不足の学生が分子生物学と細胞生物学の基礎能力を身につけるための科目を配置する。
[CP3]
選択科目では、学習課程を体系的に履修するために分子生命科学系と生体生命科学系に分けて関連する学問分野を体系づけた教育を行い、さまざまな知識を応用する能力を身につけるための科目を配置する。
[CP4]
生命科学を俯瞰的に見られるよう、各分野でのトピックスを基礎から紹介し、興味を持たせながら広い知識を身につけるために「生命科学トピックス」を配置する。
コミュニケーション力
[CP5]
研究分野の英語論文を要約したプレゼンテーションを行い、専門英語能力、コミュニケーションやプレゼンテーションのスキルを身につけるために「ゼミナール」を配置する。
[CP6]
研究成果を中間報告会、修士論文公聴会および学会などで発表する機会を設けることによりプレゼンテーション能力を身につけるために「理工学特別研究」を配置する。
課題解決能力
[CP7]
研究成果を修士論文としてまとめることにより論理的思考や問題解決能力を身につけるために「理工学特別研究」を配置する。
アドミッション・ポリシー(AP:入学者受入れの方針)
本専攻のディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーを理解し、学士課程レベルの学力および次に掲げる資質・素養を有する人を求めます。
科学技術者倫理
[AP1]
社会人としての基本的なマナーを身につけている。
[AP2]
生命を扱うものとしての高い倫理観を身につけようとする意欲を持っている。
専門実践力・数理能力
[AP3]
英語で書かれた生命科学に関する学術論文の内容を説明できる。
[AP4]
生命現象に興味を持ち、幅広い基礎知識と学際的な視野を身につけようとする意欲を持っている。
コミュニケーション力
[AP5]
卒業研究の内容を他人に伝えるコミュニケーション能力とプレゼンテーション能力を有している。
[AP6]
研究成果を関連する学会で発表しようとする意欲を持っている。
課題解決能力
[AP7]
学士に相当する基礎学力と問題解決に柔軟な思考力を有している。
[AP8]
科学機器を用いて実験を遂行し、得られたデータの意味を解釈できる。