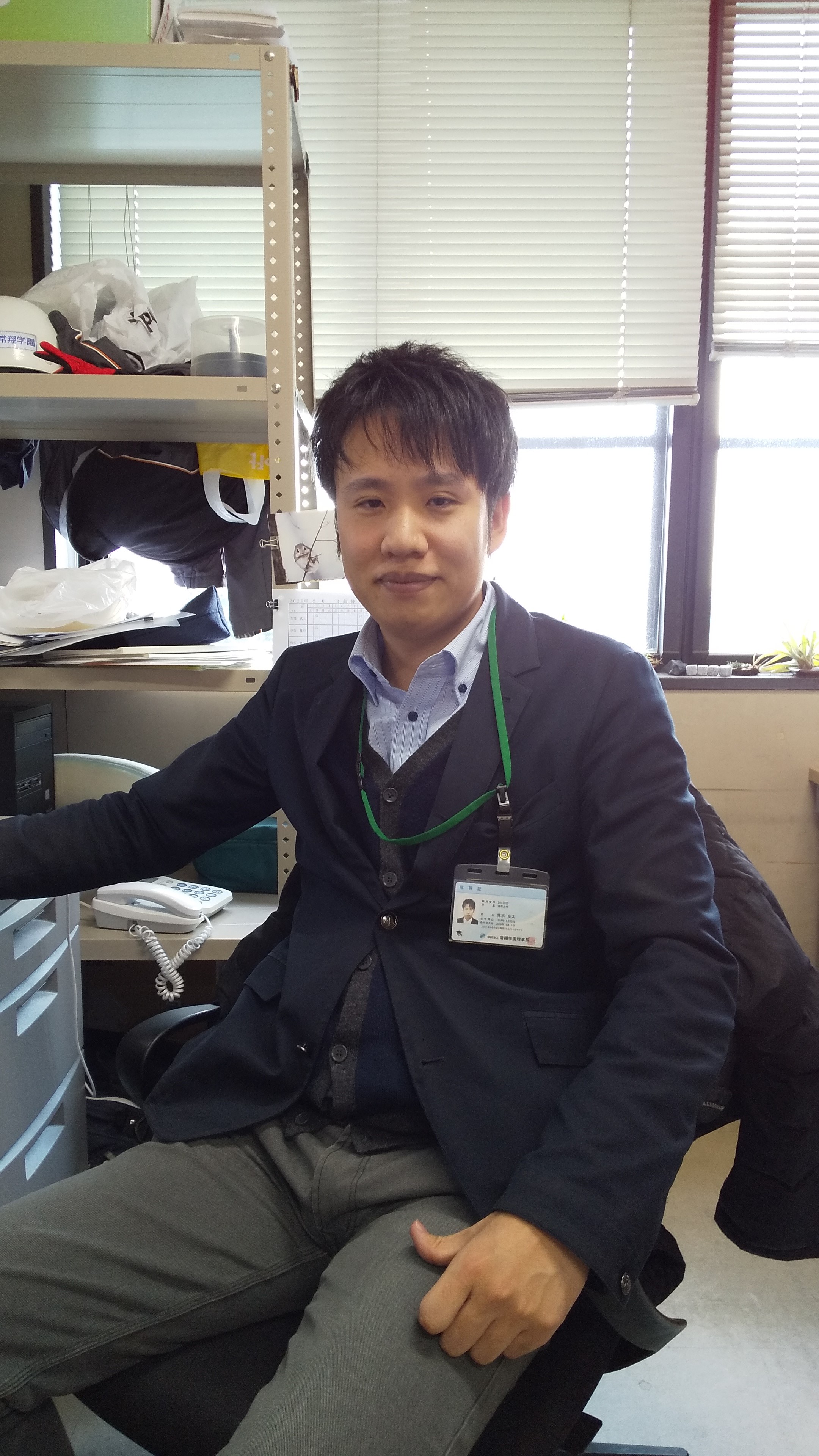その他
【薬学部】 ラボ☆なう No.22 荒木 良太 講師(複合薬物解析学研究室)
薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!
ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!
第22回目は、複合薬物解析学研究室の荒木 良太 講師です!荒木先生は薬学以外に、少年犯罪心理や都市開発、地球環境など幅広い分野にも興味をお持ちです。
それでは、第22回 ラボ☆なう スタートです(^^)
-複合薬物解析学研究室では、どのような研究をされていますか?
私自身の研究範囲は大変幅広いですが、主要な研究テーマの一つが漢方薬の作用機序の解明です。漢方薬は経験則で効果があると思われていますが、科学的根拠がないものが多いです。昨今の医療現場では、科学的根拠を求められるので、漢方の効果に関する科学的根拠を探究しています。
大学院生時代に薬局でバイトしていたのですが、精神疾患やうつ病、不安障害、発達障害に対し、漢方薬が処方されることがありました。大学・大学院では医薬品の薬理学を研究しており、漢方については全く専門外だったのですが、なぜ漢方薬に精神疾患などへの効果があるのか気になっていました。私の場合、研究のスタートは、日常でのギモンによるものがほとんどです。小学生でも感じるような、単純なところに研究のヒントは転がっています。
-学生時代の苦労話を教えてください!
高校での成績はそこそこ良い方でした。高校は進学校だったので、授業=受験勉強という感じでしたが、受験勉強でも困ることはありませんでした。
高校での感覚のまま大学に入学したので、大学入学当初は大学での学びに戸惑いました。大学では主体的な学びが求められます。疑問点があっても、すぐに先生が教えてくれることはなく、自分で図書館などに行って調べる必要があります。最初は慣れませんでしたが、主体的に学習を進めることによって、理解力が増し、追再試験を一度も受験することなく、4年制薬学部を卒業しました。
-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?
研究室でたくさんのことを学びました。研究の進め方や実験方法、論文の書き方など、直接研究に関わる内容はもちろんのこと、プレゼンテーションの技法や外部団体への研究助成金の申請書の書き方など、研究者になるという夢、将来を見越した学びを経験できました。当時の研究室では、2週間に一回、研究報告書を教員に提出する必要があり、非常に大変でしたが、文章力を鍛えてもらいました。
私自身、学生時の専門分野は漢方ではなく、薬理系の基礎研究でした。現在こそ、漢方を専門にしていますが、ベースは薬理系の基礎研究です。そのような漢方研究者はそう多くありません。元々、さまざまなことに興味があるタイプで、少年犯罪心理や都市開発、地球環境などにも興味があります。余談ですが、野球観戦が趣味で、ピッチャーの持つ変化球やメンタル面を考え、キャッチャーの配球を推測することが大好きです。分野を問わず、考えることが好きなのかもしれません。分野に縛られず興味を持つところが私の強みだと考えています。
-薬学部の面白さを教えてください!
薬学は基礎科学だと考えています。理論に基づき、生体の科学、ライフサイエンスを学ぶ学問です。薬学研究を行う上で重要なことは、科学的根拠を追究することで、結果として医師や患者のために貢献します。科学的根拠を自分で明らかにできる点が非常に面白いです。
-高校生に向けて一言!
ライフサイエンスをするなら薬学部へ!
いろんなものに疑問を持ち、知りたいという探究心を大切にしてください!