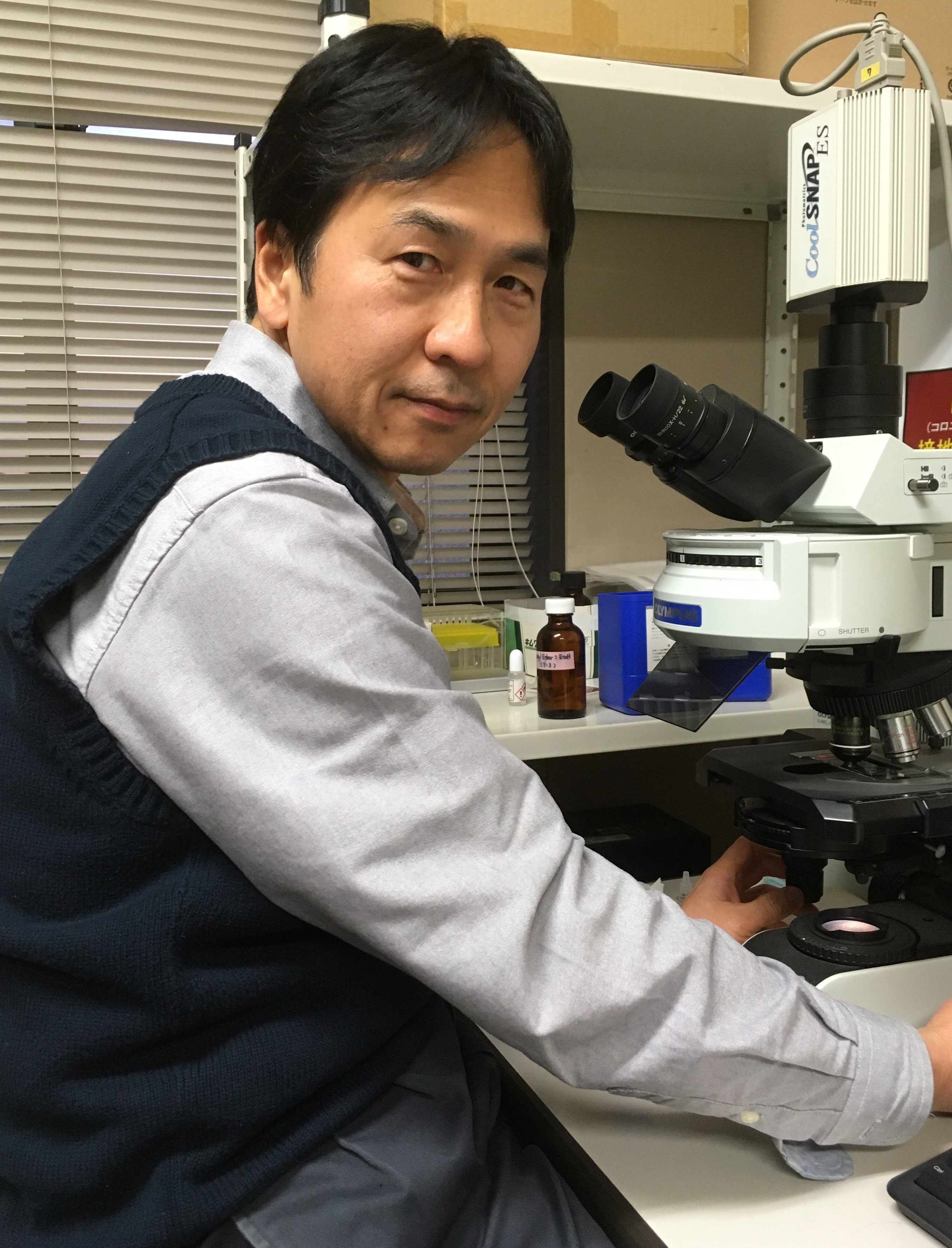その他
【薬学部】 ラボ☆なう No.7 高松 宏治 教授(生物系薬学分野 微生物学研究室)
薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!
ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!
第7回目は、微生物学研究室の高松 宏治 教授です!高松先生は、微生物学研究室で研究されるとともに、薬学部附属薬用植物園の管理責任者も務めています。
それでは、第7回 ラボ☆なう スタートです(^^)
-微生物学研究室では、どのような研究をされていますか?
細菌の【芽胞】を研究しています。芽胞は納豆菌や炭疽菌などの細菌が厳しい条件下で生き残るために形成する特殊な細胞です。ほとんどの方にとって馴染みのない存在と思いますが、気付かないところで日々の暮らしと関わっています。
私の研究分野は、薬学部の衛生系と呼ばれるカテゴリーに含まれており、【人の健康と環境】をテーマに研究・教育活動を展開しています。芽胞研究はマイナー分野なので、薬学部における位置付けが十分に理解されていないかも知れませんが、食品衛生や品質管理、感染症や食中毒の防止など薬剤師の業務とも関わっており、長い研究の歴史があります。
私が研究に用いている主な芽胞形成細菌は枯草菌(こそうきん)です。枯草菌は納豆などの食品や健康に役立つプロバイオティクスの生産、有用物質の工業生産、研究などに利用され、私達の生活に役立っています。一方で、食品や飲料などを腐らせる危害細菌として知られています。私は芽胞が厳しい条件下で生き残る能力に興味を持ち、本研究室の桑名講師と一緒に研究を進めています。桑名講師は、世界的に有名なフランスのパスツール研究所と共同研究を行っており、研究熱心な女性教員です。
-学生時代の苦労話を教えてください!
私は広島県廿日市市出身で、高校までずっと広島県で生活していました。その後、茨城県の筑波大学に進学しましたが、入学当初は習慣や言葉の違いからカルチャーショックを受けました。大学受験の時、ホテルからタクシーで移動したのですが、運転手さんが何を言っているのか全くわかりませんでした(笑)。今でも耳に残る懐かしい響きです。
大学では生物学を専攻し、留学生も含めて出身地の異なる学友とともに勉学に励みました。言葉(方言)や習慣の違いなどを克服する努力を通じて、多様性に対する理解が深まったと思います。学部3年生までは楽しい思い出が多く、研究に携わるようになった4年生からは辛い思い出も沢山あります。実家が兼業農家で小学生の頃から植物栽培に興味があり、大学入学前は「植物の力を利用して人の健康維持や医療などに貢献したい」と考えていました。その影響なのか、医療に直接関わる分野をほとんど学習していなかったにもかかわらず、今こうして薬学部の教員として研究・教育を続けていることに驚いています。
-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?
学部4年生から、一貫して枯草菌の研究を行っています。大学院5年間(修士2年間+博士3年間)を含めて、約30年間研究を続けていることになります。出身大学の先生方は教養深く、専門分野はもちろんのこと、他の学問や、芸術・文化など幅広い知識をお持ちでした。教育熱心で、自らの知識と経験を惜しみもなく伝授して頂きましたので、今でも恩師のような教員になることを目標にしています。母校のキャンパスは「陸の孤島」と呼ばれており、都会の空気に汚されることなく、豊かな自然の中で生物学を「体験学習」できました。人や環境に恵まれた学部時代だったと思います。
-薬学部の面白さを教えてください!
薬学部には多彩な学問が集まっています。物理、化学、生物、医療などの様々な分野の専門家と巡り合えることが薬学部の魅力と思います。
-高校生に向けて一言!
現代は情報が溢れており、情報に振り回される難しい社会ですが、私の学生時代と比べると学びを続けるために必要な環境が十分整っています。自分の可能性を拡げるために、情報の使い道を適切に学びつつ、実体験を大切にしてほしいと思います。扉を開けて一歩踏み出しましょう。自信を持って下さい。あなたたちは素晴らしい才能を持っています。