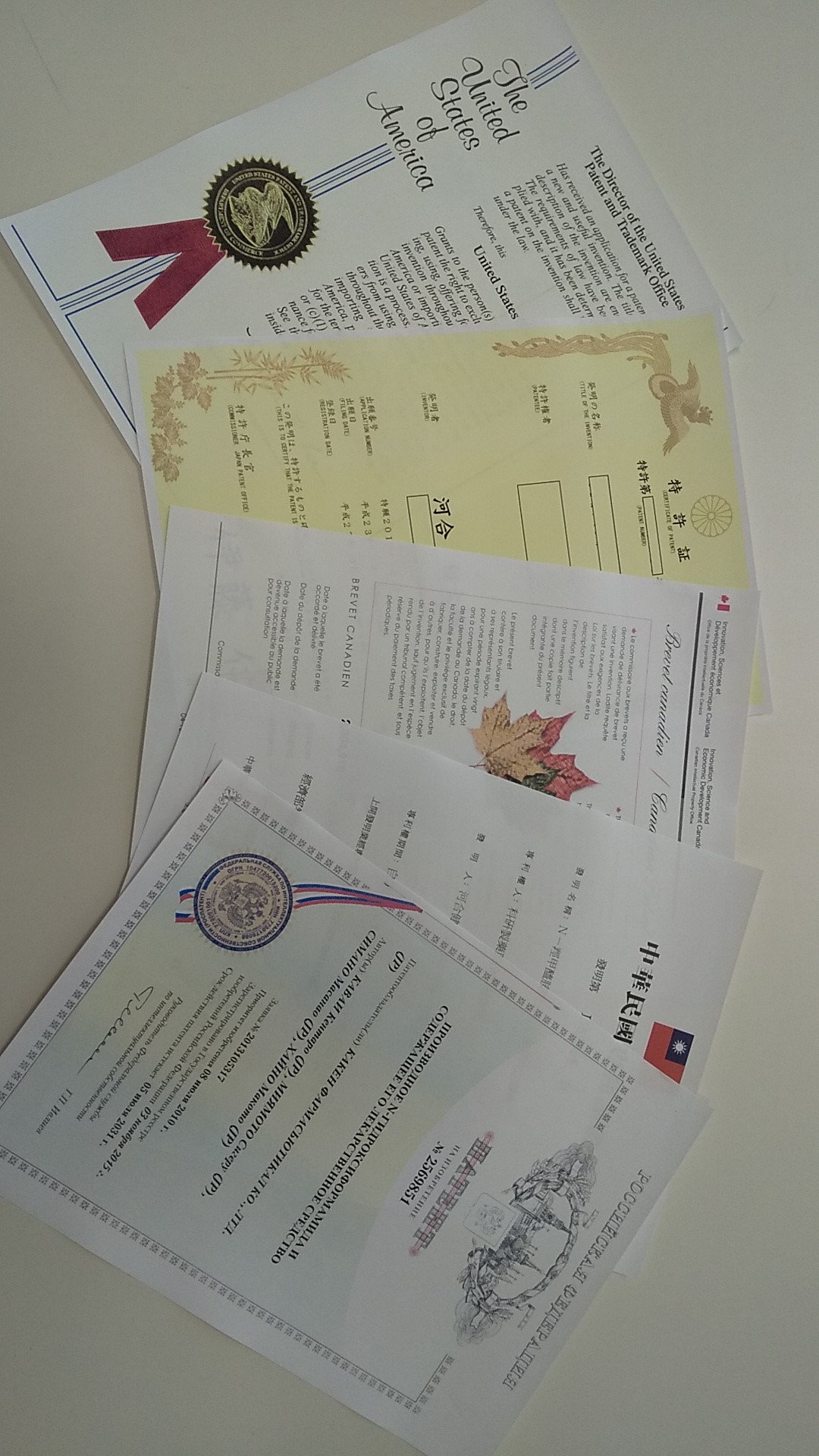その他
【薬学部】 ラボ☆なう No.19 河合 健太郎 准教授(化学系薬学分野 医薬品化学研究室)
薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!
ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!
第19回目は、医薬品化学研究室の河合 健太郎 准教授です!河合先生は長年製薬メーカーで新薬の開発に携わり、2018年4月、本学に着任されました。
それでは、第19回 ラボ☆なう スタートです(^^)
-医薬品化学研究室では、どのような研究をされていますか?
医薬品化学研究室では、薬のタネになる化合物について、日々研究しています。化合物の力で、多くの困難な疾患に立ち向かうことができます。
私は理学部出身で、大学院では食中毒の原因となっている天然物を合成しました。天然からは化合物が微量しか得られず、食中毒のメカニズムを解明するためには、大量の化合物が必要だったからです。天然物の合成と薬の合成は全く異なるように思われますが、複雑な化合物を合成するという点では、良く似ています。そこで、製薬メーカーであれば、大学・大学院で学んだことを活かすことができると思い、メーカーの研究職に就きました。
製薬メーカー時代に比べ、大学ではチャレンジングな研究を行っています。というのも企業での研究は営利を追求する傾向がありますが、大学での研究は基礎研究がメインであり、奇抜なアイデアであっても、研究を行える環境にあります。学生とともに研究を行うのは初めてですが、明るい学生とともに楽しく研究を進めています。
-学生時代の苦労話を教えてください!
やはり研究活動には苦労しました。学部4年生の頃、研究室では毎日、朝早くから深夜まで研究を行いましたが、成果が出ないこともしばしばありました。心が折れ、研究には向いていないのかと落ち込んだこともありましたが、元々諦めるのが嫌いな性格のため、【研究の仮説が成り立つのか、成り立たないのかを解明してやろう】と躍起になり、最後までやり遂げました。この経験から、実験が上手く行かない理由を考え、次に生かすことの大切さを学びました。
その後、研究が1年間だけでは物足りなくなり、修士課程に進学し、テーマとなる化合物を変えたことで、順調に成果が出るようになりました。自分の名前が入った学術論文が出版されたときは、努力が報われたと心から感じました。
-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?
先ほどお話ししたように、私は薬学部出身ではありません。しかし、現在の研究の中には、製薬メーカー時代にやり残したものを発展させているものもあり、これらは理学部時代の学びがそのまま活かされています。
また、大学時代、一風変わったアルバイトをしていました。主に文系の大学教員が所属する学会のアルバイトで、マイクロフィルムを使って明治時代の新聞を一つ一つ調べ、関係する記事を収集して、教員に渡すというものです。こんな仕事もあるのかと思いながら、アルバイトしていましたが、現在、研究を進めるうえで、過去の研究者の先行研究を調べることがあり、アルバイトでの経験が役に立っています。
-薬学部の面白さを教えてください!
薬学部では、臨床を意識した教育を行っています。物理、化学、生物などのサイエンスをベースに、疾患や薬物療法に関する教育を行っています。実学的と言えるでしょう。
また、大学では「チーム学習」を取り入れており、学生同士が主体的に学びあう仕組みがあります。私の学生時代や製薬メーカー時代には耳にしたことがない言葉で、新鮮でした。
-高校生に向けて一言!
素朴な疑問を大切に!研究のタネは身近にあります。ぜひ一緒に研究しましょう!!