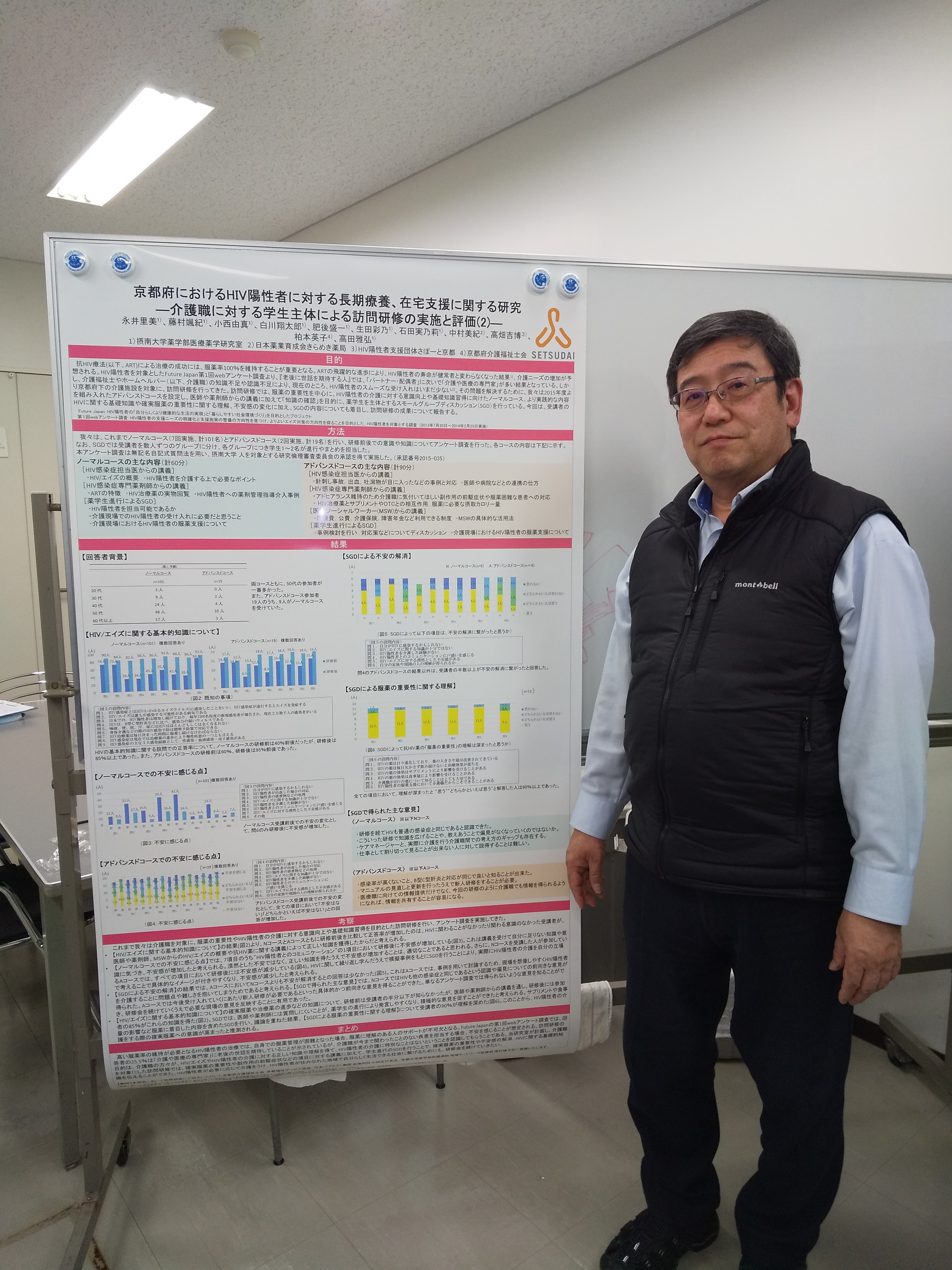その他
【薬学部】 ラボ☆なう No.21 高田 雅弘 教授(医療薬学研究室)
薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!
ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!
第21回目は、医療薬学研究室の高田 雅弘 教授です!高田先生は長らく国立病院で薬剤師として活躍され、臨床経験が豊富な先生です。。
それでは、第21回 ラボ☆なう スタートです(^^)
-医療薬学研究室では、どのような研究をされていますか?
私も含めて、医療薬学研究室の教員は、全員医療現場(病院、薬局)での臨床経験があります。このため、医療現場や在宅現場での課題に沿った研究を行っています。
最近では、「HIV/AIDS患者に対する長期療養・在宅療養支援」、「薬物依存」や「地域医療」に関する研究を進めています。
「HIV/AIDS患者に対する長期療養・在宅療養支援」では、患者団体や京都府、京都市、京都府介護福祉士会、HIV担当医師、HIV感染症専門薬剤師、メディカルソーシャルワーカーと連携し、介護職に対する訪問研修を行っています。HIV陽性者の治療には抗HIV薬を確実に服薬していただくことが不可欠です。このため、在宅ケアにおいて薬剤師の訪問指導に加え、介護職に服薬の確認などをしていただく必要があります。そこで、HIVに関する必要な知識を介護職の方々に理解していただくための研修を、研究室の学生主体で企画して実施しています。
「薬物依存」に関しては、報道されている覚せい剤などだけでなく、市販薬の乱用や依存も問題になってきています。また、依存症から社会復帰をめざす人たちへの支援のあり方も今後の課題といえます。このような依存症に対するゲートキーパーとして薬剤師は薬物乱用や依存へどのように対応することが求められるかを学生達と考えています。
「地域医療」では、交野市、河内長野市、和歌山県日高郡のとある地区において、健康相談や講演会などを通して住民の方々と交流し、薬剤師が地域でどのような活動を行うことが住民の方々の健康につながるかを研究しています。
-学生時代の苦労話を教えてください!
私は薬学部を1984年に卒業しました。苦労話ではないのですが、学生時代は「漢法医学研究部」に入っていました。”漢方”ではなく”漢法”です。あまりよく知られていないのですが、古来から「本来、方は処方のこと、法とはこの処方を一定の法則の下に運用する方法であるから、漢方医学ではなく漢法医学でなければならない」という考え方があって、その考えに共鳴したクラブ名でした。傷寒論という難解な古典(3世紀ごろに書かれた漢方薬の使い方を書いたバイブルみたいなもの)を読んで部員で議論したものです。
このときの経験は、後に病院薬剤師になったときに活かされたと思います。皆さんの中には、漢方薬って効果があるかないか、よくわからないものと思われる方がいると思います。でも少し考えてください。3世紀頃に考えられた古典医学がいまだに使い続けられているということは、それなりの効果があるということだと思いませんか。なぜ効果があるのかということを明確に説明できていないだけだと思います。私は、医師に漢方を勧めたときに「漢方は非科学的だから〜」と言われたら「非科学ではありません。未科学なだけです〜」とお話しするようにしていました。この未科学だった分野にも最近ではいろいろな研究が進んでいます。
-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?
大学1年生の時に、父を肝臓癌で亡くしました。これをきっかけに、病院薬剤師として医療に携わりたいと強く思うようになり、(当時はいまのように臨床に直接結びつく科目はなかったですが)勉学やクラブ活動の漢法に取り組みました。
家庭の事情で私は研究室に所属できず、研究室で研究する同級生をうらやましく眺めていました。その反動か、病院薬剤師として勤務した病院では、臨床研究部に出入りし、当時の主任研究官の恩師に研究の面白さや理論的な考え方を教えてもらいました。
結構なスパルタ教育で、最初の学会発表では、頭が真っ白になりながら英語で発表したのを覚えています。
-薬学部の面白さを教えてください!
医療において、薬物治療はなくてはならないものだということはご存知だと思います。では、薬剤師の仕事はなんですか?と聞かれたら皆さんはどのようなことを思い浮かべますか。この質問には「お薬を調合する仕事」「薬の説明を患者さんにする人」などの答えをよく聞きます。
では、医師の仕事はなんですか?と聞かれたら皆さんはどのようなことを思い浮かべますか。これには「患者さんの命を救う」「病気をなおす」などの答えをよく聞きます。
この違いを考えてみると、薬剤師の仕事で思いつくことは治療の「方法」であり、医師の仕事で思いつくことは治療の「目的」ではないでしょうか。薬剤師の仕事は、今までは「方法」に目が行きがちでした。しかしこれからは「患者さんの命を救う」「病気をなおす」という本来の「目的」を目指して薬剤師は薬物治療を通して医療の一端を担わなければならないと思います。
薬学部で学ぶ6年間は、いろいろな意味で充実した6年間になると思います。「患者さんの命を救う」「病気をなおす」ための学びを積み重ねていき、将来、臨床現場で患者さんから「ありがとう」の一言を言ってもらえることは、大変やりがいのあることだと思います。
-高校生に向けて一言!
薬剤師をめざす生徒さんに、薬剤師の仕事(使命)は皆さんが考えているより、もっと広く深いことを知って欲しいと思います。
そこで、元日本病院薬剤師会会長の全田浩先生(故人)がよく言っておられた言葉をおくります。
「薬あるところに薬剤師あり」