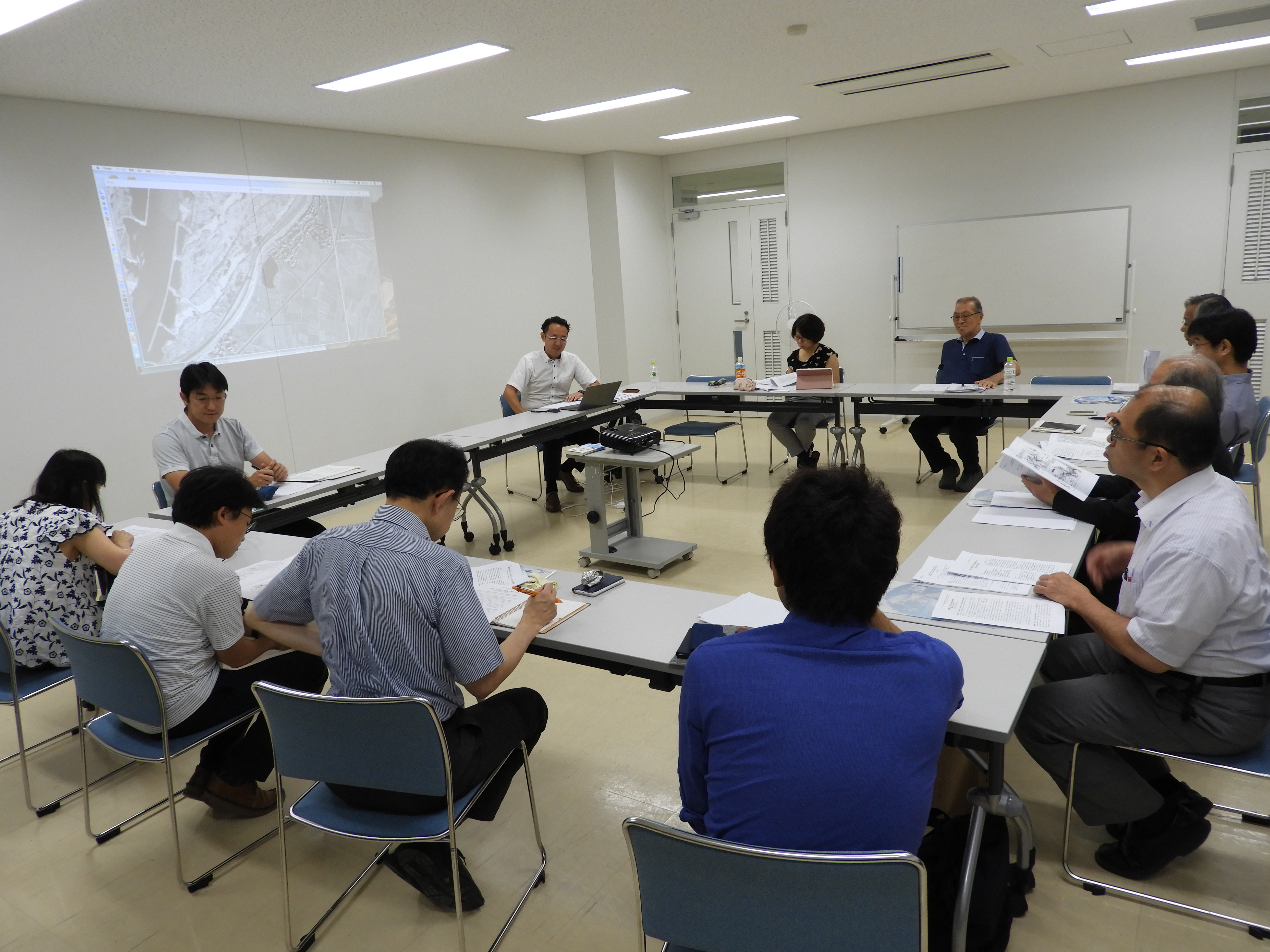経済学部
Smart and Human「淀川水系に関する総合的研究」研究会を開催しました
7月27日、S&H研究助成『淀川水系に関する総合的研究』プロジェクトは、愛知大学准教授・飯塚隆藤氏をお招きして、「淀川流域における近代河川舟運の地域的変化―歴史GISの手法を用いて」をテーマに、研究会を開催しました。
飯塚氏は、淀川流域、木曽三川流域、利根川流域の比較も行っており、この3流域で最も長く舟運が使われたのは、淀川水系だということです。また、明治期の水運に関する先行研究や、陸軍参謀本部によって編纂された『徴発物件一覧表』等を使い、それらの情報をGISで地図上に落とし込むことにより、淀川水系のどこが船舶の定繋地として使われていたのかを明らかにしておられます。
通説では、明治期以降、陸運の発展により舟運は衰退したとされるが、淀川水系では、昭和10年代まで、琵琶湖周辺及び、大阪市には、約1万隻の船舶が存在したと飯塚氏は指摘されました。寝屋川等の中流域では、舟運は、危険物等の運搬に使われ、大阪市では陸路や海運との連携もみられるとのことでした。
GISを用いて、水系の舟運を視覚的にも明らかにする試みは、興味深く、本研究プロジェクトにも様々な示唆を与えてくれるものでした。