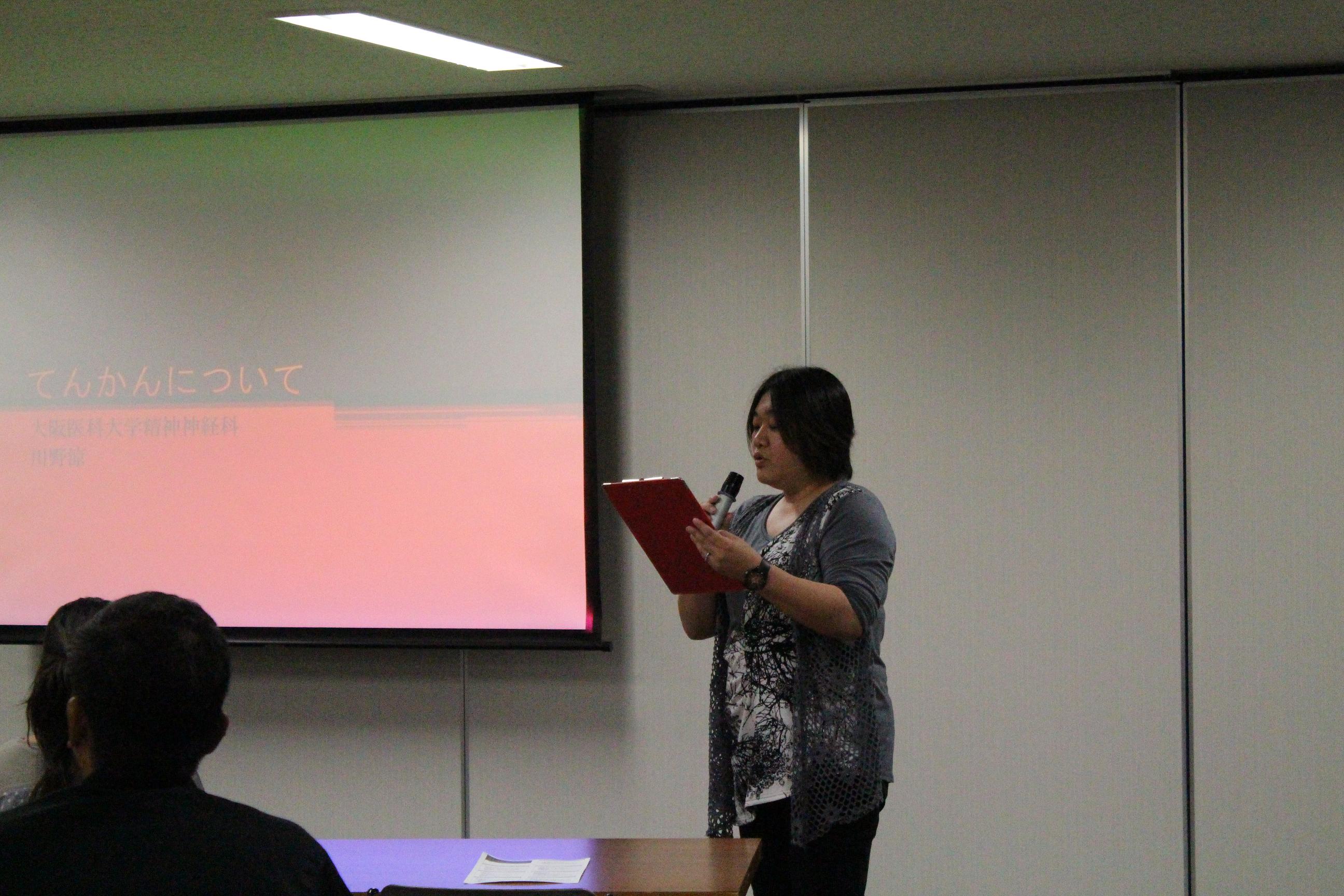その他
「てんかん」研修会を開催しました
10月23日(水)、寝屋川キャンパスにおいて、「てんかん」に関する研修会を開催しました。
この研修会は、脳の電気活動の一時的な乱れによって発作が起こる「てんかん」について正しい知識と理解を深めるために保健室が開催し、本学教職員約30人が参加しました。
まず本学保健室の看護師から開会の挨拶があり、本研修会の講師である大阪医科大学附属病院精神神経科川野涼医師に講演いただきました。
『てんかん』の種類は、大きく分けて、全般発作(全身けいれんなど)、単純部分発作(意識・言語障害など)、複雑発作(精神運動発作:意味のない行動をするなど)がある。治療方法は薬物療法が主体であり、けいれんなどの発作を抑制するためには、医師の指示に従って内服加療を継続することが大切である。
けいれんを起こした人への対応は、まず危険がない安全な場所に寝かせ、慌てず発作の様子や呼吸状態・打撲などの外傷の有無を観察し、どれくらいの時間発作が続いたかを確認することが大切。また、けいれん後にもうろう状態となり、歩きまわるなどの行動がみられる時は、無理に行動を止めようとせず後ろから付き添って危険を回避する。けいれんの最中に口の中に指やタオルなどを入れたり、けいれんを抑えようとしてはいけない。『てんかん』の確定診断があり、主治医からの特別な指示のない場合は、救急車を呼ぶ必要はないが、10分以上発作が続く場合や呼吸困難がみられる、頭部を打撲している場合などは救急車を呼ぶことが必要である。
『てんかん』は内服忘れや睡眠不足、疲労により、発作が起こりやすいことなど非常に分かりやすく説明されました。
参加者からは『てんかん』という病気には、色々なタイプがあることを知った。病気について正確に理解し、何かあれば対応できるように援助する体制が必要であることを改めて感じた」と感想を述べていました。