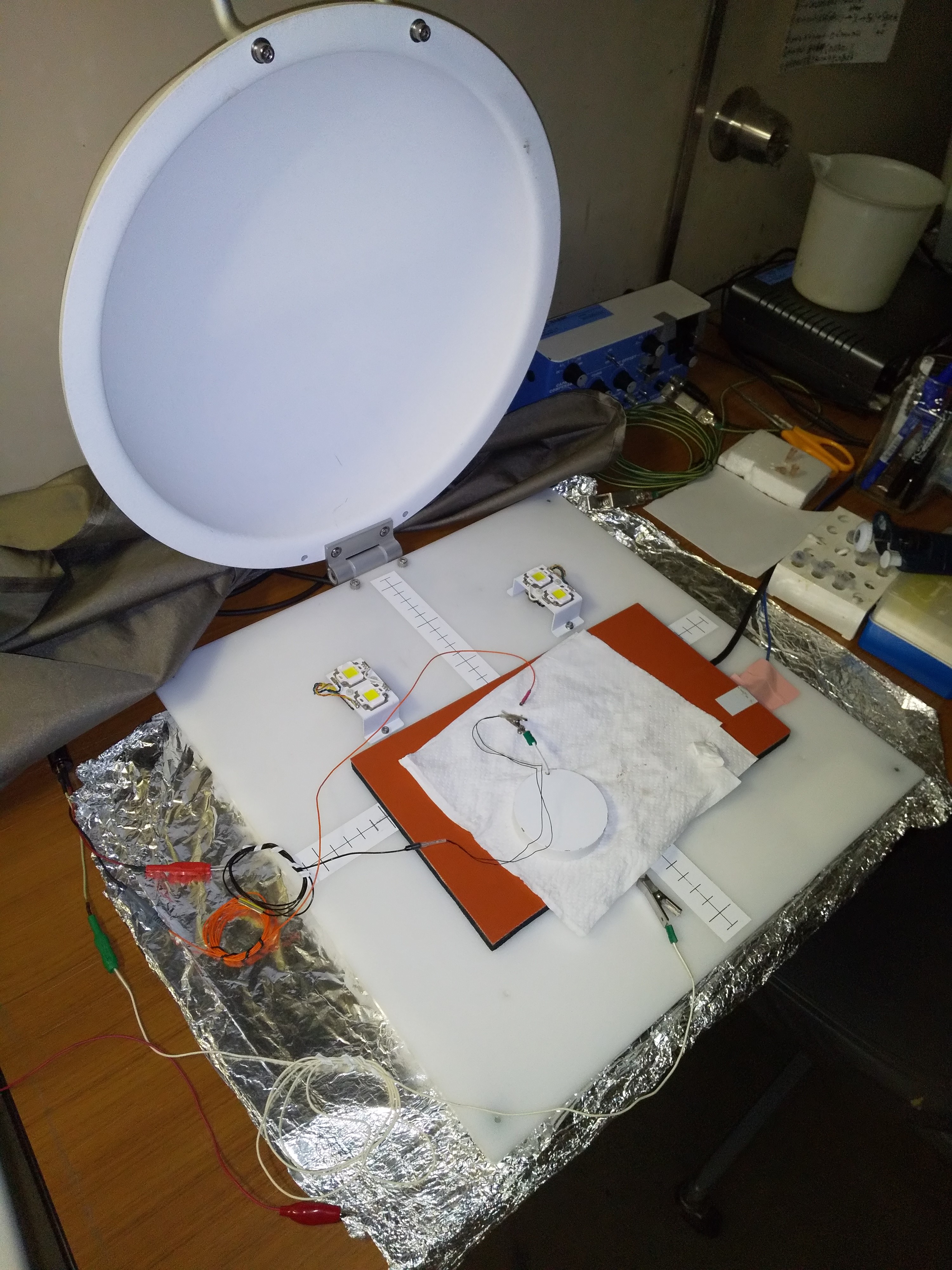その他
【薬学部】 ラボ☆なう No.13 石丸 侑希 助教(薬物治療学研究室)
薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!
ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!
第13回目は、薬物治療学研究室の石丸 侑希 助教です!石丸先生は本学OBで、学部生時代から縁あって同研究室で研究されてきました。
それでは、第13回 ラボ☆なう スタートです(^^)
-薬物治療学研究室では、どのような研究をされていますか?
私たちの研究室では、神経変性疾患の治療法について研究しています。例えば、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や緑内障、糖尿病性網膜症など治療が難しい疾患に対する治療法の探索を行っています。これらの疾患は未だ根本的な解決策を見出せていないため、新たな治療薬の開発が望まれています。
私は大学院生時代から10年来、【アペリン】というタンパク質の研究を行っています。このタンパク質は20年ほど前に発見されたもので、その働きを明らかにする研究が世界中で行われており、様々な病気に関わることがわかってきました。私はノックアウトマウスと呼ばれる「体からアペリンを無くしたマウス」を用いた研究から、アペリンが視機能の維持に重要な働きをすることを発見し、失明を阻止できる治療薬としての可能性を発見しました。研究とは計画通りには進まないものですが、その都度考えながら、治療法の開発という目標に向かって頑張っています。
-学生時代の苦労話を教えてください!
大学に入った当初は、バスケットボール部での活動、焼肉屋でのアルバイト、学業の全てを両立するのに苦労しました。負けず嫌いな性格で、1年生の時に単位を落としたときには、今後、【全科目で好成績を収める】ことを目標に、勉学に励みましたが、部活もバイトも諦めることはしませんでした。試験科目数が多いときにもこの目標が達成できたときには、大変自信がつきました。
-学生時代の実習の思い出はありますか?
私は、摂南大学のOBで、衛生薬学科(※)に所属していました。衛生薬学科では、病院+衛生施設、または病院+薬局+衛生施設での実習を選択できました。私は様々な現場について学びたかったため、3実習経験できるコースを選択しました。衛生施設での実習では、大阪市柴島にある浄水施設にて淀川の水を効率的に浄化するための検討を行いました。様々なことに興味を持つことで貴重な経験ができたことから、こういった思いを今でも大切にしています。
(※)当時の薬学部は、薬学科と衛生薬学科に分かれていました。
-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?
大学院時代の恩師の先生から「論文を書くことの大切さ」について学びました。研究成果を論文で発表することによって、世界中の研究者とその知見を共有することができます。誰かが私の論文を読み、新たな成果を生み出してくれるかもしれませんし、また、そうした他者の成果は、自分の新たな成果に繋がるかもしれません。このような共同作業によって研究は進んでいき、医療の発展に繋がります。英語で論文を書くのは大変ですが、自分の研究成果を世界に発信するのは楽しい作業です。私も学生を指導する際にこの大切さを伝えています。
学部時代に学んだことが、現在大学教員として学生を指導する立場になり、大変役立っています。指導を行う上で学生と信頼関係を構築することが大変重要で、そのために学生の立場を考えて指導を行うことを常に心掛けています。
-薬学部の面白さを教えてください!
薬について学べることはもちろんのこと、普段何気なく食事から摂取しているビタミンやミネラルなどの栄養素の働きについても学ぶことができます。それらの作用をターゲットとした薬もあります。学習を進めることで、科学的な視点から食生活を見直し体調管理を行うことが可能になりますし、病気になった際に重点的に摂取すべき栄養素などがわかるようになります。また一方で、身体に悪影響を及ぼす毒物や放射線等についても知ることができます。薬につながる幅広い知識を得られるところが面白いですね。
-高校生に向けて一言!
一緒に薬学研究にのめり込みましょう!