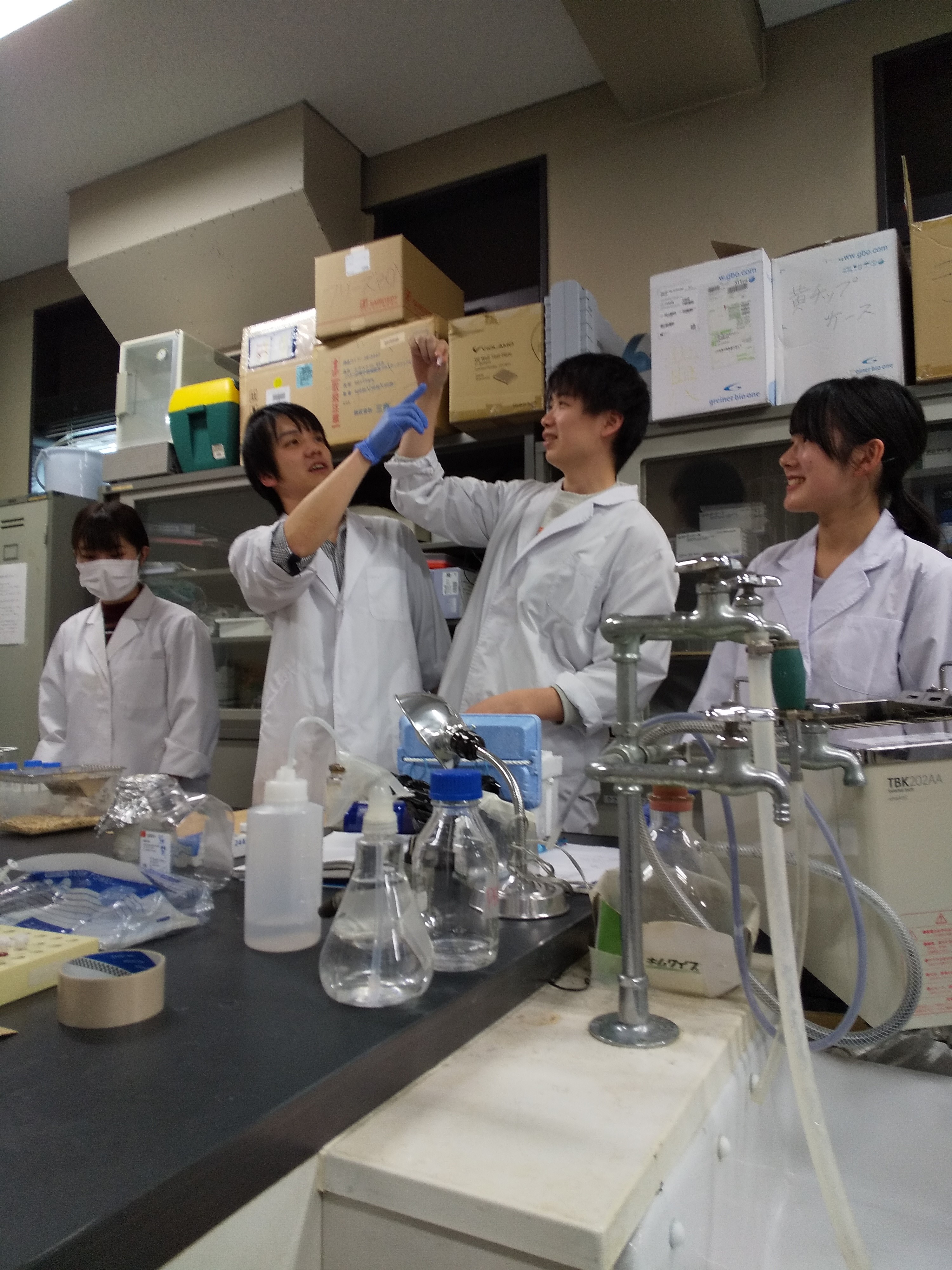その他
【薬学部】 ラボ☆なう No.15 伴野 拓巳 助教(薬物送達学研究室)
薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!
ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!
第15回目は、薬物送達学研究室の伴野 拓巳 助教です!伴野先生は薬剤師資格のほかに、臨床検査技師の資格もお持ちで、現在の研究にも役立っているそうです。
それでは、第15回 ラボ☆なう スタートです(^^)
-薬物送達学研究室では、どのような研究をされていますか?
ペプチド医薬品や抗体医薬品といったバイオ医薬品の研究をしています。バイオ医薬品は副作用が少なく、治療効果が高いことで、昨今注目されている医薬品です。しかし、バイオ医薬品は注射でしか投与できないものが多く使用に際して患者さんが痛みを伴うこと、また病院でしか投与できないことなどの問題があります。そこで、私たちは飲み薬や鼻に噴霧するなど、痛みがなく患者さん自身でバイオ医薬品を使用・服用するための技術開発を行っています。
私たち薬物送達学研究室では、研究室の主宰者である佐久間信至教授が開発に関与した吸収促進剤を用いて、通常では身体に吸収されにくい薬などを吸収されやすくする研究を主に行っています。これまでの研究で、その吸収促進剤を使うことで通常はほとんど吸収されないバイオ医薬品の吸収効率が上昇することがわかりました。この技術を用いて、製薬メーカーとも共同研究を行い、医療の発展に貢献したいと考えています。
-学生時代の苦労話を教えてください!
大学入学当初は、授業が薬に関するものより物理や化学といった基礎的な科目が多く、なかなかモチベーションが上がりませんでした。薬学部に入学したということで、薬に関する専門的な勉強がすぐできると思っていたのでしょうね。しかし、2年生での物理薬剤学の授業のテストで高得点を取ってから、人生が変わりました。授業担当の先生に気に入ってもらえて、2年生ながらその先生の研究室に入り浸るようになりました。研究室を選択するときも、その研究室を希望し、研究者への道を目指すようになりました。研究室では身体の中で薬を運ぶ働きをしている薬物トランスポーターの研究をしていたのですが、できることが増えていくにつれて、自分にも自信がつき、もっと自分の手で突き止めたいという思いが湧いてきました。研究にのめり込むにつれて、入学当初に受けた授業との関連がわかるようになり、授業の意味が分かるようになりました。元々、人前に立つのが苦手だったのですが、研究の場面では研究室のセミナーや学会発表など周りの人に研究内容を発表する必要があります。日々の実験だけでなく、そういった機会にも数多く挑戦し、自分のキャパシティを大きくしたことにより、成長できたと思います。
-学生時代の実習の思い出はありますか?
病院実習は大学病院が実習先でした。6大学の学生が一緒に実習を受けましたので、他大学の学生からたくさん刺激を受けました。大学では追再試験を受けたこともなく、成績は悪くなかったのですが、他大学の学生と関わることで、自分たちに不足している点を再確認できました。一緒に実習を受けた仲間とは、実習が終わってからも交流が続いています。
-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?
薬剤師のほかに臨床検査技師の資格も持っています。私が通っていた大学では、臨床検査技師コースの単位を履修すれば、受験資格を得られたため、取れるものは取っておこうとコース科目を履修しました。薬学部では学びきれない知識を得ることができましたし、病気について臨床検査技師の視点から深く学ぶことができました。
幅広く知識を得ることができましたし、他者にはない私の強みとなっています。臨床検査技師の資格を持っているので、心電図を取ることや、医師の指示により人の採血もできるんですよ。
-薬学部の面白さを教えてください!
薬学部には幅広い分野があります。興味を持っていけば、自分の研究室以外の研究者とも接触可能です。いろんな方向で解決策を検討することができます。私自身、他の研究室の教員と意見交換は頻繁に行っていますし、自分が持っているデータが別の研究室ではどのように使えるかなど、日々模索しながら、研究を進めています。
-高校生に向けて一言!
できるだけ、自分がやったことのない嫌いなことに挑戦し、自分の可能性を見つけてほしいです。
もしかしたら、それが自分の得意分野かもしれません。