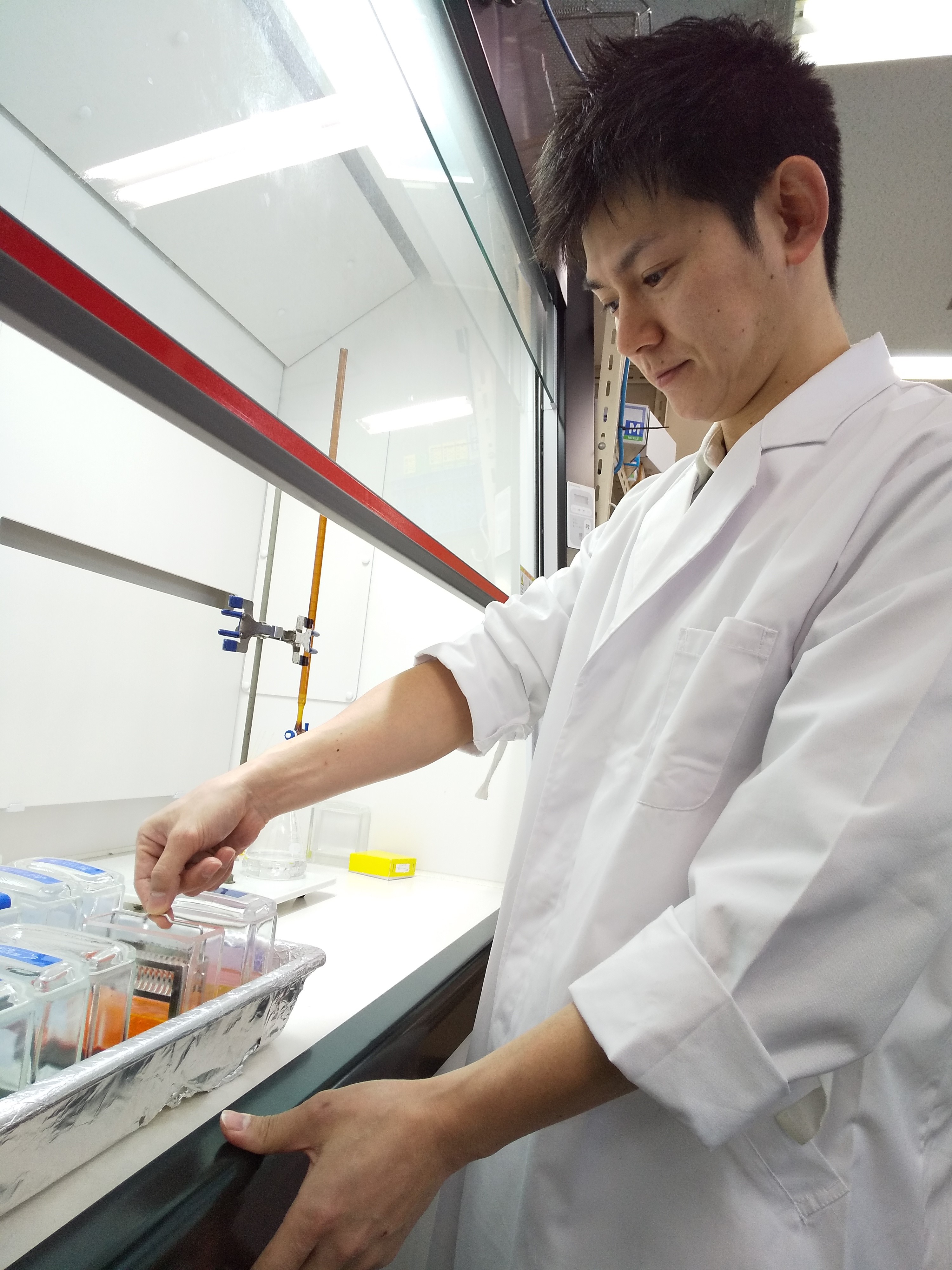その他
【薬学部】 ラボ☆なう No.17 荻野 泰史 助教(公衆衛生学研究室)
薬学部、新コンテンツ「ラボ☆なう」です!!
ラボ☆なう では、高校生の皆さんに、各研究室・分野の研究内容や、学生時代の苦労話、実習の思い出などを紹介します!!
第17回目は、公衆衛生学研究室の荻野 泰史 助教です!荻野先生は本学OBで、看護師をされているお姉さんの影響で薬学部に進学されました。
それでは、第17回 ラボ☆なう スタートです(^^)
-公衆衛生学研究室では、どのような研究をされていますか?
公衆衛生学研究室では病気の予防に関する研究を行っています。予防と言うと『病気にならないようにする』というイメージが強いと思うのですが、それだけでなく、早期に発見して治療を開始したり、生活習慣の改善などによって病気が進行、悪化しないようにすることも予防の一つです。私たちは糖尿病などの生活習慣病や加齢によって生じる認知症、アレルギー疾患について、予防に貢献することを目標にしています。
生体内で生成する活性酸素は、通常防御機構によって適切に調節されているのですが、この酸化・還元のバランスが何らかの原因によって崩れ、酸化反応が進んでいる状態を酸化ストレスと言います。酸化反応が過剰に進むと、様々な疾患の発症・進行に関与することが知られており、酸化ストレスを軽減させることによって病気が予防できるかどうかや、そのメカニズムを明らかにするために研究をしています。
-学生時代の苦労話を教えてください!
高校では、英語や第二外国語に力を入れた国際教養科に所属していました。語学教育や国際理解教育が充実している分、数学や理科などの授業が少なく、そこから薬学部に進むのは少し苦労しました。高校では文系でしたが、姉が病院で看護師をしており、院内で薬剤師は薬について頼りになるという話を聞き、薬剤師職に魅力を感じ、薬学部を志望するようになりました。ただ、高校では、面白そう!と言う理由だけで化学と物理を選択したため、生物の知識がなく、大学入学後の生理解剖学の授業はちんぷんかんぷんでした。受容体について習ったときは、本当に呪文のようでどうやって覚えられるのかと絶望したことはいまだに忘れられません。その分、理解できたときは人体の仕組みの素晴らしさに感動し、生物学、薬理学が面白いと思うようになりました。
-学生時代の実習の思い出はありますか?
私が実習させていただいた病院では、薬剤師がいかに医療現場に介入していくかを強く意識されていて、当時、私の抱いていた薬剤師のイメージの遥か先を行く経験をさせていただきました。また、薬剤師としては直接的な関わりが薄い、検査科やリハビリ科、放射線科でのガンマナイフ治療や、外科手術の見学もさせていただきました。たった20日間の実習期間だったのですが、薬剤師としてだけでなく医療に関わる人として、必要な考え方を学ぶ機会になりました。
-学部時代の学びが、どのように活かされていますか?
中学生や高校生に『数学が何の役に立つのか』と言う人がいますが、同様に、薬学部では『化学や物理がなぜ薬剤師に必要なのか』とよく耳にします。しかし、実際にはかなり重要で、薬の化学構造や物理的性質が薬効にも影響しますし、研究においても、そういった基礎的な化学や物理の知識が不可欠です。その他にも薬物動態学や分析学など、現在の自分の専門外の分野でも基礎的な理解があることで研究の役に立っていると感じることはよくあります。そう考えると学部時代の学びが自分の研究の根底を支えていると実感します。
-薬学部の面白さを教えてください!
薬学は生物だけでなく化学や物理学など分野が多岐に渡る学問です。例えば、薬がどのように効くのかを考えるときに、薬物自体のメカニズムだけでなく、薬の物理的・化学的な性質や服用する人の健康状態や遺伝的背景など非常に多くのことが影響します。そのため、幅広い知識と多角的な視点で考えることが必要になります。一方で、ある分野に特化した専門性も重要です。広く学んだうえで、専門性を高めていけるところがサイエンスとして、薬学部としての魅力だと感じています。
-高校生に向けて一言!
学ぶことの原動力は好奇心だと思います。なぜ?どうして?と思う気持ちを大切にしてください。