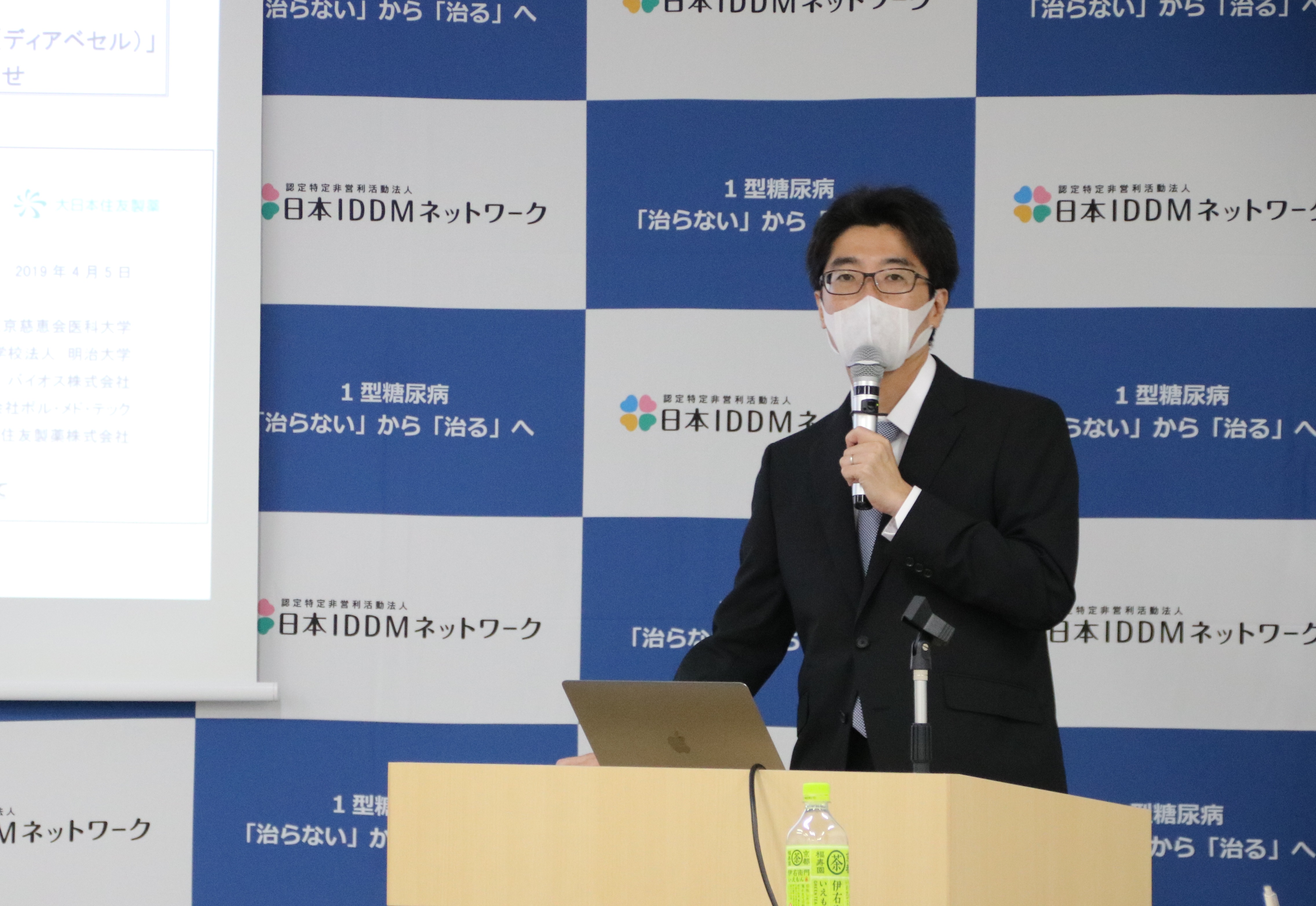その他
7月29日、摂南大学×日本IDDMネットワークが研究助成金の贈呈式を行いました
農学部 応用生物科学科の井上亮教授が進める1型糖尿病に関する研究が、患者と家族らでつくる認定NPO法人「日本IDDMネットワーク」から600万円の研究助成金を受け7月29日、枚方キャンパスで贈呈式を行いました。
1型糖尿病は、体内でインスリンを作ることができなくなる原因不明の自己免疫疾患です。小児期を中心に発症し、1日5回程度インスリン注射などを続ける必要があります。
1型糖尿病の治療法には、膵臓や膵島の移植がありますが、ドナー不足が深刻な課題となっています。その解決策として、同団体が助成し、井上教授や明治大、福岡大などの研究機関が連携して進めているのが、医療用ブタの膵島細胞をカプセルに入れて移植する「バイオ人工膵島移植プロジェクト」です。このバイオ人工膵島移植は、現在1型糖尿病の根治に最も近いとされており、ドナー不足の解消も期待されます。
井上教授は異種間移植で必須課題となる安全性を確保するための「感染症検査体制構築」に取り組んでいます。膵島細胞の病原体感染の有無はPCR検査や、メタゲノム解析などといった方法で検出。既に、厚生労働省の指針に記載されているウィルスの 7 割以上をカバーするPCR法を確立し、実用化に向けた調整を行っています。また、次世代シーケンサーを使った網羅的な病原体検出方法についても基盤は構築済みです。
荻田喜代一学長は、「非常に心のこもった研究助成金に感謝するとともに、本研究に大いに期待している」と話し、日本IDDMネットワークの井上龍夫理事長は「医療は安全性を担保することが重要」と感染症の検査体制構築への期待を語りました。
井上教授は「今後は実用化に向けて検査の感度を上げ、検査回数を最小にするなどの改善を行い、検査時間の短縮と感度向上を図っていきます」と意気込みを述べました。