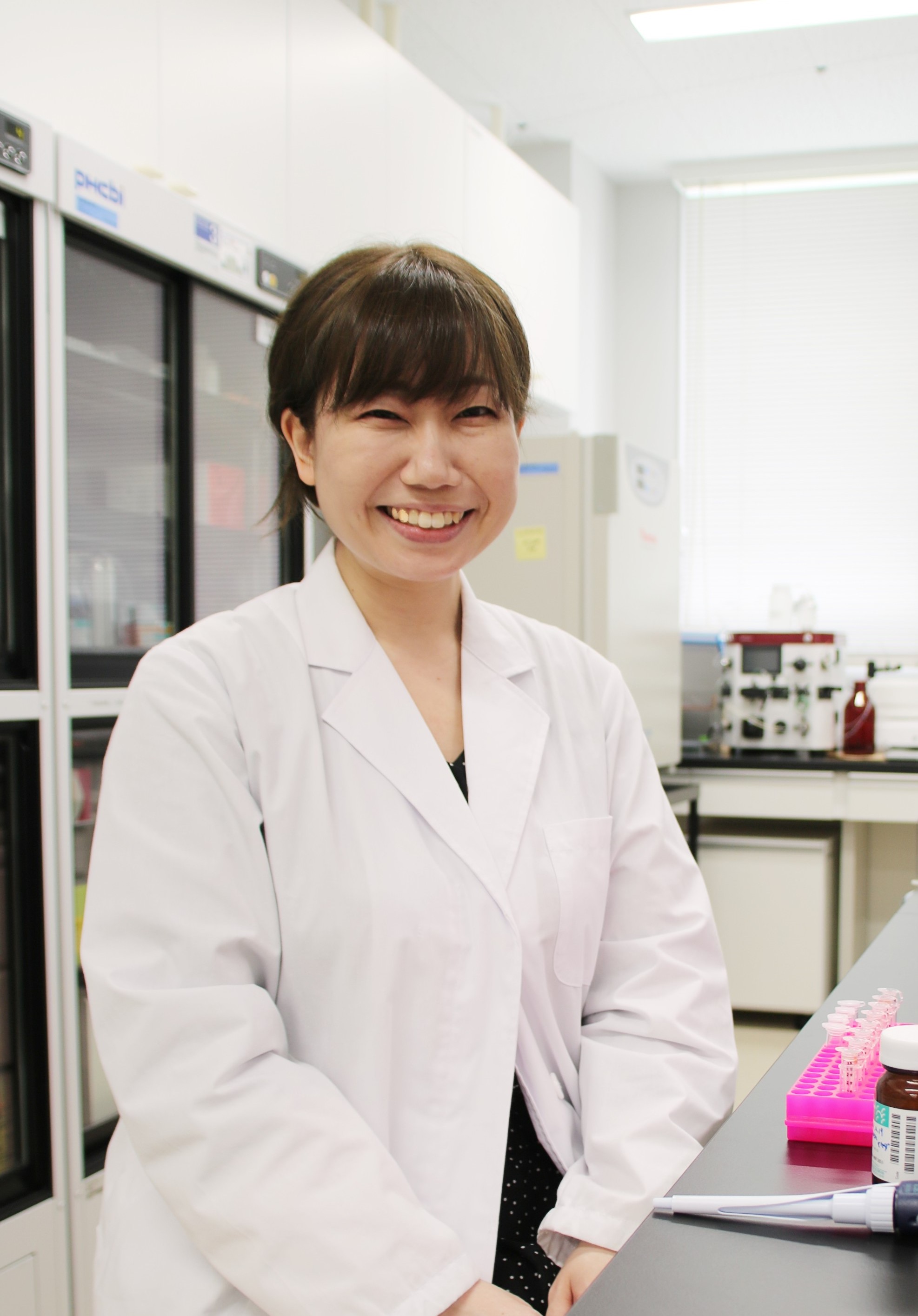その他
「コロナうつはなぜ起きるのか--精神疾患を薬に頼らずに治す「行動栄養学」というアプローチ」応用生物科学科 池田裕美助教 (FLOW84号「研究最前線」より)
コロナ禍で自粛生活が長引き、他人と交わる機会が減ったりして、心を病む人が増えています。一般に「コロナうつ」と呼ばれ、英国ではコロナ感染症から回復した3人に1人が半年以内に何らかの精神疾患を発症したという研究報告もあり、今後も増加することが懸念されます。
池田助教は「運動不足や孤独感がうつ症状を引き起こすという研究結果がある」と警鐘を鳴らします。新規分野の開拓に挑む「行動栄養学」はそうした精神疾患を防ぐ一つのアプローチです。動物行動学と動物栄養学を組み合わせた新たな研究分野で、薬剤ではなく栄養素で行動をコントロールすることで精神疾患の予防や改善を図ることを研究のゴールとしています。
強いストレスを受けた時、ヒトや動物は異常な行動を示す場合があります。その中でも特に池田助教は「常同行動」という動きに着目します。動物園で、檻の中の動物が同じ動きを繰り返すのもこの常同行動です。池田助教は、マウスなどをモデルにさまざまな環境下でのストレス状態や行動を調べ、ヒトへの応用に取り組んでいます。例えば、ケージの中に長期にわたり1匹で飼育したマウスの多くに常同行動がみられ、集団で飼育したマウスにはみられないことを明らかにしました。また、不安を感じやすい性質のマウスは、そうでない性質のマウスより強い常同行動を示すことも突き止めました。
こうした異常行動を抑制するため、「栄養素、とりわけ、タンパク質の基になるアミノ酸が有効ではないか」。そんな仮説を立て、池田助教はおとなしい種類のハムスターと、せわしなく動く種類のハムスターの運動機能をつかさどる小脳にアミノ酸がどれくらい含まれているかを調べました。その結果、おとなしい種類の脳内では鎮静・催眠作用を有するセリンが多く、せわしなく動く種類では少ないことが分かり、セリンが行動の沈静化に効いている可能性が示唆されました。
今はまだ動物実験の段階ですが、池田助教はヒトへの応用に自信を見せます。セリンは牛乳やカツオ節など日ごろよく口にする食品に多く含まれます。即効性では薬より劣りますが、「栄養素は日常的に安心して摂取でき、予防的観点からもメリットがあります。子供も気兼ねなく口にできます」。
コロナうつが広がる時代に、手軽に摂取できるサプリメントなどへの応用にも期待が膨らみます。「企業との連携も提案していきたい」と研究開発を続けています。
■いけだ・ひろみ 2012年鹿児島大学農学部生 物生産学科卒。2018年九州大学大学院生物資源環境科学府資源生物科学専攻博士後期課程修了。日本学術振興会特別研究員などを経て2020年から現職。博士(農学)。熊本県出身。
▼FLOW94号eBook(8月5日発行)はこちらから
https://www.josho.ac.jp/flow/