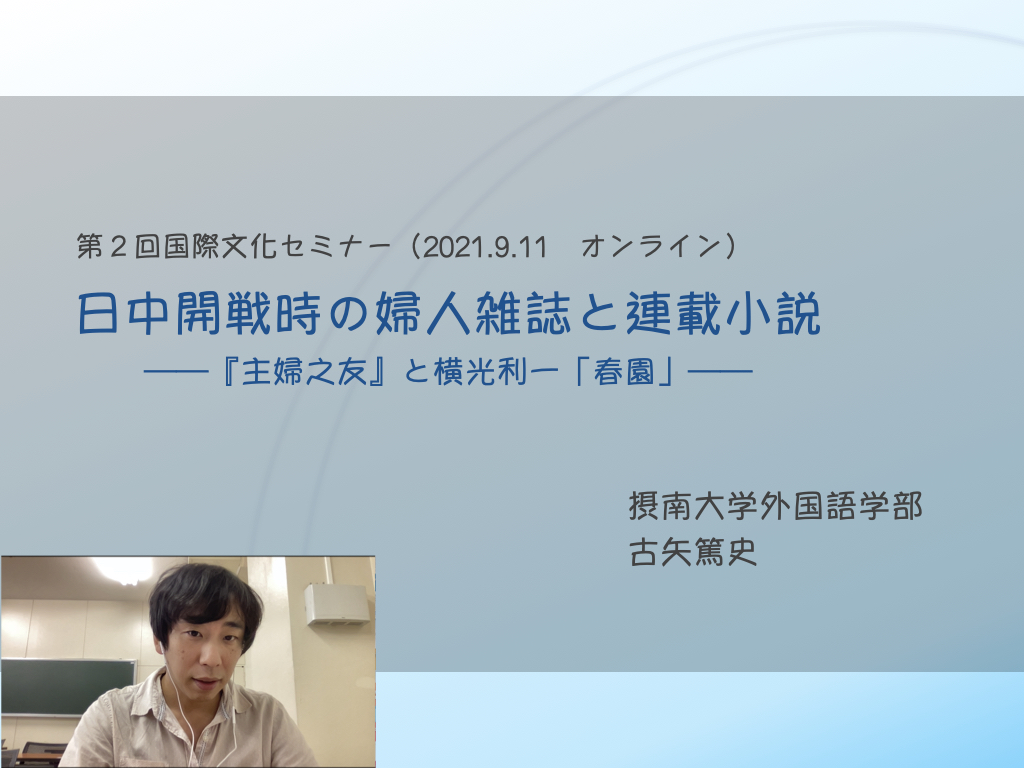国際学部
第2回国際文化セミナーを開催しました。
外国語学部主催の第2回国際文化セミナーが、9月11日(土)11時~12時に、Zoomによるオンライン形式で開催されました。学内外から多くの参加者に集まっていただきました。
今回は「イメージ×テクスト — 日本近代文学、ルネサンス美術、ジェンダー」と題して、外国語学部の古矢篤史講師、杉山博昭講師が発表を行いました。文化の一領域として別々のものと捉えられがちなイメージとテクストですが、両者の接点の「場」(メディア)に注目することで、双方の理解をより多角的に展開し、より深く掘り下げることができるのではないかという問題提起をテーマの狙いとしています。
古矢講師の発表のタイトルは「日中開戦時の婦人雑誌と連載小説 —『主婦之友』と横光利一「春園」」でした。本発表は、横山利一の小説「春園」と小説が掲載された『主婦之友』との関係性を、小説の連載中に勃発した日中開戦という時局を背景にして読み解こうとするものです。以下、発表の要約です。
「春園」の主人公美紀子は、物語の前半と後半で大きく人物像が変化します。西洋近代の教養を身につけた活動的な人物(百貨店の店員)から日本文化をたしなみ、献身的に家事や看護に専念する「主婦」となるのです。この変化に対応するのが、『主婦之友』の提示する女性像の変化です。日中開戦前は、目次の口絵に解放的な女性のイラストが使用されているのに対して、開戦後は「銃後」を守る献身的な女性が描かれるようになります。小説の中には戦争に関係する場面や描写はなく、小説(テクスト)だけを対象とするなら、なぜ主人公の人物像が変化したかは理解しにくいところがあります。しかし、小説が掲載された『主婦之友』における女性像が大きく変化したことを重ねてみると、「春園」の美紀子の人物像の変化が、実は戦時下において求められた女性の役割に対応していることが浮かび上がってきます。小説が掲載されたメディアに注目することによって、小説への理解がより多角的になされる可能性が開かれると言えるでしょう。
杉山講師の発表のタイトルは「ルネサンス期の聖史劇と婚礼家具 —「スザンナ」を巡る機制と欲望」でした。本発表は、15世紀フィレンツェにおける宗教絵画(婚礼家具の装飾画)と演劇(宗教劇)を旧約聖書のテクストと重ね合わせることで、当時の人々の「聖」と「性」の交差の結び目を明らかにしようとするものです。以下、発表の要約です。
旧約聖書外典の聖女スザンナのエピソード(テクスト)は、貞節を守るためには死をもいとわない聖女スザンナが、好色で悪辣な2人の老判事の偽りの告発を、聖ダニエルの助けによって退けるというものですが、スザンナが庭で水浴をしているところを判事たちが覗いている場面、判事の悪事が露見し死刑に処せられる場面が出てきます。スザンナの水浴の場面は、多くの画家によって描かれてきましたが、15世紀フィレンツェの婚礼家具にもこの2つの場面が描かれています。特に、スザンナの裸体のイメージは、一方で貞操への「抑圧(機制)」として働きつつも、特に男性に対しては欲望を「惹起」するという両価感情を引き起こします。さらに、同時代の聖史劇で演じられることで、スザンナのエピソードは、より広く人々に知られるようになります。そこでは、女装をしたうら若い少年が、「限界まで肌を露出して」セザンヌを演じました。聖史劇においては、聖性と禁忌(同性愛と幼児性愛に対する)が相反するがゆえに結びついていることを見てとることができます。絵画と劇に注目することで、テクストとイメージのはざまで聖と性とが交差しているありようが浮かび上がってくるのです。
いずれの発表も大変知的興味を喚起するものでした。今回も60名弱の参加者があり、学生からの質問も含め熱心な質疑応答が行われました。
画像1:古矢篤史講師
「日中開戦時の婦人雑誌と連載小説 —『主婦之友』と横光利一「春園」」
画像2:杉山博昭講師
「ルネサンス期の聖史劇と婚礼家具 —「スザンナ」を巡る機制と欲望」
(報告者 有馬善一)
第3回「国際文化セミナー」(摂南大学外国語学部)
2021年11月13日(土)11:00~12:00 (開場10:45)
講演テーマ:「トランスナショナルな世界をよみとく」
発表1:森 類臣(特任准教授)
「K-pop、韓ドラの社会学—Convergence Cultureから考える韓国現代文化—」
発表2:加来奈奈(准教授)
「ハプスブルク家の結婚政策—神聖ローマ皇帝カール5世と彼をめぐる女性親族たち—
申込みフォーム:https://forms.office.com/r/gBR1kKBh3i