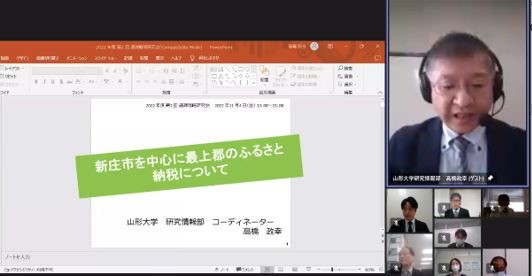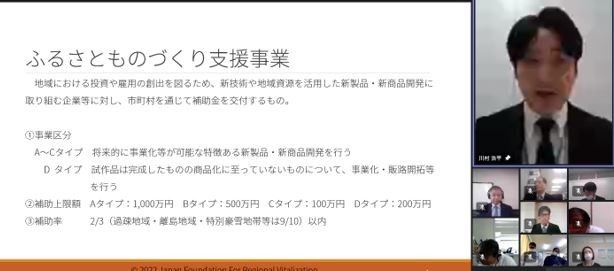その他
「過疎」を「適疎」に転換! 自治体の関心も拡大 -人口減少の課題解決支援へ「適疎戦略研究会」-
摂南大学(学長:荻田喜代一)地域総合研究所(所長:経済学部 教授 野長瀬裕二)は、過疎認定を受けた自治体や人口減少に直面する自治体の活性化に向けて学術面でのサポートを行う「適(てき)疎(そ)戦略研究会」を運営しています。11月4日に開催した第2回研究会では、「ふるさと納税」をテーマに実施しました。自治体の関心は高く、参加自治体も増えています。
【本件のポイント】
● 第2回適疎戦略研究会では、「ふるさと納税」について有識者を交えた勉強会を開催
● 2府4県から18の自治体が参加し、成功事例や課題を共有
関西では適疎自治体や過疎予備群の急速な増加に加え人口減少が進み、過疎地域の持続的発展に向けた支援が深刻な課題となっています。「適疎」とは「人口減少に対して適切な対応をとり、持続可能な地域経済/生活基盤がある状態」を表す近年注目される考えで、地方再生のヒントとされます。
本年度発足した、「適疎戦略研究会」では、自治体が問題意識を共有するためのネットワーク構築を行い、経済学、経営学、農学、看護学など総合大学ならではのさまざまな分野の教員らの学術的知見を用いて、雇用や経済・インフラ面など多岐にわたる課題の把握・共有や、個別自治体の問題解決に向けた共同研究などのサポートに力を入れています。発足6カ月で2府4県をはじめとした21の自治体が会員として加盟しました。
11月4日には「ふるさと納税」をテーマに第2回の適疎戦略研究会を実施。山形大学 産学連携研究員の高橋政幸氏は、「新庄市を中心に最上郡のふるさと納税について」と題して、山形県最上地域におけるふるさと納税の獲得に向けた取り組みや成功事例を紹介し、地域に根差した民間事業者の活用やふるさと納税ポータルサイトとの提携の重要性を示唆し、次に一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団) 融資部の川村浩平氏が「ふるさとものづくり支援事業」を活用した返礼品開発事例を紹介。最後に、株式会社CAMPFIRE 事業統括部の長田 拓氏が、「ふるさと納税型クラウドファンディング」の制度を説明。「支援を募るには、返礼品にまつわるストーリー性やその自治体を応援したいと思わせる共感性が重要となる」といったアドバイスを行いました。
次回の研究会では、「過疎地域に投資する企業」をテーマに、投資実績のある企業を招き、産業振興や企業誘致などについて考えます。
■内容に関するお問い合わせ先
摂南大学 研究支援・社会連携センター(担当:吉田)TEL:072-829-0385