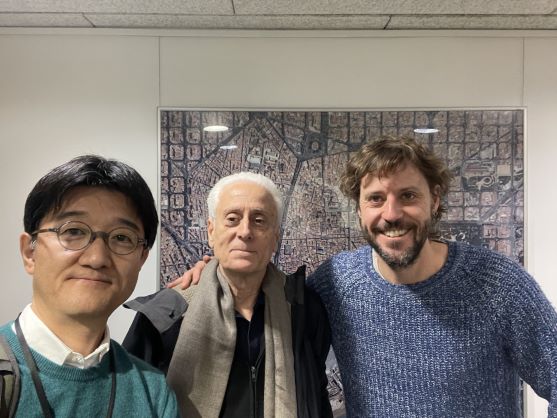理工学部
【理工学部】長期海外出張報告 スペイン・バルセロナ市カタルーニャ工科大学
2023年8月21日から2024年8月15日まで、スペイン・バルセロナ市にあるカタルーニャ工科大学Universitat Politècnica de Catalunyaのバルセロナ建築高等研究院にて、研究・教育活動を行なってまいりました。その活動や生活環境、街の様子について報告したいと思います。
大学ではカタルーニャ都市建築遺産講座に席を用意していただき、都市史研究グループの先生方と、バルセロナ市が取り組む都市計画戦略の仕組みや課題について研究していました。具体的には、「界隈計画Pla de Barris」や「スーパー街区Superilla」と呼ばれる、バルセロナ市における現代的な都市計画技術です。
界隈計画Pla de Barrisとは地区単位で都市生活圏の改善を目指す施策で、市全体の10区に属する合計73に区分された界隈Barriから介入が必要な地区を選定し、地区の状況に応じた生活環境の改善策を実施するというものです。これは4年間を一まとまりの期間とし、公共空間・教育環境・住宅環境・雇用環境・福祉環境などを改善する具体的な事業を地域分析と住民との対話を通して立案し、選定された界隈を対象に実施する施策です。例えば、公共空間に関しては、歩行者空間や小広場の整備、植樹の促進などがあります。教育環境については、図書館の整備から学校での課外活動の支援、地区に住む移民への言語教育まで幅広いアクションが用意されています。従来の長期・広範囲にわたる物理的な空間整備に重点を置いた都市計画というよりも、地区の居住環境としての持続性の向上を目指す地域界隈の生活環境の整備改善と地区アイデンティティの構築を目指すものです。対象地区の選定には、多様な評価軸が用意され、科学的に地域診断がなされ、脆弱性の高い地区が優先的に選択されます。福祉政策を含めた都市計画のようにみえますが、区域単位での比較的小さな生活環境を単位とするものであり、地域住民の参画を重要視し、具体的な施策の検討段階から建築家が介入することが大きな特徴だと言えます。
スーパー街区とは、気候変動による危機に対するもので、基本的には都市の緑化を目指した取り組みです。車道空間を歩行者空間化し、植栽を施し、交通手段は低速のモビリティを前提とした物理的、システム的な改善策です。自動車中心社会だった街に、緑と休憩場所に溢れた場所を増やしていくというものです。そのために、都市全体の交通システムの改善(バスやトラム線)や緑軸Eje Verdeと呼ばれる植樹帯を増やし、都市を取り巻く生態系にも配慮したヒューマニティを回復する空間整備の手法だと言えます。ポジティブな側面のみが取り上げられがちですが、その背後には、どの地区に介入するか、実践した後に生じる地区格差、空間整備の持続性などが大きな課題としてあります。
文献やアーカイブの調査から市の施策の把握、施策の歴史的変遷や技術的側面についての市の様々な関係者へのインタビューから得られた知見は、これらの施策の実態と課題を把握するうえで大変貴重なものとなりました。
またバルセロナ建築高等研究院ETSABでは、受け入れ教員のM. Rosselló先生、D.Falagán先生が受け持つ修士課程の授業「20世紀のバルセロナ都市住宅環境史」に参加していました。半期15週というのは日本と同じですが、一回3時間でした。私はそのうち2回、比較考察として、日本の住環境および都市住宅の講義を担当しました。講義は拙いスペイン語でやりましたが、違うコースの学生も含めて皆熱心に聴講してくれました。多くの質問があり、質疑応答やディスカッションの時間は大変充実していました。大学院コースは社会人が自身の勤務時間を調整しながら大学に通うというのが一般的でした。年齢も様々で私と年齢も変わらない学生も珍しくなく、良い交友関係を築くことができました。他にもジローナ大学Universitat de GironaやNipponia日本文化アカデミーなどから声をかけていただき、日本の住居や都市空間の成り立ちについて講演を行う機会をいただきました。
バルセロナでの生活は、様々な面に置いて快適だと感じるものでした。人口160万人の大きな都市ですが、精肉店や魚屋や金物屋といった生活に必要な小売店がとても多いです。地区ごとには公設市場や図書館をはじめとする様々な公共施設も充実しており、「15分都市」と言えるほどのコンパクトな生活圏が成立していると言えます。公共交通機関も、縦横無尽にバスや地下鉄やトラムが走り、75分以内は乗り換え自由など、合理的に移動できる交通システムが構築されています。バスは車椅子の乗降もスムーズです。二酸化炭素排出量の削減に向けて、地元住民を対象としたbicingと呼ばれるコミュニティサイクルシステムも取り入れられており、街はサイクルステーション、自転車レーンとも大変充実しています。他にも、生活ゴミの回収コンテナの設置場所の多さやごみ収集システム、公共空間の清掃、地区の緑地や公園の多さ、犬の散歩可能な場所や店舗の多さなど、公共サービスの質的向上への関心は非常に高い都市でした。
異文化に来たからには徹底的にその中に入ろうと、いただいたお誘いは出来る限り受け、多くの方々と出会うことができました。私の凝り固まった頭は掻き回され、より広い多様性に触れることができた刺激的な日々でした。
今後ますます、海外に出かける機会だけでなく、国内でも外国人と交流する機会も増えてくると思います。日本人であっても皆それぞれ異文化を背景に持っているとすら言えるでしょう。学生の皆さんこそ、若い頃から自ら進んで異文化に触れ、異なる価値観を受け入れ、その背後にある文化や習慣を見つめる機会にしてください。視野を少し拡げて、異文化だと思っていた遠いものごとが案外近いものに感じられることもあると思います。
(記載はすべてカタルーニャ語)
理工学部建築学科
加嶋章博