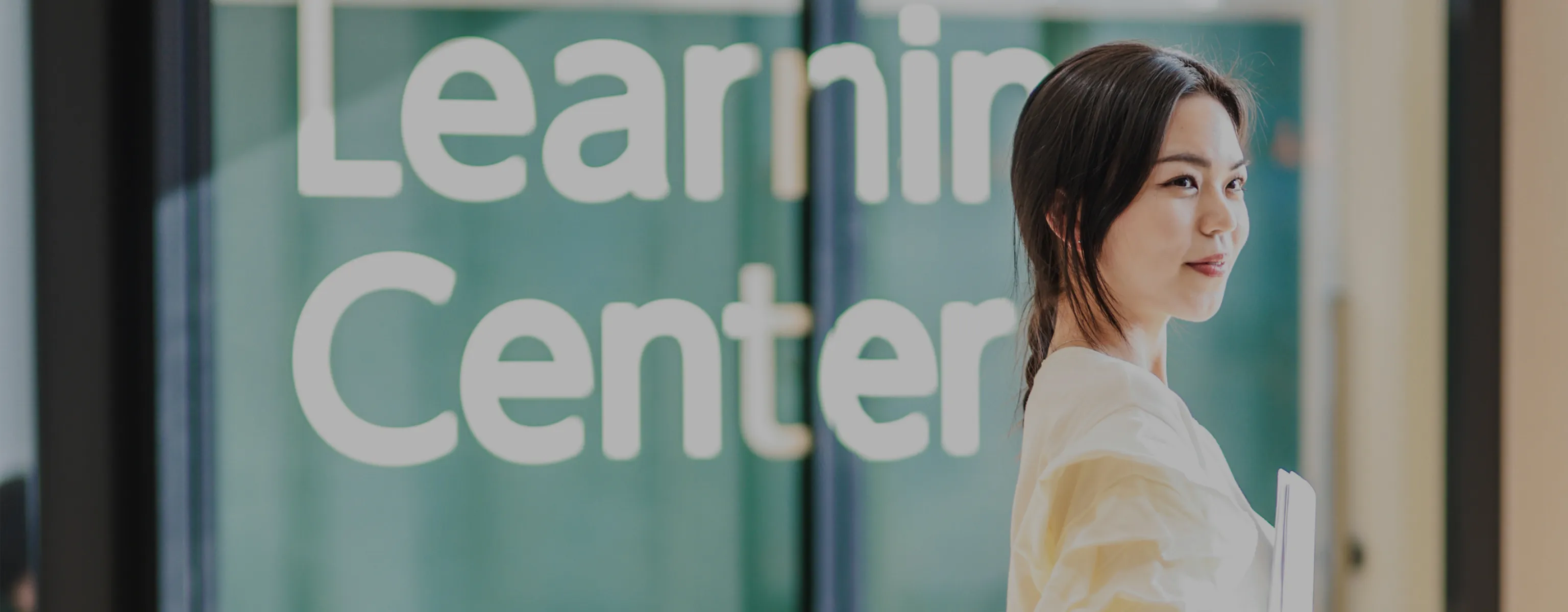言語から、経済から、美術から...異文化を研究。
世界とコミュニケーションする方法はひとつじゃない。
1年次から少人数制のゼミナールを設けています。現地の新聞記事など、比較的親しみすい教材を用いた学習やスピーチを行なう基礎的ゼミナールからスタートし、年次が進むごとにより専門性を高めていけるよう段階的に設定しています。自分の関心のあるテーマを取り上げ、担当教員の指導のもと、自ら探究し、学ぶ姿勢を身につけながら、4年次には発表や討論を通じて実践的なコミュニケーション能力を強化します。
日本史学
教授赤澤 春彦
「歴史学」というと、「難しそう」とか「暗記しなければ」と思うかもしれません。しかし、私たちの身のまわりのあらゆるものは、人々の暮らしのなかで生まれ、育まれてきました。皆さんが興味を持っているファッションや音楽など、どのようなことにも歴史があります。
また、歴史は「覚える」ことが目的ではありません。資料を集めて新たな発見をしたり、様々な可能性や解釈を考えたりすることに面白さがあります。このゼミではゼミ生それぞれが興味を持ったことについて、資料を探して、みなでディスカッションしながら深く掘り下げて考えていきます。
アメリカ文学
准教授天野 貴史
小説とは、「私ではない誰か」が「私ではない誰か」を主人公にして「私ではない誰か」に向けて書いた物語であり、それは「他者」そのものであると言ってよいでしょう(だから小説は「わからない」)。このゼミでは、ゆっくりとページをめくりながら、そこに現れた「他者」と真摯に向き合うとともに、「他ならぬ私」についても理解を深めていきたいと思います(とはいえ、小説はわからないとつまらないので、読むときのコツのようなものも学んでいきます)。
オセアニアの歴史と文化
講師新井 隆
欧米諸国や日本のオセアニア地域に対する認識には、時代を経ながら羨望と侮蔑という相反する見方が入り混じってきました。さらに、19世紀末から20世紀前半には、オセアニアを含む世界各地に欧米列強や日本が勢力を拡大させていきました(植民地支配の拡大)。
このゼミでは、オセアニア地域の歴史や文化について、欧米諸国や日本をはじめとするアジア諸国との関わりも踏まえつつ、俯瞰的な視野から自分の考えを伝える能力を養います。
そのなかで、オセアニア地域や現代世界が抱える様々な問題と自分たちの暮らしが歴史的につながっていることを感じてもらいたいと思います。
哲学、倫理学
教授有馬 善一
現代社会は、マス・メディアやインターネットの発達によって、高度に情報化しています。私たちを取り巻く大量の情報は、生活に役立つものでもありますが、反面、リアルとヴァーチャルの境界を曖昧にしてしまうものでもあります(例えば、フェイクニュースの氾濫)。このゼミでは、インターネット空間やマンガ・アニメのリアリティ(と嘘っぽさ)とは何かについて、具体的な問題や作品を取り上げて、共に考え、議論をしていくことで、現代の人間社会の抱える問題について掘り下げていきます。
英文学
准教授池田 景子
文学作品は難しい言葉で書かれていて"とっつきにくい"イメージを持つ人もいるかもしれません。もちろん作品や作家に対する好き嫌いはありますが、じっくり読んでみるとその作品や作家の良さや魅力がだんだんとわかってくることもあります。このゼミでは文学作品をいっしょに読んで、文化的背景も考えながら作家の問題意識にアプローチしていきたいと思います。そのうえで、その作品(作家)の魅力といった感性に訴えかける側面を自分なりに論理的に説明をする練習をします。
文化人類学
教授上田 達
「文化人類学で世界を学ぶ」がテーマです。文化人類学は、自分たちに馴染みのない考え方や慣習を対象として、それらの理解について考える学問です。ゼミでは、こうした文化人類学のコモン(共通の)・センス(感覚)を身につけることを目指します。
担当者は東南アジア島嶼部(マレーシアと東ティモール)で調査・研究をおこなってきました。同時代を生きる他者の暮らしや文化的営みについて、知見を共有しながら学んでいきましょう。
社会学、インドネシア地域研究
教授浦野 崇央
わたしたちにとっての「あたりまえ」を疑ってみると、必ずや新たな「発見」があります。このゼミでは、現代社会におけるさまざまな事象を題材に、新たな視点で深く考えます。
なお、担当者の専門領域は社会学/インドネシア地域研究ですが、ゼミ生の取り組むテーマは多岐にわたっています。
環境学、自然地理学
講師大谷 侑也
国内や世界のさまざまな地域の自然環境を知りそこで人々がどのような生活を営んでいるのかを調べ、記述できる力を身につけることを目標とします。あなたの興味がある地域(たとえば本州、沖縄、東南アジア、アフリカ、太平洋の国々等)はどこですか?その地域を調べ、仮説を立て、調査を行い、その結果を分析して考察する能力を獲得しましょう。この一連の流れを遂行する能力は卒業後、企業や役所等でも必ず役に立つはずです。
中国近現代史、中国地域研究
講師小都 晶子
外国語を習得し、その国の人とつきあっていくと、文化や考えかたの違いに戸惑うことがあります。こうしたとき、その国/地域の歴史的・社会的背景を理解していることは、ことばと同じくらい重要になってくるでしょう。このゼミでは、中国語圏をとりあげて、特定の国/地域の文化や社会への理解を深め、研究するための方法を学びます。香港、台湾などを含め、広く中国語圏の社会や文化に関心のあるみなさんを歓迎します。
異文化コミュニケーション
講師カーティス・チュウ
The goal of this seminar is to help students acquire skills for communicating across cultures. In addition to learning about theories in intercultural communication, students will conduct virtual exchanges with students abroad to experience intercultural collaborations and learn about diversity. Project-based learning is at the core of this seminar.
西洋史学
准教授加来 奈奈
ゼミでは、ヨーロッパ(場合によっては、アメリカ)の政治・社会・文化・ジェンダーを歴史の視点から学んでいきます。先行研究(研究書)や当時の人々が書き残した史料(手紙、年代記、新聞、挿絵など)について触れながら、歴史を読み解きます。ヨーロッパ(アメリカ)の歴史や文化またはジェンダーに関して、自分がおもしろいと思ったことや、これが好きというものを、じっくり掘り下げて、過去と向き合い、客観性を身に着けながらも、自分らしい視点で歴史(社会)を見て、表現する力を養います。
教育工学、英語教育
教授柏原 郁子
柏原ゼミでは、さまざまなICT教材やAI機能を備えた学習アプリなど利用し、楽しみながら英語学習する体験ができます。そして、自分の目標としている英語レベルに達するようコーチングを行います。例えばどんな教材なら学習が継続できるのか、どんな学習方法なら無理なく継続できるのか、また学習を継続するためにはどのような動機付けが必要なのかをアドバイスをしていきます。自分に合う学習教材・方法が見つかれば、生涯を通じて「言葉」を学ぶ喜びを手に入れることができるはず。ゼミでは、卒業論文指導はもちろん、さまざまなテーマで意見交換をしたり、ゼミ生同士で情報交換するなど、毎週和やかな雰囲気の時間が過ごせます。ゼミの卒業生には、カナダやオーストラリアへの短期留学を経て、ANA、JAL、ルイ・ヴィトンジャパン、総合商社、教職等さまざまな業界に就職をして活躍している方もいます。英語のスキルを身につけて、世界に羽ばたきませんか。
日本語・日本語教育と異文化コミュニケーション
教授門脇 薫
日本語を母語としない外国人を対象にした「日本語教育」をとおして、海外や日本国内で起こっているさまざまな動きを「日本・日本語」、そして自分自身に 関連づけて考え、よりよい社会のために行動できるようになることをめざします。 日本語を母語としない人たち、言葉も文化も異なる人たちと接するにはどのようにしたらいいかを考えることが、広い意味の日本語教育です。今後日本に在住する外国人は更に増加すると考えられます。2019年に「日本語教育推進法」が施行され、ますます日本語教育の重要性が高まっています。大学在学中や卒業後に日本国内や海外で、言葉や文化の違う多様な人たちと接することがあると思います。広い意味の「日本語教育」をとおして広く言葉・文化・コミュニケーション等について一緒に学びましょう!
researchmap文化人類学
准教授金子 正徳
このゼミでは、多様な異文化に生きる人々のくらしと変化に注目しています。「あたりまえ」に思っていることが実は他地域では得がたいものだったり、びっくりするほど近年になって定着したものだったり、あるいは知らないところでそんな「あたりまえ」を揺るがす変化が密かに進行していることもあります。文化人類学的な考え方をベースとして、文化や社会を草の根の視点から捉えるための考え方を学び、総合的に考える力を養うゼミにしたいと思っています。
SDGs and Art
講師香林 綾子
このゼミでは、国際問題、SDGsを英語で理解し、世界の課題を知り、世界の人と協同を通じて解決していくことのできる温かい心と、目標を設定し、目標を達成するために行動できる自律性を持った学習者を育成することを目指します。
ゼミでは、国際問題、SDGsを英語で学びながら、異文化理解を深め、英語・日本語でコミュニケーションしながら実践を積んでいきます。
ゼミで扱う内容は主に国際問題やSDGsですが、その領域は広いので、例えば、ファッション、アート、文学、映画などに興味があり、それらを研究対象とし研究することも可能です。それらの表現を主観的に、客観的に観察し、考察・分析し、新しい価値観を創造し、表現力を磨き、世界で活躍することを期待しています。
コーパス言語学
准教授後藤 一章
本ゼミでは、AI (人口知能) について学ぶとともに、AI 活用の様々な可能性を探ります。ChatGPT の登場により、我々の知的生産活動はある種のシンギュラリティへ到達しました。読解、論述、翻訳、作曲、描画、プログラミングなど、多様な分野で AI は驚異的な性能を示しつつあります。一方、世間の AI に対する反応は様々であり、教育や研究への AI の利用もまだまだ手探りの段階です。AI の理解を深め、そのメリット及び、デメリットをみんなで議論していきましょう。
人文地理学
講師小林 基
このゼミでは「まち」で過ごす時間を持つことで、日常生活が大きく変わることを学びます。まちは、皆さんの日常に彩りと新鮮さをもたらします。気の合う仲間と出逢ったり、趣味やイベントに興じたり、誰かのたすけになるような活動をしたり。さらには、副業・転職・起業のきっかけを得たり。まちは、人が生きがいに打ち込んだり、活躍し、成長していく「舞台」なのです。まずは、まちで活躍する人々と実際に出逢い、その人たちの生き方から学びましょう。そして、次は自分で実践してみましょう。自分の人生に、そして社会に、ちいさな革命を起こす。それが、このゼミのねらいです!
英語教育学、英文学(国際学部)
教授齋藤 安以子
「知っている、と思っていることを、自分は本当に知っているのか?」と問い、仮説を検証するための技術を学びます。世界はワクワクすることに満ちているので、担当者の研究テーマ以外の題材もゼミにはたびたび登場します。教職・演劇・言葉・マンガ・映像・メディア・食、なんでも研究対象になります。「キャベツ」で卒論を仕上げたゼミ生もいます。
表象文化論、西洋美術史、中世演劇史
講師杉山 博昭
画像生成AIが活況を呈す現在、イメージの氾濫がみだりに始まってしまいました。その結果、イメージとヒトの関係も混迷の度合いを深め続けています。もはやイメージと無関係に生きるという選択肢を奪われたわたしたちは、イメージとのより良い接点を探らなければなりません。ここで重要なのは、イメージを自分の眼で見る、言い換えれば、イメージを自分の言葉で語ることです。また、かつてイメージがいかに見て語られてきたかをたどることも大切でしょう。過去は未来の道しるべになるからです。このような技術や情報を整理・集成したものを、人類は「美術史」「美術批評」と呼んでいます。わたしがみなさんと共有したいと思うのは、その方法と効果です。
政治学、宗教学
教授田中 悟
このゼミでは、皆さん自身の身近な興味や関心を出発点として、最終的に「他の人に読んでもらえる論理的な文章=論文」を書きあげることをめざします。そのためにゼミでは、論文を書くための手順を段階的に身に付けていきます。 担当者は日本と韓国の近現代社会を主な研究対象にしていますが、皆さんは必ずしもそれにとらわれる必要はありません。「自分の考えていること/言いたいこと」を明確にして、それを他人に伝えて「わかってもらう」ためには、どのようなことに気を配る必要があるのか。ゼミという場を通じて他人の力を借りながら、互いに学んでいきましょう。
アメリカ研究
教授鳥居 祐介
アメリカ合衆国の社会、歴史、文化についての基礎知識を身につけ、各自の個人研究テーマを見つけ、ゼミ仲間、教員と一緒に深掘りをしていきます。音楽、映画、スポーツ、歴史、時事ニュースなど幅広いジャンルのテーマが対象です。アメリカに関心がある人、人種、ジェンダー/セクシュアリティ、経済格差の問題に関心のある人、英語力や海外経験を生かした卒業研究をしたい人におすすめです。毎週各自のテーマに沿った資料やメモを持ち寄って話し合い、2年間じっくりかけて卒業研究レポートを完成させます。
英語音声学
教授中島 直嗣
2つの専門分野を持ち、「二刀流」で研究・授業を行っています。ゼミでは「国際ビジネス論」をテーマにしています。国内外のグローバル企業の事業展開やマーケティング戦略に注目し、国際ビジネスの要点について具体的な事例とともに研究します。その際、サプライチェーン、地政学的リスク、SDGsの対応策なども交えて考察しています。また、グローバル企業は、それぞれの国や地域に合わせて製品やサービスを現地化している場合も少なくないため、文化・宗教・歴史的背景、社会的慣習、地理的条件といった多角的な視点からも分析していきます。卒業後ビジネスパーソンとして大企業を中心にグローバルに活躍できる人材の育成が大きな目標です。
日本の文化について考える
教授橋本 正俊
「日本文化」 よく聞く言葉ですが、いったい何を、どのようなものを指すのでしょうか。そしてそれはなぜ「日本文化」と言えるのでしょうか。
このゼミでは、様々な資料や文献、現地調査などをもとに、自分の関心ある研究テーマを見付けて、突き詰めることを目指します。そしてそれは、現在の日本、そして世界について見つめ直すきっかけとなるでしょう。
国際関係論
講師原田 豪
ウクライナ戦争をはじめ、日々のニュースでは海外で起こるさまざまな出来事が報じられています。これらの出来事は私たちと決して無関係でないにもかかわらず、「外」で起こっているために分かりづらいものとなっています。このゼミではこのような「分かりづらい事」を「調べ」、「考え」、分かったことを「伝える」力を身につけることを目的とします。
アメリカン・コミックス研究
講師トッド・フーパー
In this all-English seminar, we examine American comics to discover how design is vital to the storytelling process in comics. Additionally, we look at how social issues in American are represented in comics. Through this research, we can learn about similarities and differences between cultures.
この完全英語セミナーでは、アメリカン・コミックを検証し、コミックのストーリー展開においてデザインがいかに重要であるかを発見します。さらに、アメリカの社会問題がコミックの中でどのように表現されているかを考察します。この研究を通して、文化間の類似点と相違点を学ぶことができます。
身近なモノから企業戦略を考える
教授藤井 嘉祥
ゼミは企業の競争戦略の分析とプレゼンスキルの向上の二本柱で展開します。世界規模でのビジネス戦略が求められる時代にあって、企業の成長にはどのような戦略が必要なのかを競争戦略の理論を参考に読み解きます。また企業戦略には貧困などの社会課題を解決するソーシャルビジネスも含まれます。企業利益と社会課題解決を両立させる方法や国際協力についても考えます。
英語学、言語学
准教授藤原 崇
本ゼミでは、英語の文法(学校文法ではなく記述文法)をテーマとし、実際に観察される言語データをどのように分析するのかを学びます。次に理論的に導きだされる予測と実際に収集した言語データとの間にどのような違いが観察されるのか、その違いはどのように説明できるのかについて学びます。
機能言語学
准教授船本 弘史
このゼミでは誰もがもっている「ことば」について知ることをねらいとします。ゼミではさまざまなトピック(ことばそのものの仕組みをはじめとして、文化、社会、心、環境、(人工)知能などいろんな角度から見たことば)を取り上げます。それらに関連する文献を読みながらことばの諸問題を科学的に説明するための知識や方法を身につけていきます。
日本文学、メディア論
准教授古矢 篤史
私たちは日常生活の中で、インターネット、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、広告など、さまざまな「メディア」を経験しています。近代以降の大量生産・大量消費を前提とする社会において、日常的なコミュニケーションや文化体験はもはや「メディア」なしには成り立ちません。このゼミでは、そのような「メディア」の働き・特徴・歴史などを学習し、現代社会における「メディア」を通じたコミュニケーションや文化のありかたについて考察していきます。
英語教育学
准教授マイケル・ハーキー
The English language is not an object for study but a tool for the mind. In this seminar we will use the text “Justice” to learn how to think about and tackle the many moral issues and ethical dilemmas people face and then apply our thinking to local Japanese examples.
地域研究(韓国・朝鮮)および東アジア国際関係論
准教授森 類臣
文化・社会・国際関係など多様な視点から「コリア-Korea-」(韓国・朝鮮・海外コリアンなど)にアプローチし、多面的に理解を深めていきます。主に次の4点です。
1)韓国社会について、現代史の勉強を基礎にして総体的に理解していきます。
2)日韓・日朝関係について、現代史・外交・市民交流などの次元から考察していきます。
3)東アジア国際関係という視点から、朝鮮半島の現在を捉えていきます。
4)在日コリアンの歴史と現在について、フィールドワークに参加しつつ学んでいきます。
ゼミナールでは、共同研究をとおして学生・教員がともに学んでいく姿勢を大事にします。文献を通した学びのみならず、積極的に現地調査をしていきます。