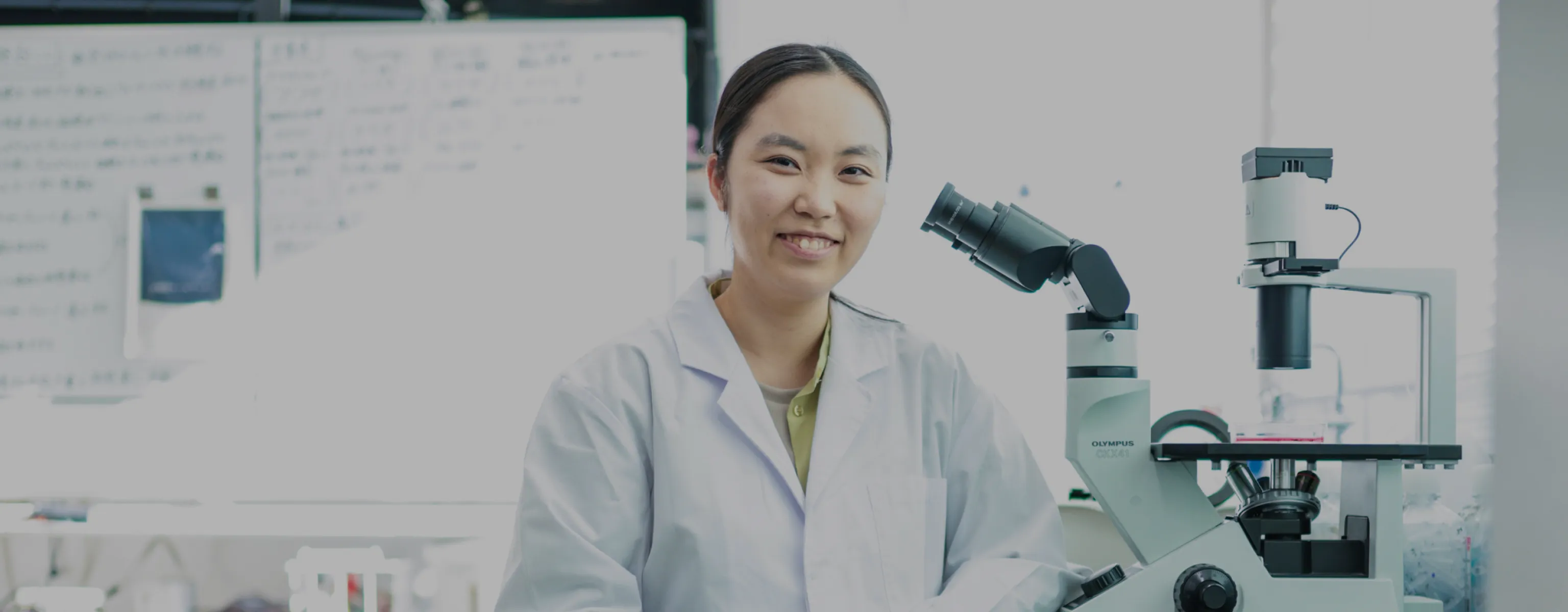生命科学の進化に立ち会える、
研究の最前線がここに。
生命科学科は以下のような研究室が設置されています。そこは生命の不思議と自然との共生を追究する最前線。まさに生命科学進化に立ち会える現場です。卒業研究ではいずれかの研究室に所属し、少人数環境のもと密度の濃い研究活動に従事します。
生殖生物学研究室
講師井尻 貴之
卵は生命のはじまりであり、その卵を活性化させるのが精子です。卵や精子においてもエネルギーを蓄える分子であるATPが重要な働きをしますが、生殖細胞が分化して卵細胞や精子が形成された後のATPの代謝についての理解は十分ではありませんでした。しかし近年、老化による生殖細胞の質の低下にともない、ATPを効率よく産生するミトコンドリアが劣化することにより不妊症が引き起こされることがわかってきました。そこで当研究室では、卵細胞についてはアフリカツメガエルを、精子についてはハツカネズミを対象として、ミトコンドリアに着目した研究から卵と精子が引き起こす複雑な生殖現象の解明を目指しています。さらに、受精後の卵の活性化や、精子の運動の活性化に重要なシグナル伝達に関連した分子の解析も行っています。
研究室WEBサイト病態薬理学研究室
講師居場 嘉教
病気の原因やその治療薬について研究するために、健康な人を病気にしたり、効果のわからない薬を人に与えたりすることはできません。それゆえ、医学を含む生命科学研究の多くは、動物実験によって成り立ってきました。 私たち人間が現在のように存在し生活できるのは、これまでに行われてきた動物実験のおかげといっても過言ではありません。しかし、適当な動物モデルがないために、病態の解明や薬効評価が進んでいない分野も多く存在しています。私たちの研究室では、マウスを用いた新規薬効評価系を構築することにより、病態の解明や薬効評価に取り組んでいます。
研究室WEBサイト生体分子機能学研究室
教授尾山 廣
タンパク質は、生命現象をつかさどる重要な生体分子です。研究室では、タンパク質がもつ特有の機能と独特な立体構造との関係を分子レベルで解析しています。最近では、熱帯植物・モリンガ樹の種子に含まれる濁水浄化タンパク質に注目しています。発展途上国では、この樹木を栽培することで循環型(サスティナブル・デヴェロップメント)の浄水システムが構築できます。一方、先進国では、遺伝子操作で大量生産させた濁水浄化タンパク質を水質改善に利用できます。この他、有用微生物のスクリーニングも行っており、キチンを分解する酵素、食肉を柔らかくする酵素、呈味性を改善する酵素などを見出し、それらの機能解析と食品への応用を進めています。
分子生態学研究室
教授見坂 武彦
微生物はあらゆる環境に存在し、さまざまな他の生物と関わりながら生きています。近くにいる生物が自身の生存に有利に働く場合もあれば、不利に働く場合もあります。また、微生物は海流や風などの自然現象、渡り鳥のような長距離を移動できる生物の活動、あるいは人間の活動によって、気づかないうちに地理的に離れた場所へ移動し、環境に適応しています。当研究室では、ミクロの視点から細菌を中心とした生物同士の分子レベルでの相互作用を、マクロの視点からは自然環境内での危害微生物の長距離移動などを研究しています。生物間相互作用にもとづいた生態や進化を理解することを目標に研究を進めています。
【主な研究テーマ】
◇渡り鳥を介した抗菌薬耐性菌の長距離拡散の解明
◇宇宙居住環境での細菌の環境適応機構の解明
◇バクテリオファージの機能を利用した消毒法の開発
生命環境科学研究室
講師長田 武
生命科学分野のうち、植物の生命現象に焦点をあてて研究しています。特に、植物と金属イオンの関係について興味をもって取り組んでいます。有害な元素は植物の生育に悪影響を及ぼす危険性があります。例えば、根の幹細胞などにストレスを与えたり、葉の光合成色素の生合成を阻害することもあります。その一方で、植物は有害元素に対して様々な応答や耐性を示すことがあります。例えば、有害元素が含まれていない方向へ根を曲げて回避しようとしたり、有害元素を吸収しないように輸送体の転写量を調節したりします。研究室では、このような植物がもつ生命現象を理解するために、分子、細胞、組織レベルのアプローチで研究を行っています。
研究室WEBサイト特殊環境微生物学研究室
教授西矢 芳昭
微生物が生産する酵素やその他のタンパク質の能力を理解し、実用性を高める研究を行っています。研究対象の酵素は医療検査などの分析分野での応用が期待され、臨床検査薬や世界初の特殊健康診断薬、バイオセンサなどで既に実用化や商品化がなされています。家をリフォームするように、酵素を用途に合わせて改良できれば便利ですが、未だ多くの課題があります。改良酵素開発のため、X線結晶構造解析による立体構造の決定、コンピュータによる改良効果の解析や反応機構のシミュレーションなども行い、研究の効率化を図っています。
また、シンプルにリアルタイム測定可能な半導体+酵素のバイオセンサを開発中です。他にも、虫好きな学生は昆虫を対象とした研究を行っており、自由な発想と自走力を大事にしています。
共生機能材料学研究室
教授松尾 康光
助教瀬溝 人生
生物の機能は35億年以上かけて、進化・改良され、創り出されてきました。
私たちは、この生物が生み出した「光合成」や「イオンの伝達」などの機能を取り出し、環境と共生できる次世代エネルギーやマテリアルを生み出す研究を実施しています。例えば、「光合成で発電する建築」もその一つです。自然に豊富で、安価で環境にやさしい生物由来の次世代エネルギーの実現をめざしています。
細胞生命生理学研究室
教授宮崎 裕明
様々な動物において、体液中のナトリウムイオン(Na+)と塩化物イオン(Cl–)濃度は驚くほど一定の範囲内に保たれています。Na+は、様々な生理的役割があることが知られていますが、Cl–の生体内における役割についてはほとんど重要視されていませんでした。
当研究室では、細胞内のCl–に着目し、生体内における新たな役割の探索を進めています。これまでに、細胞内Cl–が神経突起伸長制御、癌細胞の細胞増殖や浸潤など生体内における様々な細胞機能に関与していることを明らかにしています。
今後は、これまでに得られた知見を基にして、細胞内Cl–をターゲットとしたまったく新しい観点からの疾患に対する治療法や治療薬の開発を目指します。
細胞分子生物学研究室
教授湯浅 恵造
人体の恒常性は、細胞間・細胞内シグナル伝達ネットワークが複雑に制御されることにより維持されていますが、遺伝的・環境的な要因によってその制御が破綻すると疾病が発症します。細胞間・細胞内シグナル伝達ネットワークを解明し、疾病との関連性を理解することは、新たな創薬ターゲットの探索に繋がると考えられています。私たちの研究室では、生命の最小単位である細胞を用いて、様々な生体反応の細胞間・細胞内シグナル伝達ネットワークの解析を行い、分子レベルで生命現象の解明を行っています。
また、柑橘類搾汁残渣の有効利用を目指し、果皮抽出液の化粧品成分としての有効性を検証するとともに、果皮等に含まれる多様なフラボノイドの新たな生理活性の探索を行っています。