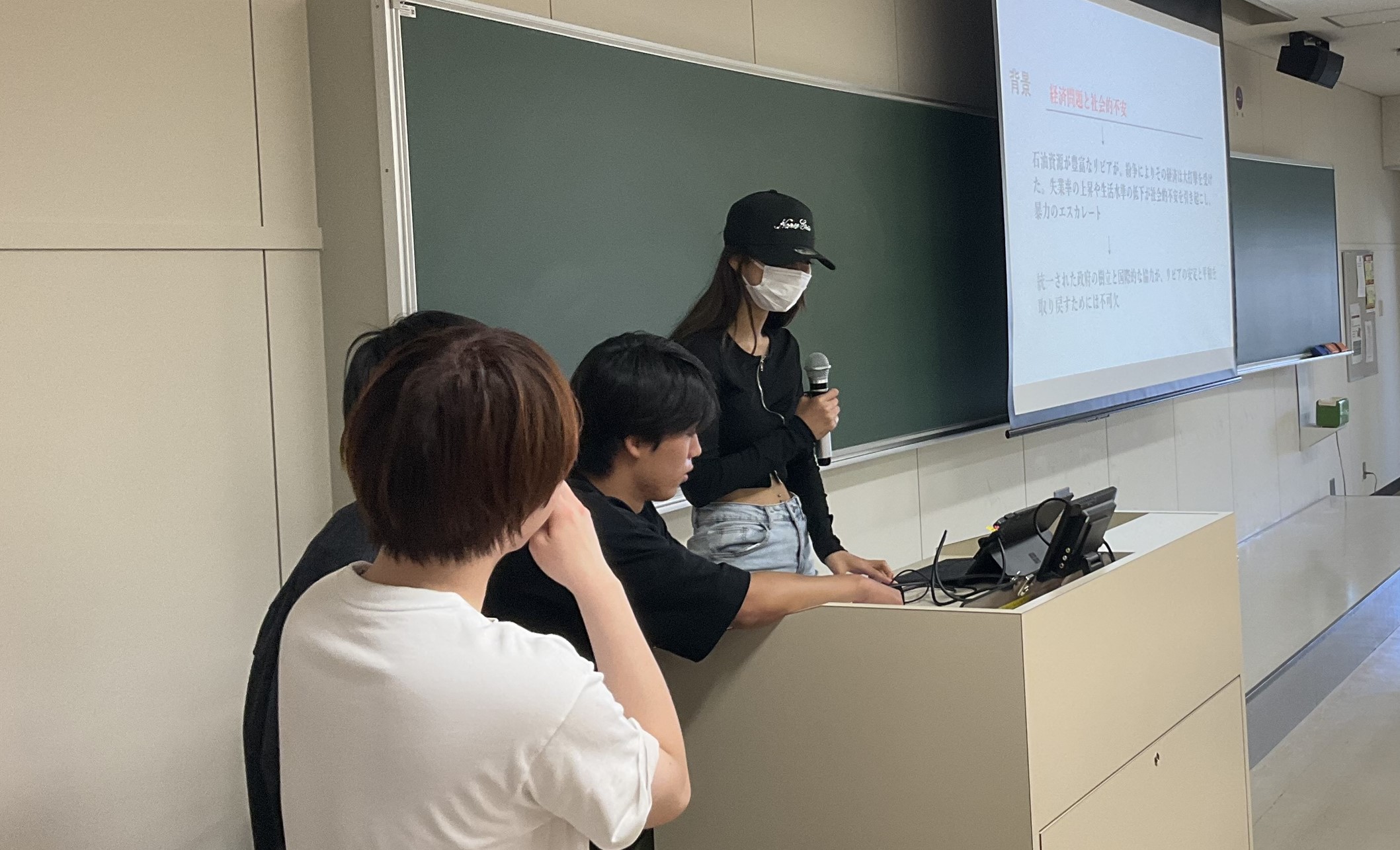国際学部
【国際学部】授業紹介No.1「国際貢献・ボランティアプロジェクト」
国際学部で2年次前期から3年次前期にかけて開講している、多彩な「プロジェクト科目」を紹介する、シリーズ投稿を開始します!
「プロジェクト科目」では講義と演習を組み合わせてインプットとアウトプットを繰り返し、学生主体で課題解決や目標達成のための計画を立案することで、課題解決力を身につけます。
今回取り上げるのは、原田豪先生が担当する「国際貢献・ボランティアプロジェクト」(3年次前期 社会協創領域)です。
授業概要(シラバスより一部引用):
グローバル化が進んだ現在、私たちの日常生活を維持するには、国際社会の安定が必要不可欠です。にもかかわらず、安定とは程遠いニュースが日々伝えられています。なぜ国際社会を安定させることは難しいのでしょうか?本授業では、基幹科目で学ぶ知識を用いながら、主に「平和」と「開発」の側面からこの問いに取り組みます。
プロジェクト科目に属するこの授業は、①自分の主張の正当性を論理的に説明し、②さらに事例を関連付けて正当性を補強していく実践などを行います。これらの実践を通じて、国際問題の複雑さに対する理解を深めるだけでなく、「考える」・「伝える」能力を磨くことがこの授業の目的となります。
授業紹介:
第7回目(5月27日)および第8回目(6月3日)の授業では、それぞれ「日本は軍事貢献をすべきか」、「国連は人道的介入を積極的に行うべきか」をテーマに、各担当グループによるプレゼンテーションとディスカッションを実施しました。各グループには、テーマに関連する事例を調査し、割り当てられた主張(テーマに対する肯定/否定)を支持する論理を事例調査に基づいて構築するという準備課題が与えられています。各主張のプレゼンテーションの後には、互いの論拠に対する質疑応答も行いました。
事例を一から調べるのには苦労していましたが、終わった後の「振り返り」では、
・高校で習っていた世界史よりもっと深い世界の歴史が分かるようになった
・普段の日本史や公民の授業では学べない国際貢献や軍事貢献についての内容などを深く知ることができた
・紛争や歴史、文化など、ニュースや新聞などでは記していないような国際情勢について知ることができた
などの感想がありました。
また、プレゼンテーションやディスカッションに対しては、
・グループでテーマについて深掘りすることができる。個人的には多少難しい内容だと感じたが、その分トーク力や相手の共有意見を考えることができると感じる。
・社会に出た際に自分の意見を伝えるときの説得力を増す練習が出来た。
などの声が寄せられています。
上記の感想のほかにも、
・大学生以上からは論理的に説明することが求められるため、社会に出てからも一生役に立つスキルがこの授業では身につくと思う。
といった授業への評価もありました。
国際問題に対する知識を深めるだけでなく、複雑な課題に取り組む際に必要となる「論理的に考え、人に伝える」経験も確かに積むことが出来たようです。
(国際学部講師 原田豪)