
好きな電気系を追究しながら、電子や情報の知見も身につきました。
理工学部 電気電子情報工学科藤川 拓馬さん
学業・研究
電気系、電子系、通信系、情報系を網羅する学科。
小学校の理科の実験で、自分で電気回路を組んだものが実際に作動して「電気実験っておもしろい!」と興味を持ったのが電気系への目覚めです。理系科目が得意だったことと、摂南大学に通っていた親戚から「授業がおもしろく、指導が手厚い」と勧められて、摂南大学の電気電子工学科に入学しました。
電気電子工学科では、電気系、電子系、通信系、情報系を幅広く学べます。具体的に言うと、スマホのような電子機器の中にある半導体、コンピュータのソフトウェア、通信システム、エネルギー制御、ロボット工学など、さまざまな分野を扱っています。広い視野を持つ「電気のわかる情報系技術者、情報のわかる電気系技術者」をめざせる学科です。
1年生では各分野の基礎を学びます。実験や演習では10人程度の学生に対して1人の担当教授が付いてくれる少人数制でした。私自身は自分でできるところまでやってみるタイプですが、実験が多くて先生や先輩と話せる機会があったので、いざ困った時には相談しやすかったです。
自分の興味や得意、エンジニアとしての将来像を考えながら、2年生の後期に「電気系コース」「情報系コース」「電気・通信システム総合コース」のどれかに進みます。私は電気系を専門的に学べて、卒業時に日本技術者教育認定機構(JABEE)の技術者認定資格が得られる総合コースに進みました。

専門知識と技術、そして「伝える力」も身につけた技術者に。
特に印象に残っている授業は2年次の「電気情報創生演習」です。2人1組でのグループワークで、プログラミングを作成してLEDを点灯させて、絵や文字を描き出すバーサライターという装置を作る演習です。規定のパソコンとバーサライターという2点だけが決められていますが、設計やデザインやどんな形にするかはすべて自由で「なんでもアリ」だからこそ難しかったです。私は相方が作成したプログラミングを実現させる電気回路を組みました。
扇風機を素材に、円の上半分を太陽、下半分を暗闇に見立てて、オレンジ色の光が動いて回転していく装置を作りました。光らせるタイミングがズレたり、扇風機の羽部分にいろいろ付けたことで重心が崩れてしまったり、高速で回転しすぎたりもして、試行錯誤しながらの制作でした。電気回路をいかに小さく収めるにはどうしたらいいかを考え、ギリギリまで詰めて細かく組み、実際に成功した時のやりがいは大きかったです。最後にみんなの前でプレゼンテーションを行い、人気投票で2番か3番目になることができました。他の組の装置やプレゼンもおもしろく、とても刺激的な授業でした。この演習を通じて、工業的なデザイン力や知識を応用する力だけでなく、人と協働したり人に伝えたりするコミュニケーション能力も鍛えられたと思います。
課外活動では大学に入ってからアーチェリーを始め、体育会アーチェリー部みんなで頑張った結果、男女ともに関西学生1部リーグ昇格を果たせました。部長を務める中で、自分で決断してみんなを説得するだけでなく、まわりに相談しながら物事を進めることができるようにもなりました。部活でも学科のプレゼンでも、自分の考えをしっかり説明することで説得力が増すことを実感しました。
就職活動はスムーズに進み、志望していた電力インフラ企業に内定しました。発電所のシステム開発などを行う予定なので、学んだことを生かせると思います。向上心を持って学び続け、卒業までには電気主任技術者試験の資格にもチャレンジしようと思っています。
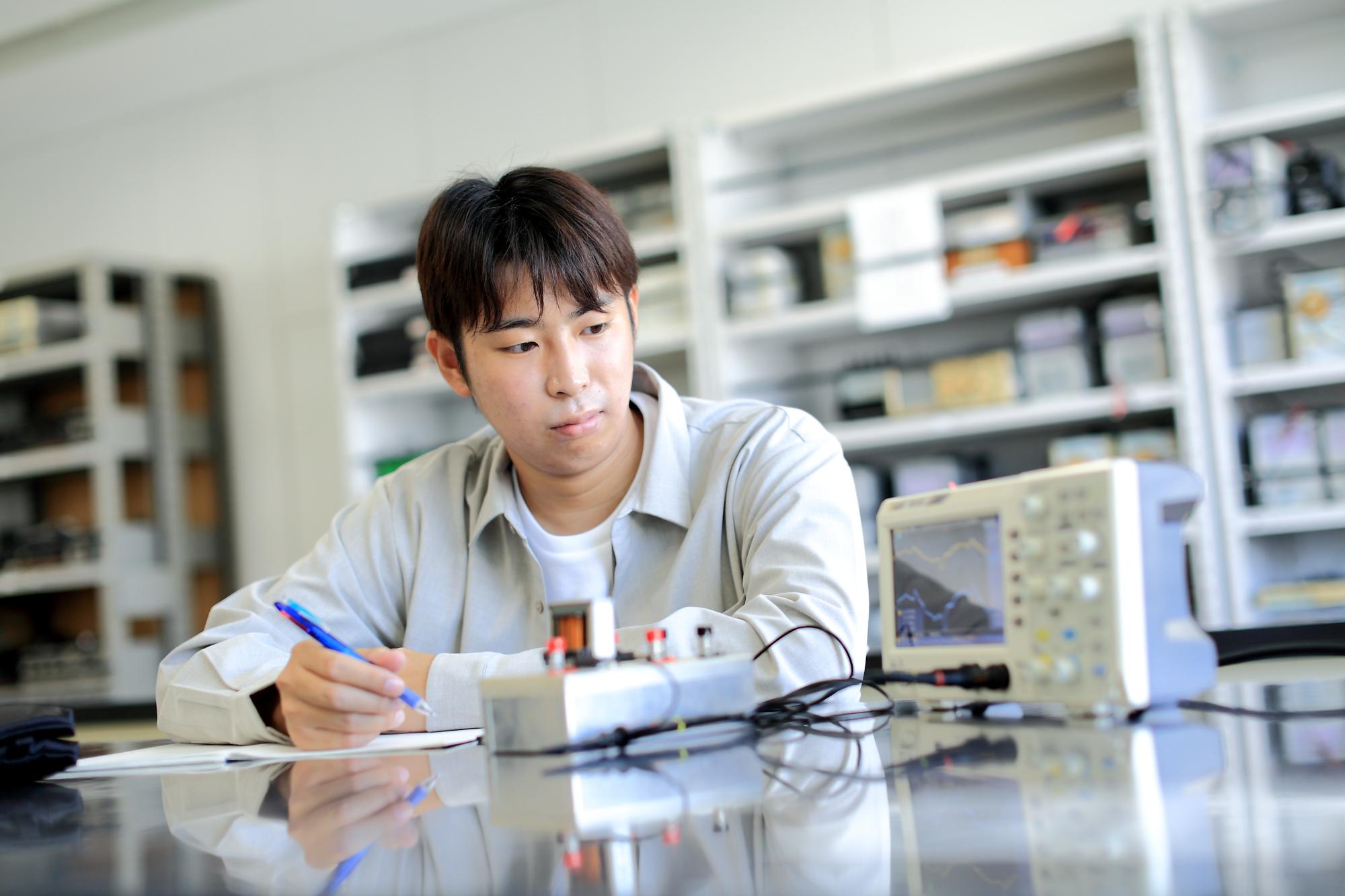
(掲載内容は2024年9月取材時点のものです)
わたし×摂南一覧へ戻る

