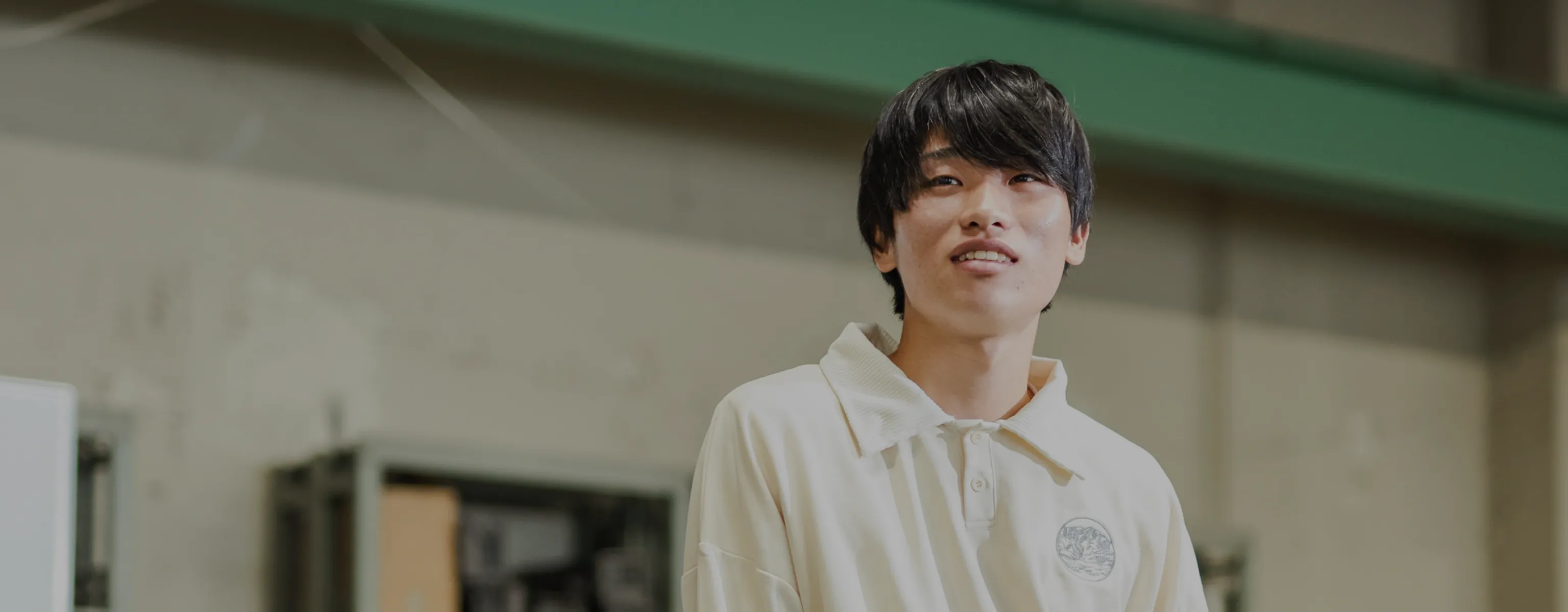屋外でのフィールドワークや、実験・検証を重ね、
都市と自然環境、人の暮らしのバランスを考える。
都市環境を切り口に、さまざまなアプローチで研究が進められています。この分野は、フィールドワークを取り入れた調査・分析が不可欠だけに、各研究室とも戸外へ出向くアクティブな研究活動が繰り広げられています。摂南大学は大都市・大阪市に近接するとともに周辺には淀川の水と緑があり、都市の問題を多角的にフィールド調査するうえで、実に恵まれた立地条件にあります。
生態環境学研究室
教授石田裕子
生態環境学研究室では、人と自然が共生できる都市環境づくりをテーマに研究を進めています。
21世紀の現代は、気候変動による洪水災害の増加や生物多様性の劣化が大きな社会問題となっています。本研究室では、淀川流域を中心に、遊水地等のグリーンインフラを用いた新な流域治水手法の確立、生物多様性保全のための河川内生息場条件の解明、水生生物のための新たな生息場の創出など、持続可能な流域環境の維持に関する研究を行っています。
また、行政・地域・市民団体等と協働して、人と生きものにとって利用しやすい河川・水辺づくりも行っています。様々な水辺に親しむ活動を通じて、流域住民・次世代を担う子どもたちへの普及・啓発活動を実施しています。
環境地盤研究室
教授伊藤 譲
土壌は生物の命の基盤である。ところが、汚染土壌の問題は、最終処分場等で蓄積される汚染土壌、自然由来の重金属汚染や、今後老朽化した原子力発電所から発生する汚染土壌など潜在的に深刻さを深めている。このような汚染土壌の課題は、特に洗浄が困難である粘土など細粒分の洗浄し難さにある。一方細粒分が凍結すると土粒子表面で洗浄液が濃縮され、水流が発生することが解っている。本研究室では、このような土壌の凍結融解現象を利用した昼夜や季節間の寒暖差等を活用できるコストフリーの技術の開発を目指している。
研究室WEBサイト都市・地域計画研究室
講師久保田 誠也
本研究室では、ソフトの面から都市や地域をより良くすることを目指しています。本研究室に配属された4年生や大学院生は、ドライブレコーダーや市販のカメラで撮影された動画像データを道路空間の基盤となる情報の整備に活用するための研究や、地方部の公共交通に関する課題解決を目的とした研究を中心に研究に取り組んでいますが、研究したいテーマがあれば可能な限り尊重するようにしています。
研究では、Pythonなどを使ったプログラミングやGISソフトを使った分析などを行っていますので、プログラミングやパソコンを触るのが好きな人や、AIや情報系のスキルを身に付けたい人にも是非興味を持っていただければと思います。
地域環境計画研究室
教授熊谷 樹一郎
地域環境計画研究室では、少子化と高齢化のなかで人口の減少する都市の状態を広い視野から調査し、今後のまちづくりに向けた必要な情報を提供することを試みています。具体的には、地理情報システムを活用し、都市内の人口がどのように分布しているのか、極端な偏りはないか、といった観点から分析を行ったり、ドローンを活用した撮影画像をAIで分類し、空き家調査をサポートする方法の検討を行ったりしています。いずれも人口減少でまちが荒廃する可能性のある箇所を広い範囲から調査・分析する取り組みです。また、まちづくりの現場にも関わる機会が多く、協議会などのワークショップに参加し、地域に関係する方々と意見を交わしながらまちのあるべき姿を一緒に議論しています。
研究室WEBサイト 研究室WEBサイト建設材料研究室
教授熊野 知司
持続可能な社会を構築する上では、社会基盤を形づくる建設材料においてもさまざまな変革が必要になります。例えば、建設材料として代表的なコンクリートの中で骨材(石や砂)を接着する役割を果たすセメントを製造する際には温室効果ガスであるCO2を排出してしまいます。このセメントの使用量を減らし、かわりに鉄鋼製造の際の廃棄物である高炉スラグや石炭火力発電の廃棄物であるフライアッシュを添加するとセメントのアルカリを刺激材として強固に硬化する性質があります。すなわち、産業全体でCO2の排出量を減らすことにつながります。建設材料研究室では、研究テーマのひとつとして、高炉スラグやフライアッシュを大量に添加したコンクリートの性質を実験によって明らかにすることに取り組んでいます。
橋梁・鋼構造研究室
准教授田井 政行
日本の社会インフラの多くは、高度経済成長期に建設され、供用から既に50-60年が経過しています。これらの社会インフラを安全・安心に使用するためには適切な維持管理を行うことが重要です。鋼構造学・橋梁研究室では、橋梁をはじめとする社会インフラの耐荷力・耐久性を実験的及び解析的アプローチにより評価を行っています。また、維持管理に不可欠な点検・診断の高度化・効率化を目的に、高精度な3次元モデルを活用した点検・診断支援システムの構築を行っています。実際に生じている損傷を学びながらその影響を評価することで、高い専門性を有する技術者の育成を行うとともに、重要な社会インフラの安全性確保に大きく貢献することを目指しています。
地盤工学研究室
准教授寺本 俊太郎
日本に住む私たちは、地震、台風、火山噴火、ゲリラ豪雨などなど、自然災害と隣合わせで生活しています。そうした自然災害から人々の豊かな暮らしを守るには、生活を支える社会基盤である「土木構造物」を頑丈に造り、維持管理していくことがとても重要となります。そのため地盤工学研究室では、「土木構造物」とそれを支える「土」について、日々研究を行っています。
【研究例】
- 構造物を支える基礎を耐震補強するために、新たに杭基礎を増築する「増し杭工法」について、新たな合理的な工法を提案しています。
- 土砂災害を防ぐための斜面補強工法について、企業と共同して研究しています。
- 杭基礎と土の間の動きを明確化するため、世界最先端の可視化技術を用いた実験を行っています。
トンネル・構造工学研究室
准教授林 久資
トンネル・構造工学研究室では、トンネルの建設・維持管理・安全に寄与するために日々研究を行っています。日本列島の地形は起伏に富んでおり、山地の面積は国土の75%を占めていることから、これまでに多くのトンネルが建設されてきました。 日本は多様な地質が複雑に分布しているため、安全にトンネルを建設するために掘削挙動予測が必要となります。そこで、数値解析や載荷実験によるトンネル掘削シミュレーションや、LiDARセンサなどを用いた肌落ち災害低減システムの開発を行っています。 また、近年は過去に建設されたトンネルが高齢化しており、そのようなトンネルは第三者被害に繋がる可能性があり問題視されています。土木学会が公開している「インフラ健康診断書」の作成支援や、AI技術を活用した冬期トンネルにおける維持管理業務低減に関する研究も行っています。
環境衛生工学研究室
学科長・教授水野 忠雄
上下水道のシステムとしての在り方や処理技術の開発に関する研究を行っています。日本の水道水は、世界では珍しく飲むことが可能です。飲用以外でも、洗面、トイレ、お風呂、炊事と、みなさんも必ず毎日使用していることと思います。また、いったん使用し汚れた水は、そのままでは、環境に戻すことはできません。飲用可能な水を作ったり、使用し汚れた水を環境に放流してもよいレベルにきれいにするためのシステムや技術についての研究を行っています。あまりにも当たり前のように水が使用できる現代においては、目立たない縁の下の力持ちである技術やシステム。物理・化学・生物・数学などの知識を活かして、実験を行うとともに、コンピューターを用いたシミュレーションによって最適な設計や運転条件を明らかにする研究を行っています。