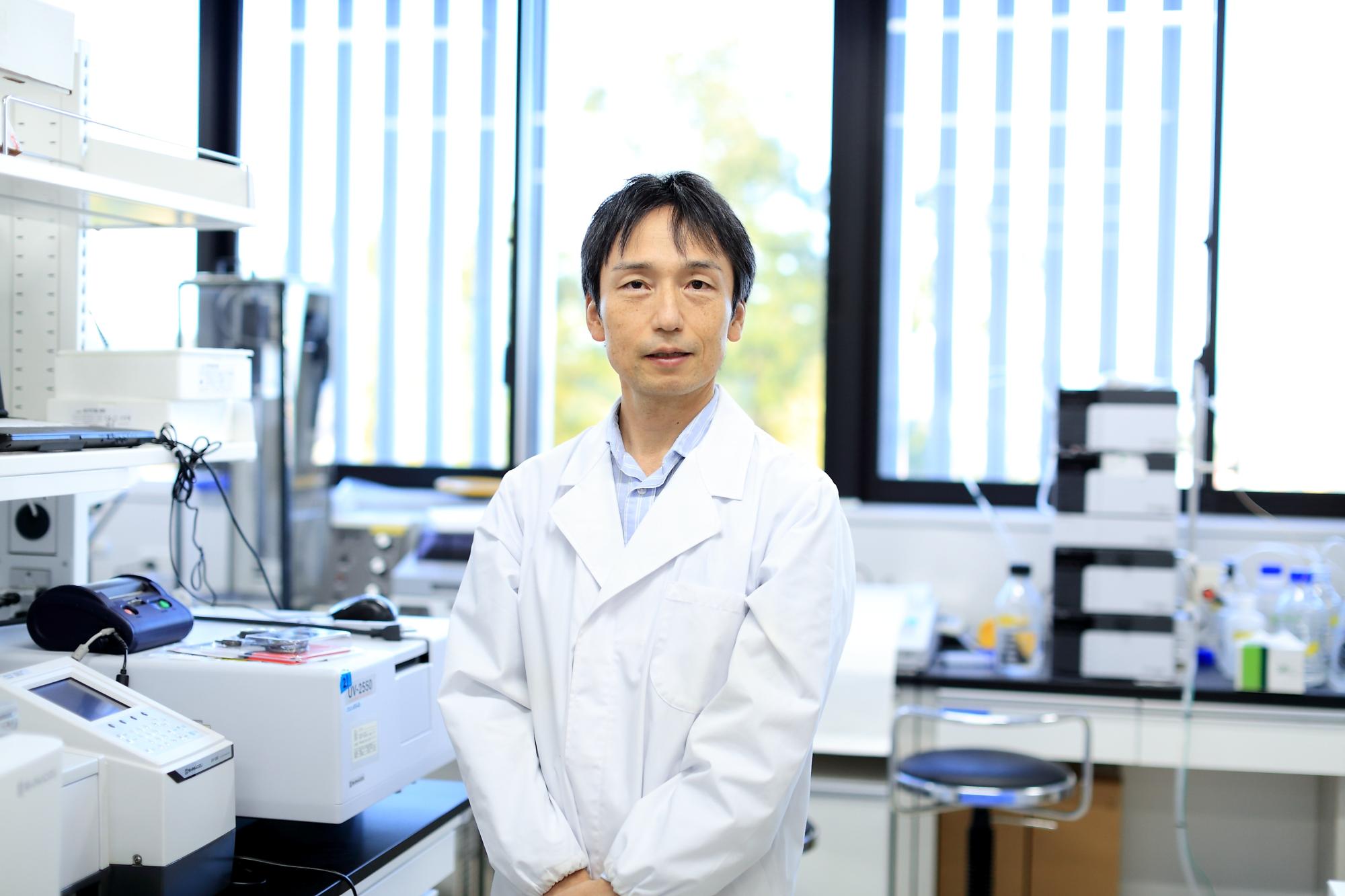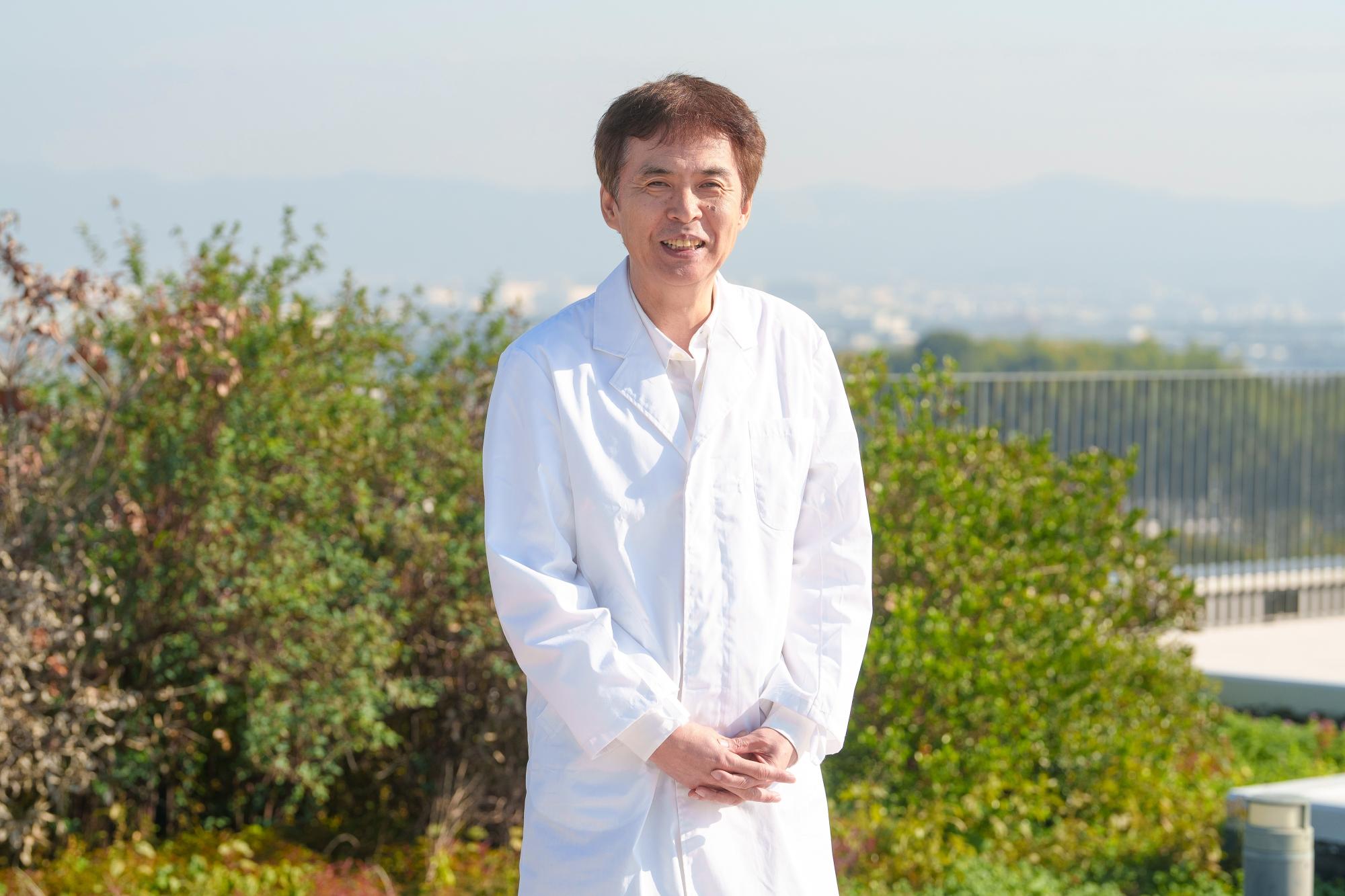慢性腎臓病患者も食べられる低カリウムメロンを実現。
私が現在の研究を始めたのは、同僚の研究者から「慢性腎臓病の祖父に、好物のメロンを食べさせたい」と相談されたことがきっかけです。慢性腎臓病患者は尿が充分に出ないため、カリウムが細胞や血液に溜まりやすく、週に3回の人工透析を行いながら日々厳しい食事摂取制限を受けています。そこで私は、「養液栽培によるカリウム制御野菜に関する研究」を行い、低カリウムメロンの開発に取り組んでいます。養液栽培とは、土を使わずに、肥料を水に溶かした培養液によって作物を育てる栽培法です。当初は、カリウム肥料を定植(植え替え)初めから制限してみましたが、葉や茎に十分なカリウムが供給されずに果実が十分肥大しなかったり、果実のカリウム含量も不安定でした。そこで、花が咲くまではしっかりとカリウム肥料を与えて、葉や茎を充実させ、開花から収穫までの8週間、カリウムを完全にカットする方法を試みました。そうすると、メロンは根からのカリウム肥料がカットされた後、葉や茎から必要最低限のカリウムを果実に送り、それが安定した低カリウム化につながりました。
こうして実現した低カリウムメロンは、試食会でも好評でした。また、テレビ番組の「世界一受けたい授業」でも試食していただきましたが、出演者の方に「これは普通のメロンと変わらないおいしいメロンだ」と言っていただけました。今後は、より安定的な収穫を実現できるように取り組んでいきます。もともとメロンのネットは、いわばひび割れによる「かさぶた」のようなものなのですが、水や肥料が取りやすい養液栽培では、収穫までに数%の果実が完全に割れてしまうのです。そのあたりを改善していきたいですね。メロン以外にサツマイモ(焼き芋や干し芋)やイチゴの低カリウム化の研究も進めています。
また、低カリウムとは逆の高カリウムサツマイモの研究も進めています。メロンは高カリウムだと苦くなるのですが、サツマイモの場合、さほど味は変わりません。カリウムを充分摂取しないといけない高血圧症患者や、筋肉のパフォーマンス低下を抑制するのにカリウムが必要なアスリートの方に、喜んでいただけるものができたらと考えています。

JAXAとともに、火星到達を見据えた月面農場の可能性を模索。
イチゴやレタスを対象とした「園芸植物の自家中毒に関する研究」にも取り組んでいます。植物は、自らの体を守るために根からさまざまな化学物質を排出しています。たとえばセイタカアワダチソウは、他の植物が周囲に生えないように根から化学物質を出すのですが、結局はその化学物質により自家中毒を起こしてしまいます。養液栽培も培養液を循環すると、自身から排出された化学物質で生育を抑制してしまうケースがあるのです。そこで、抑制物質を除去するアプローチとして活性炭や微生物を試しましたがさまざまな課題が残り、最終的には交流型電気分解にたどり着きました。こちらも今後実用化に向けて研究を進めていければと考えています。
養液栽培などの園芸技術は、これまでにない野菜を開発できるだけでなく、月面農場などの新しい可能性にもつながっています。人類が今後火星に到達するためには、中継地点としての月面基地の発展が必須条件であり、食料確保のための農場も必要となります。そこで、宇宙飛行士の尿を再生利用した養液栽培を見据えて、まずは人工尿を利用した養液栽培の研究にJAXAと共同で2年ほど取り組みました。近い内に2本目の論文を書く予定ですが、自家中毒の研究が生きてくると思います。学生の皆さんにも、ぜひ「植物にアプローチして、植物の能力を引き出す」という園芸科学の魅力を感じてもらえたらと考えています。

(取材内容は2024年11月時点のものです)
摂南タイムズ一覧へ戻るこの記事に関連する学部をチェック

学科紹介
農学部