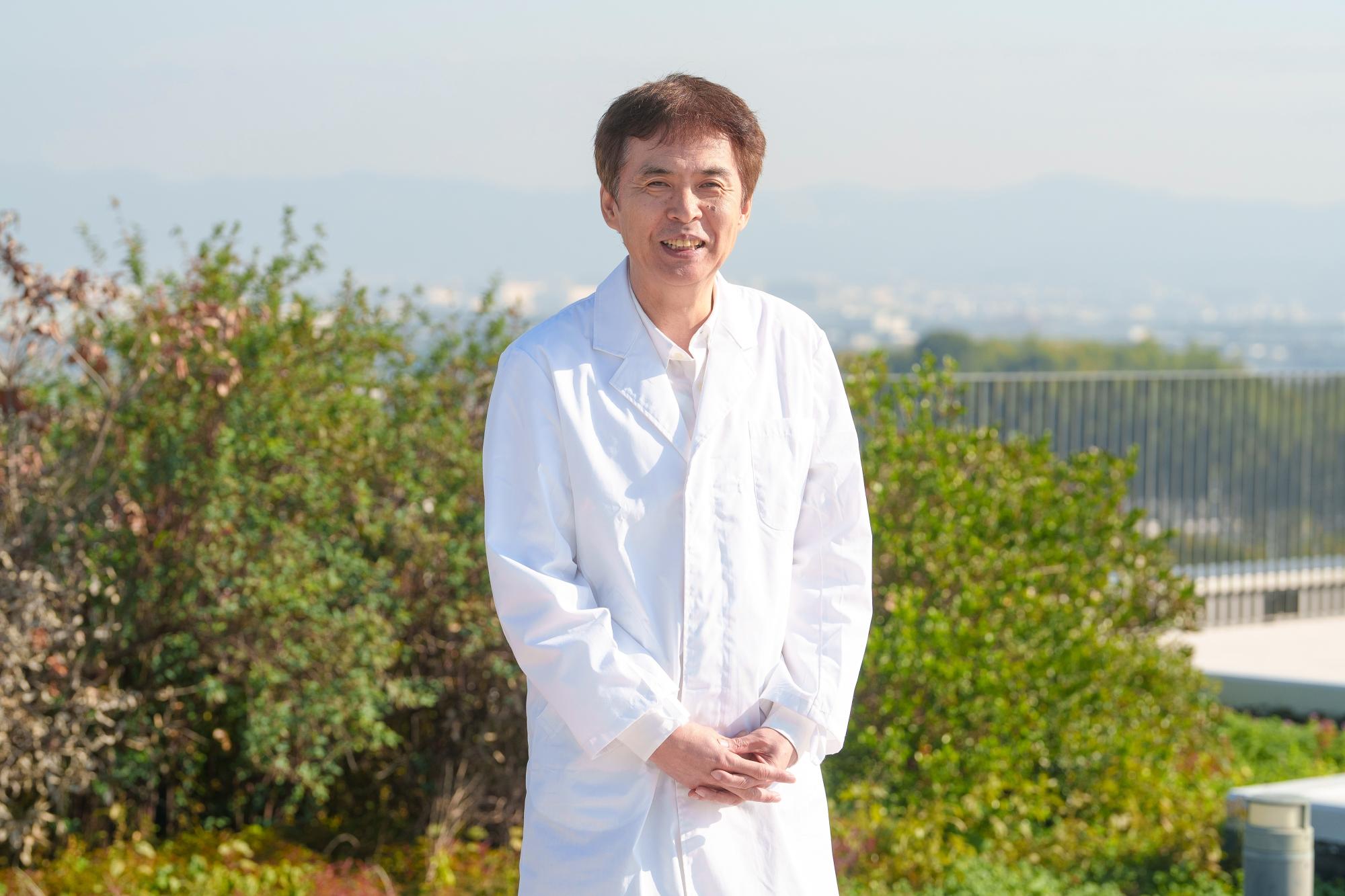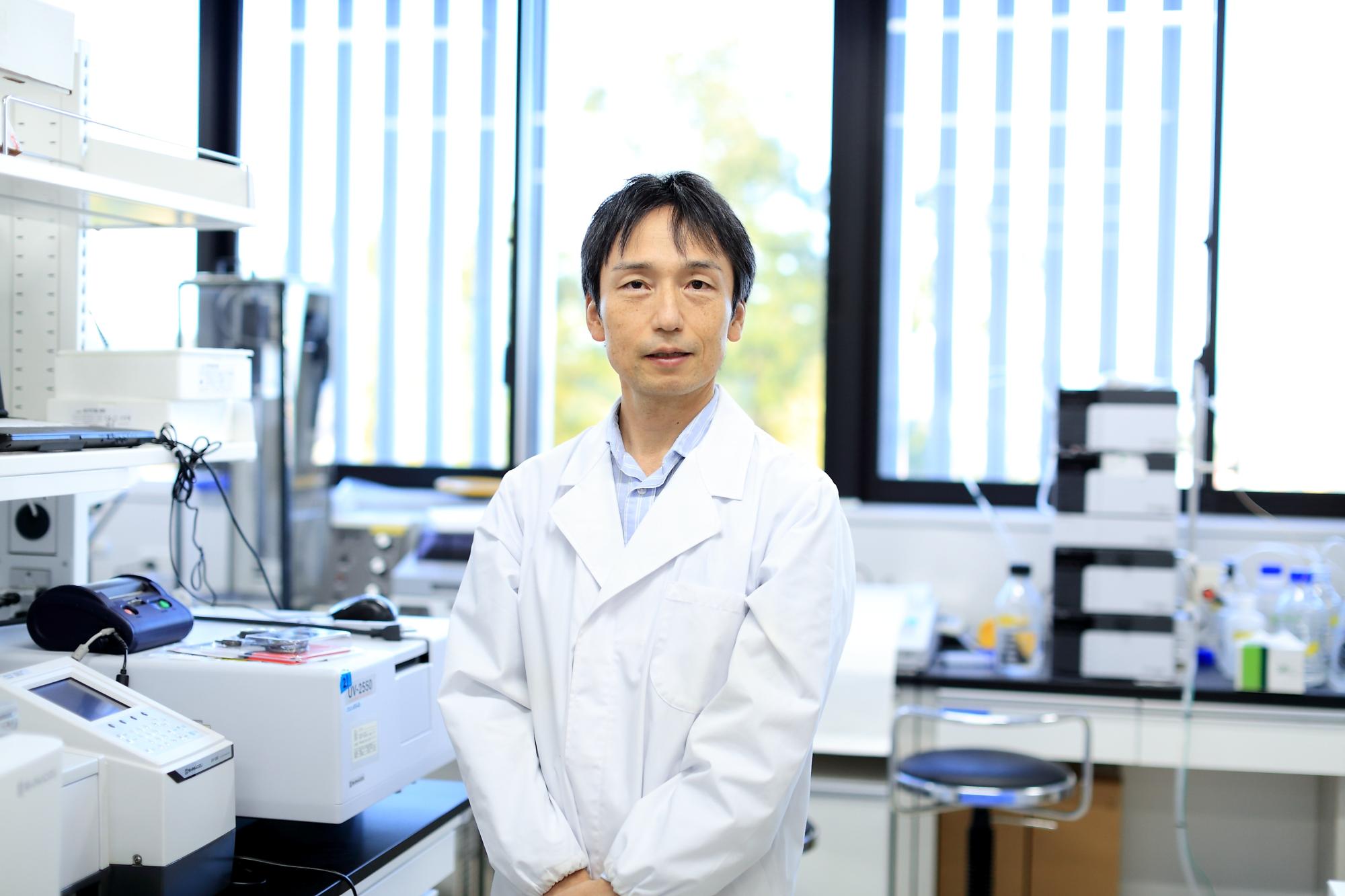ユネスコの無形文化遺産登録で注目を集める麹づくりの技術。
私は現在、さまざまな食品素材を麹化する研究を行っています。麹(こうじ)とは、米や麦、豆などに麹菌というカビの一種をつけて培養したものです。日本古来より日本酒や味噌、醤油などの製造に用いられてきた伝統技術で、2024年12月には麹づくりを中核技術とする日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されることが決定し、あらためて注目を集めています。
私は、この伝統技術を生かして、おいしさや機能性など、従来にはなかった新たな価値を食品素材に与えようと取り組んでいます。麹化の過程で原材料のタンパク質をアミノ酸に分解し、甘みや旨味を引き出すことで新たな味わいが生まれる可能性もあります。また、色味も視覚的なおいしさの要素のひとつです。たとえば緑色のえんどう豆を麹化することで、緑色の色素成分が移った麹を用いて緑色の発酵食品を作ることもできるかもしれません。健康面でも抗酸化機能の付与などが考えられます。材料や作り方でもいろいろ変わってくるので、今は網羅的に探索している段階です。

たとえばオレンジ色の人参麹甘酒など、食品に新たな価値を。
食品素材を麹化するためには、麹菌の栄養となるタンパク質や炭水化物がある程度必要となります。また、水分量が多い野菜も、そのままでは麹菌の繁殖には適しません。現在、私が注目しているのは、豆類の麹化です。豆類では、醤油や味噌のもとになる大豆が有名ですが、その他にもえんどう豆やいんげん豆、そら豆など、非常にたくさんの種類があります。「血圧を抑える」など、豆類がもともと持つ機能性をそのまま、あるいは強化して発酵食品に移せないかと考えています。
これまでの麹化の中心だった米や麦と比較すると、豆類は固い種皮を持っているのが特長です。そのままでは麹菌が繁殖することができないので、たとえば小豆なら種皮ごと粉砕してしまうという手法が従来から用いられてきました。私は、それとはまた異なるアプローチとして、豆を粉砕せずに表面に処理を行うことで麹菌の通り道をつくってやる手法を試みています。麹菌がどのようなルートを通るのか、顕微鏡で確認しながら、麹化の条件を細かく設定しています。
その他、人参などの野菜類、アーモンドなどの種実類の麹化にも取り組んでいます。炭水化物が少なかったり、野菜の水分を処理する必要があったり、いくつものハードルがありますが、いろいろ試していきたいですね。たとえば人参の麹で、オレンジ色の甘酒や醤油もできるかもしれませんね。
麹ではありませんが、黒酢とにんにくを組み合わせることで、食品に新たな価値が生まれた例もあります。この研究でも、麹を使った新しいアプローチを学生たちとともに提案できたらと考えています。

(取材内容は2024年12月時点のものです)
摂南タイムズ一覧へ戻るこの記事に関連する学部をチェック

学科紹介
農学部