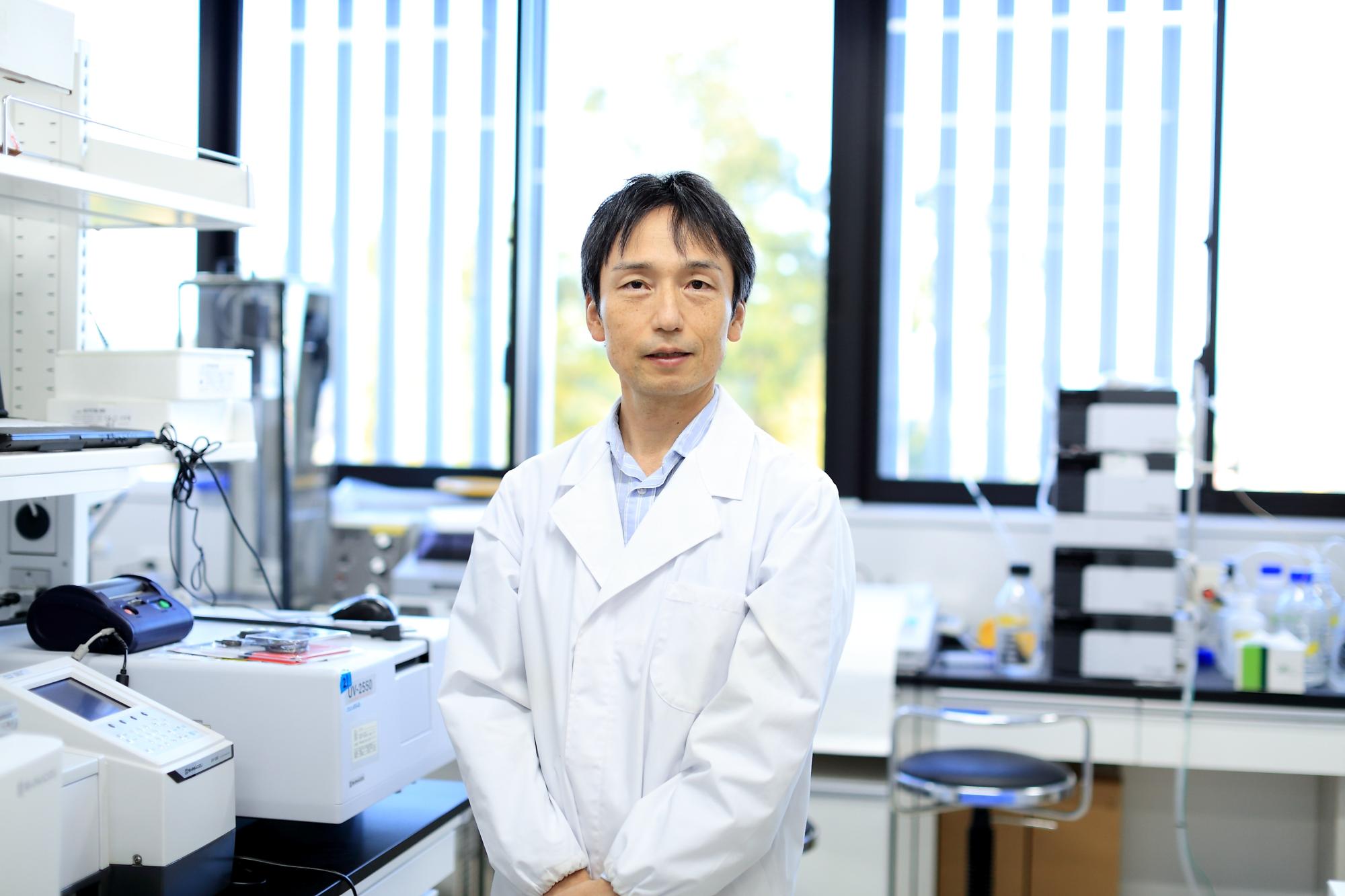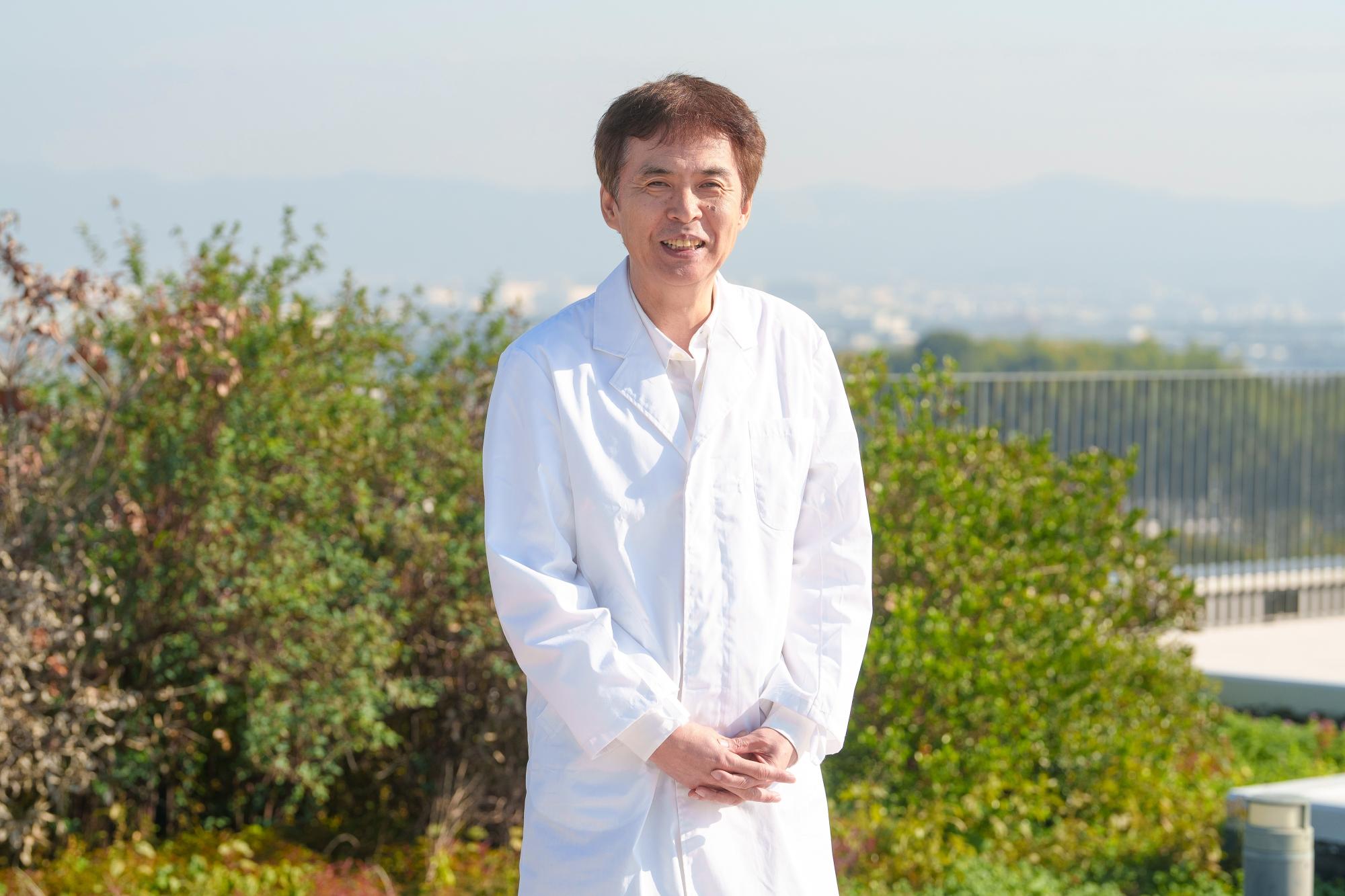琵琶湖と切り離されている川から、「琵琶湖型」遺伝子を持つイワナが。
夏になると、毎年のように「記録的な猛暑」という言葉が聞こえてきます。経験したことがないような暑さに見舞われる日本列島ですが、山の奥には冷たく澄んだ水が流れる沢があり、私たちの身近な川の源流となっています。そこには、冷涼な水を好むサケの仲間、イワナが棲んでいます。
北国の魚という印象が強いイワナですが、近畿・中部地方の山間部でも生き続けています。氷期と間氷期を繰り返す気候変動の中で、北方から徐々に分布を拡大してきたと考えられます。現在は、地域ごとに遺伝的・形態的に異なるいくつかのグループが知られていますが、それぞれのDNAを調べることで、そのイワナがいつどこからやってきたのか、さらには河川や山々の地形変化の歴史まで探ることができるかもしれません。
そこで私たち研究チームは、中部地方と琵琶湖周辺の30河川を対象に、源流域32地点で採取したイワナ計332匹の遺伝情報を解析し、「日本海型」「太平洋型」「琵琶湖型」の3グループに分類しました。驚いたのは、日本海に流れ込む福井県の川(以降、A川)の源流域で、本来いるはずのない「琵琶湖型」が見つかったことです。A川は、現在は琵琶湖につながっていません。一方、隣接する川(以降、B川)は琵琶湖に流れ込んでいます。かつてB川の上流であった川の流れが、地形変化の影響で隣のA川に奪われる「河川争奪」という現象があったと考えられており、イワナの遺伝子型はその過程とぴったり一致していました。B川の上流にいた「琵琶湖型」のイワナは、「河川争奪」によってA川の上流となった今もそこに生息しているのでしょう。このように、現在の水系とは矛盾するイワナの個体群が棲む川は、他の調査地でも確認されました。私たちにとって未知なる河川の流路変更があったのかもしれません。DNAに秘められた生物の歴史、変遷に触れ、現在の地図が形成された歴史を考察する中で、自然の壮大さと大きな時の流れを肌身で感じました。

魚たちが生きていた証を、論文という形で未来に残したい。
私は生来の山好きで、20年以上にわたって河川源流部の美しい水に棲む魚たちに惹かれて、奥山の渓谷を巡って渓流釣りを楽しんできました。今回の調査でも、イワナのサンプルを採取する際に、人が立ち入りにくい場所へと足を運びました。釣り人のために放流された、研究サンプルとして適さないイワナを誤って採取してしまわないようにするためです。そこでは深い山々と水、そしてそこに棲む生き物の美しさに出会えた一方で、豪雨災害などによって荒廃した風景も目にしました。また、工事などの人為的な活動の影響も見受けられ、河川の環境はいつまでもそのままであり続けることが難しいことをあらためて実感しました。
私は、遺伝子を調べることで、魚たちが歩んできた歴史を調べ、たしかにそこに生きていた証拠を論文という形で未来へと残していきたいと考えています。現在の研究に取り組む以前は、鉄などの必須元素の利用をはじめとする生化学系の研究に長年取り組んできたので、その視点を生態学にも取り入れていければと考えています。川に落ちた落ち葉の炭素や生き物の鉄分などが、自然の中でどのように循環してきているかといったことも追求していきたいですね。
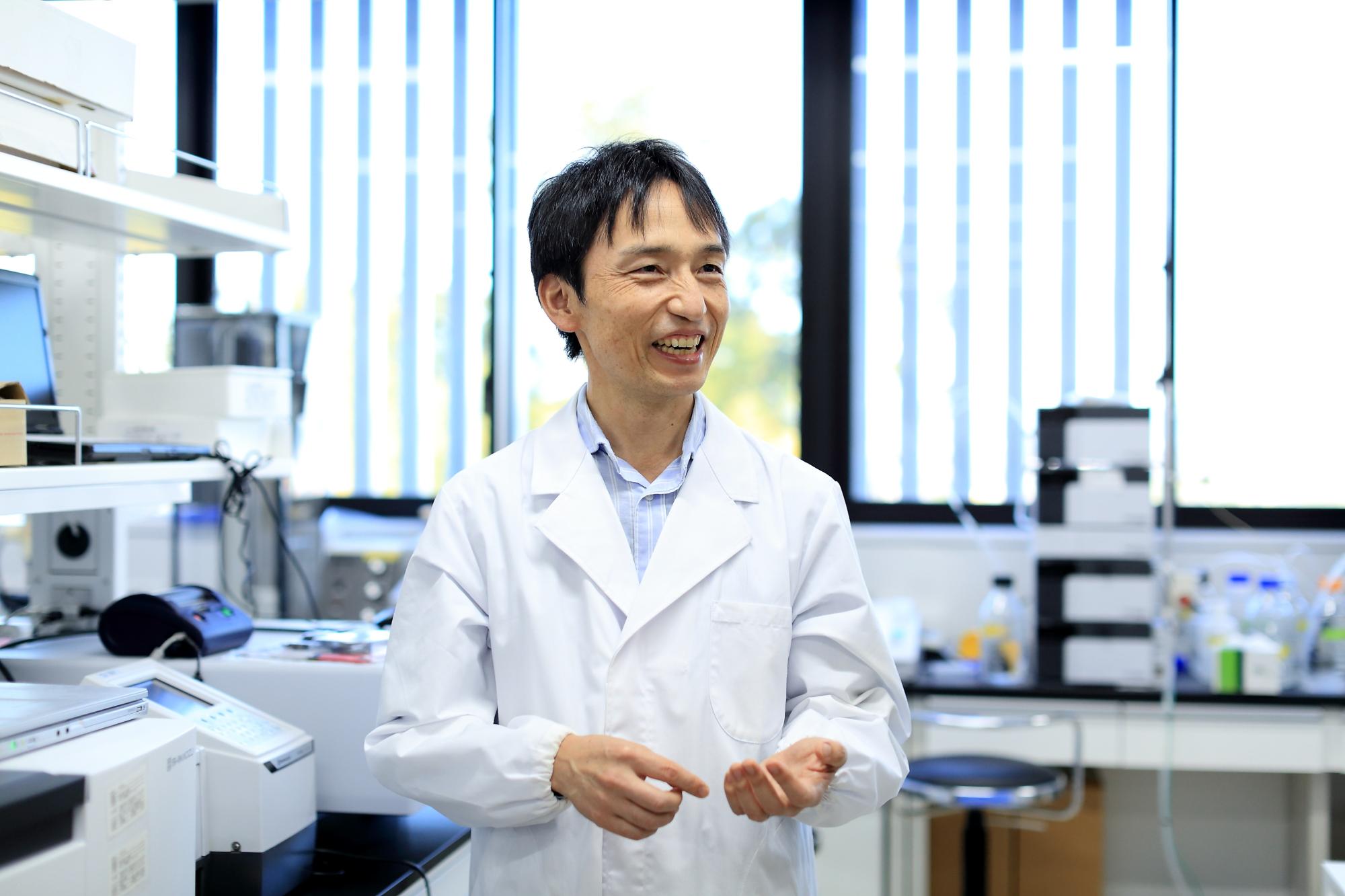
(取材内容は2024年11月時点のものです)
摂南タイムズ一覧へ戻るこの記事に関連する学部をチェック

学科紹介
農学部