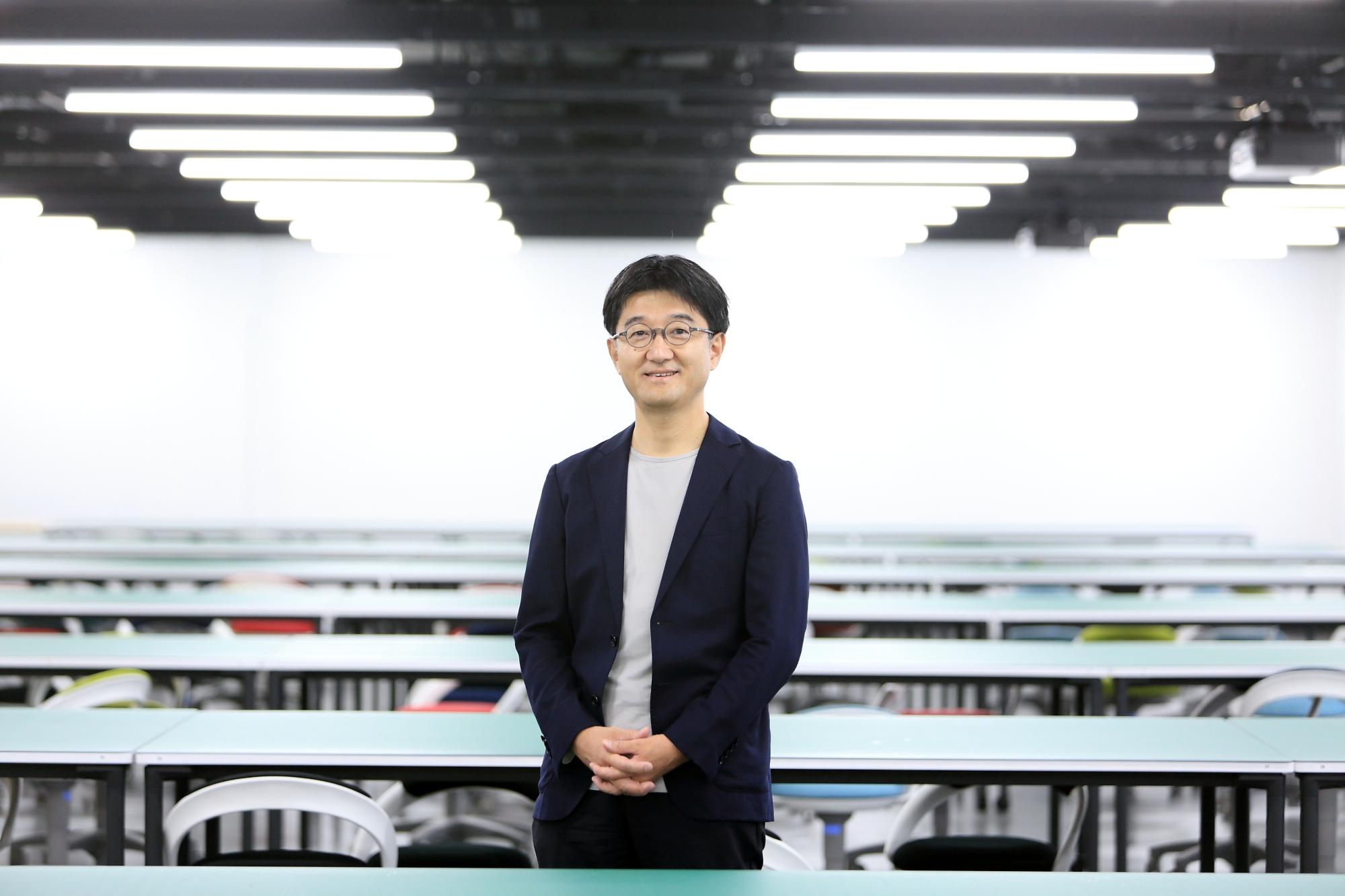「デマンドレスポンス」で、建物側の消費電力をコントロール。
私は、「建築が地球温暖化防止にどう貢献できるか」を主な研究テーマに、CO2排出量の削減をめざす活動を行っています。地球温暖化防止にはCO2排出量の削減が欠かせませんが、日本ではそのうちの約4割が建築に関連しています。たとえば、日常的に建物で使用されるエアコンや照明などの設備の電力消費はもちろん、建物の新築や改修などで用いられる建材の製造過程、工事現場における建設機械等の使用においてもCO2は排出されます。
住宅エアコンのコントロールによって、CO2を排出しない再生可能エネルギー拡大の手助けを行うというのが、私の代表的な研究のひとつです。これまでの電力供給は、いわば建物側の需要に合わせて、電力会社が発電する量をコントロールしていました。建物が多くの電力を必要としているとき、火力発電であれば燃料を増やして発電量を調整できますが、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの発電は、まさに自然任せ。日没後や曇り空では、太陽光で発電することはできません。今後、再生可能エネルギーが主な発電方法となったときに、送電する発電所側と受電する建物側の電力量が合わないと、停電することもあり得ます。
となると、再生可能エネルギーの発電量に合わせて、建物側が電力消費量をコントロールすることが重要になってくるんです。その解決手段のひとつが、「デマンドレスポンス」です。これは、発電量が不足する時には建物側が電力消費量をセーブしたり、逆に発電量が余る時は積極的に電気を使ったりというアプローチです。もちろん酷暑の中、発電量が不足するからといってエアコンが勝手に長時間オフになるようでは困ります。設定温度を調整するのか、短時間だけオフにするのか、あくまでも人の許容値の中で考えていく。躯体の熱容量が大きいRC造ならゆるやかに室温が変化するなど、建物の造りでも変わってきます。研究では、このように快適性を維持しながら、住宅のエアコンでどこまで対応できるかを探っています。

建物のCO2排出量を、時間単位で見極めていく。
また、建物のCO2排出量を時刻単位で評価することも行っています。日本の再生可能エネルギーによる発電量の割合は、2023年度実績で約23%となっています。ただ、再生可能エネルギーの発電量は自然任せで増減するため、日没後や曇り空など、CO2を排出する火力発電などの割合が増える時間帯も出てきます。現在、建物のCO2排出量を算定する際には、この変動を無視し年平均で評価するのが一般的ですが、例えば太陽光発電ができない夜間に電力を多く消費する建物では、年間のCO2排出量が実際よりも少なめに評価されていることになります。時刻単位での評価を行うことによって、より実態に近い評価をめざすとともに、再生可能エネルギーの発電量が多い時間帯に建物側のエネルギー消費を誘導したいと考えています。結果的に、それはさらなる再生可能エネルギー拡大の後押しにもつながるはずです。
「CO2削減」や「人口縮小」というと、どうしても右肩下がりのイメージがつきまといます。しかし、地球環境に負荷を与えず、自立的で持続可能な都市や建築の姿を描くことは、人々にこの上ない安心感や希望感をもたらし、その後の安定した人口形成の社会基盤となるはずです。持続可能な建築・都市の実現をめざし、「建築環境・都市環境・建築設備」と「エネルギー」の関係を追及することで、これに少しでも貢献できたらと考えています。

(取材内容は2024年9月時点のものです)
摂南タイムズ一覧へ戻るこの記事に関連する学部をチェック

学科紹介
理工学部