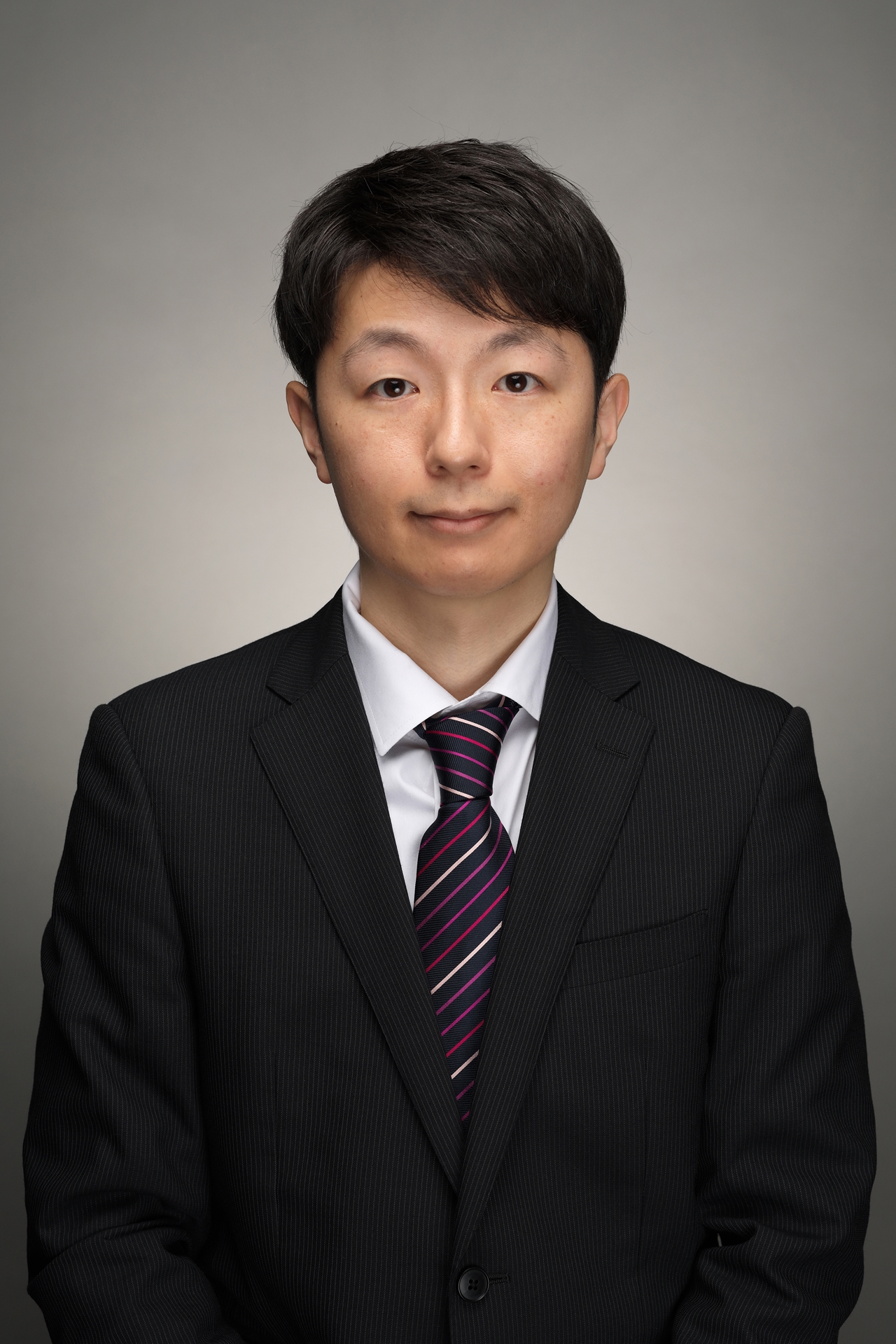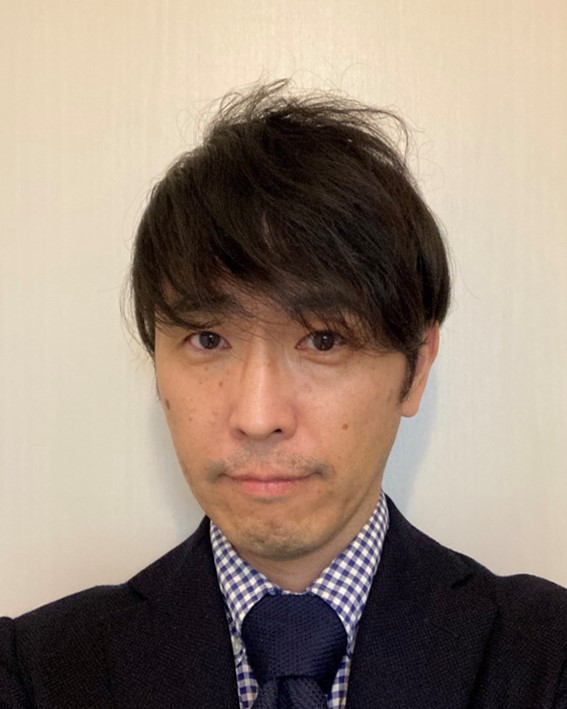松尾 康光教授マツオ ヤスミツ
所属
理工学部 生命科学科
専門分野
バイオエネルギー、環境技術・環境材料|生物物理、機能物性化学、エネルギー関連化学|電子デバイス、電子機器
キーワード
バイオマテリアル / 燃料電池 / 水素エネルギー / 光合成
関連リンク
光合成で電気をつくる! ~自然と共生する次世代エネルギー~
スマホやテレビ、コンピュータなど、今や電気は欠かすことができません。 しかし、今はまだ、電気の生成はCO2を排出する石油や天然ガスに頼っているため、 地球温暖化といった環境に負荷をがけながら、我々は電気を使っています。 CO2を排出しない次世代のエネルギーとして、水素エネルギーが知られていますが、 もし伐採植物や廃棄野菜などの棄てられる植物から、水素を簡単に得ることができればいいなと思いませんか? 皆さん聞いたことがあると思いますが、植物の葉は、光合成を行い、でんぷんを作りますが、 その途中で水素イオンが生成されます。 この水素イオンを使い、、光合成から電気をつくるのが、我々の研究です。 現在、効率よく光合成から電気をつくる方法やその詳細なメカニズムについて調べるとともに、理工学部住環境デザイン学科の川上教授とともに「光合成する建築」を実作し、「エネルギー」と「緑の心地よい空間」を生む建築の実現をめざしています。
うろこから電気を創る!
皆さん、我々が食べずに捨てている「魚のうろこ」や「カニの甲羅・エビの殻」が次世代水素エネルギーを生み出す燃料電池の心臓部に使えること、知っていますか? 生物は35億年以上の年月を費やして、様々な機能を創り、改良してきました。その一例が、魚のうろこやカニの甲羅などの水素イオンだけを通す性質です。魚のうろこはコラーゲンとハイドロキシアパタイトから成り、カニの甲羅やエビの殻はキチン・キトサンからできていて、生物によってつくられます。我々は、このコラーゲンやキチンが水素イオンだけを通し、水素から電気を取り出す燃料電池の心臓部「電解質」に利用できることを最近見い出しました。環境にやさしい自然素材から成る燃料電池の誕生です。 現在、コラーゲンやキチンの分子構造を変化させ、より速く、多くの水素イオンを流すことのできるバイオ燃料電池電解質の探索と合成を行っています。