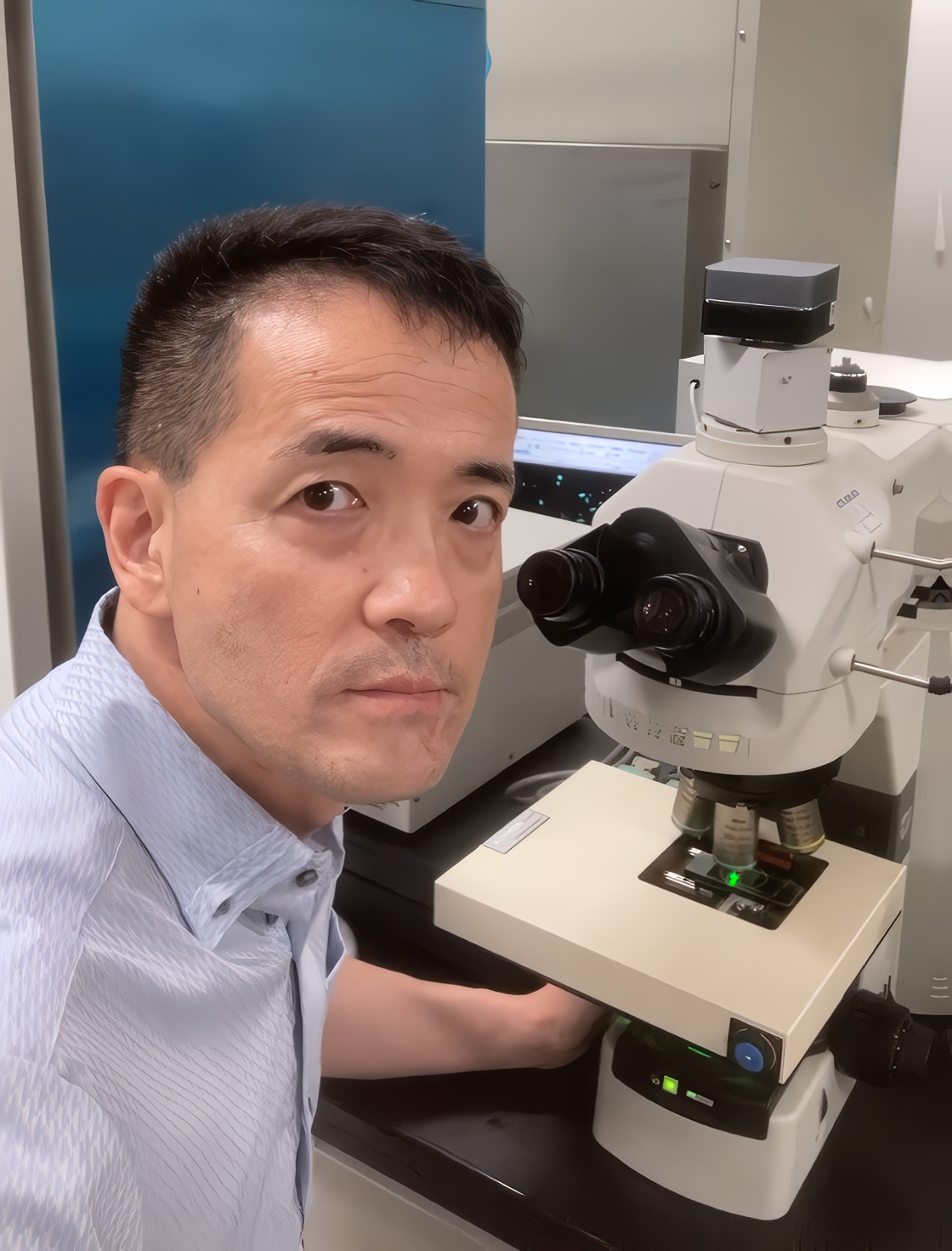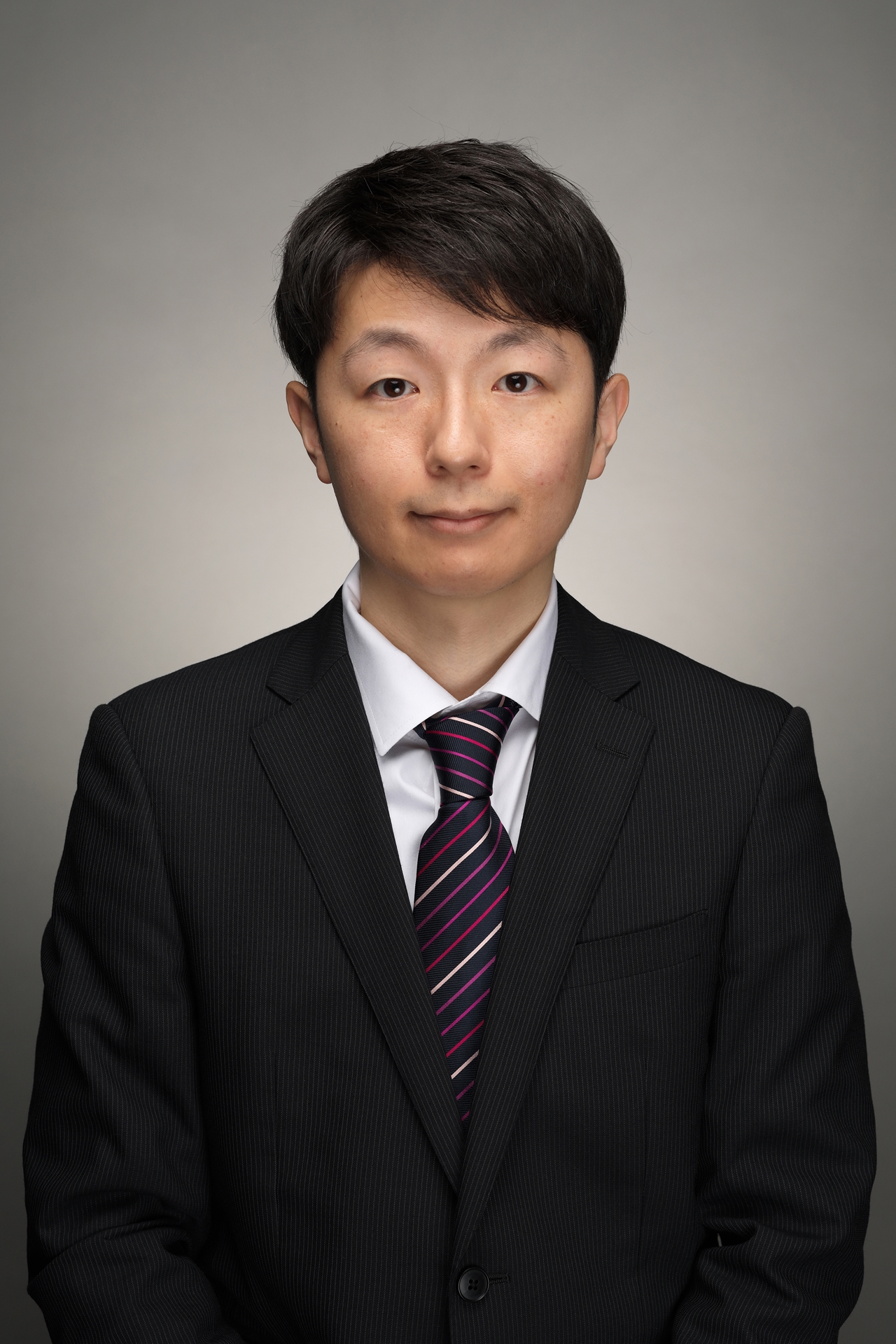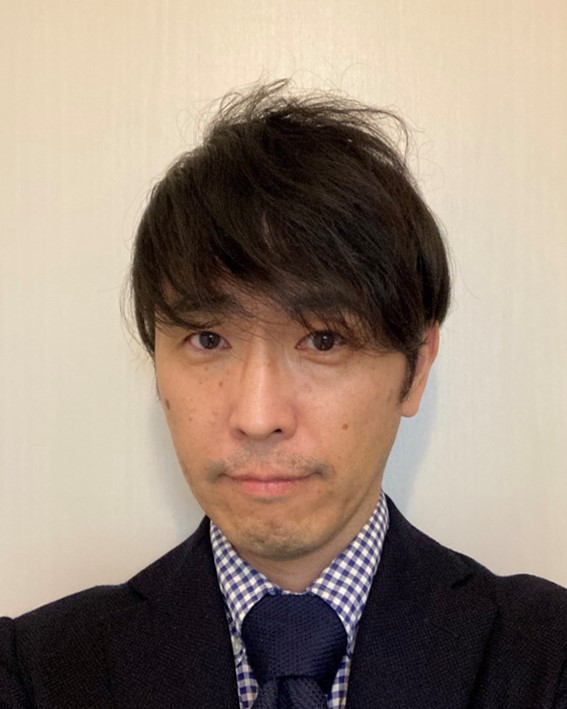中嶋 義隆教授ナカジマ ヨシタカ
所属
理工学部 生命科学科
専門分野
構造生物化学
キーワード
構造生物学
関連リンク
プロフィール
| 出身 | 兵庫県 |
|---|---|
| 愛読書 | 和田美代子著 高橋俊成監修 「日本酒の科学」講談社 2015 |
| 好きな映画 | 紅の豚 |
| 好きな言葉 | 「飛ばねぇ豚は、ただの豚だ。」ポルコ・ロッソ |
研究紹介
タンパク質は,我々ヒトも含む多様な生物を形作る重要な構成成分のひとつです.様々なタンパク質が知られていますが,生命活動においてこれらは,それぞれにひとつ(あるいは複数)の重要な役割を担っています. 一方,どのタンパク質分子も基本的には,直鎖状に連結したアミノ酸の重合体が折畳まれるという共通の構造を持っています.しかしながら,構成するア ミノ酸の種類や順序,折り畳み方が異なることで,タンパク質分子はそれぞれ固有の「形(構造)」を採ります. この「形(構造)」こそが,タンパク質の持つ機能に重要な関わりを持っています. 目で直接、見ることができないタンパク質の分子構造をX線と結晶を使って、可視化することで、タンパク質の機能、主に酵素がどのようなメカニズムで発揮されるかについて研究しています。
研究との出会い
私は理学部化学科の出身です。大学に入学する頃は、「有機合成を学んで将来は創薬に携われたらなぁ。」なんて、漠然と考えていました。3年次になると卒業研究に向けて、所属する研究室を選択します。本学でも同じですね。化学科の場合、有機化学分野、無機化学分野、物理化学分野に大きく分類されるでしょうか。それぞれの教員による研究室紹介を聴いている中で、構造化学研究室のプレゼンで紹介されたタンパク質分子のリボン図に目を奪われたことを今でも思い出します。物理化学分野って、候補に入ってなかったんですよね。でも、そこから改めて、生物学を学びはじめ、微生物を使ったタンパク質の生産や精製したタンパク質の結晶化、大型放射光施設で夜を通して結晶からのX線回折データ測定、UNIXやLinuxのコンピュータを使ったデータ解析とタンパク質分子のモデリングなどなどを経て、誰もみたことのない分子のかたちがみえたときは喜び勇んだものです。化学も物理学も生物学も情報工学など、融合的な学問分野であったことも性に合っていたのかもしれませんね。みなさんも、心躍るような素敵な研究との出会いがあると良いですね。
SDGsの取り組み
社会課題
- バイオ・ライフサイエンス