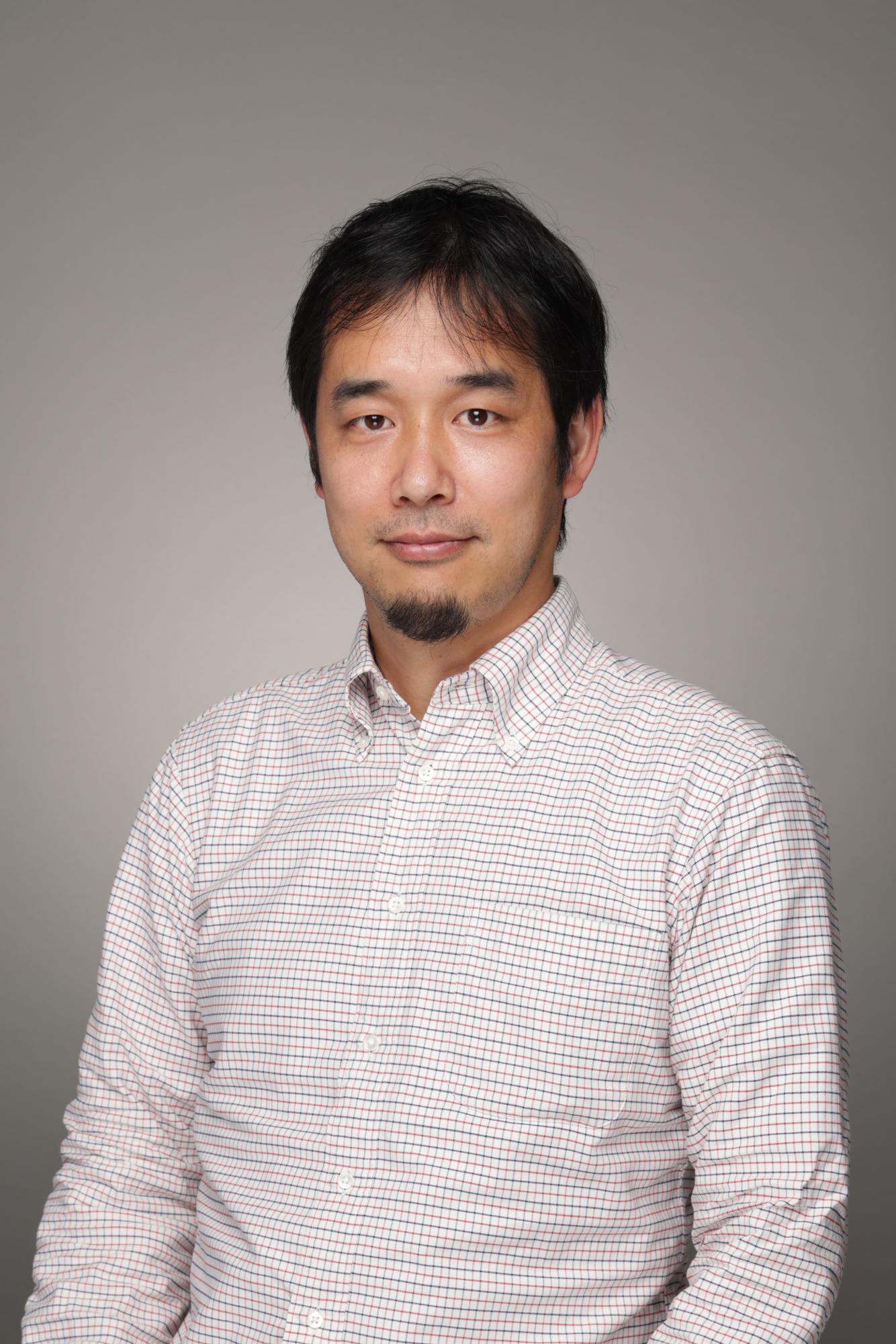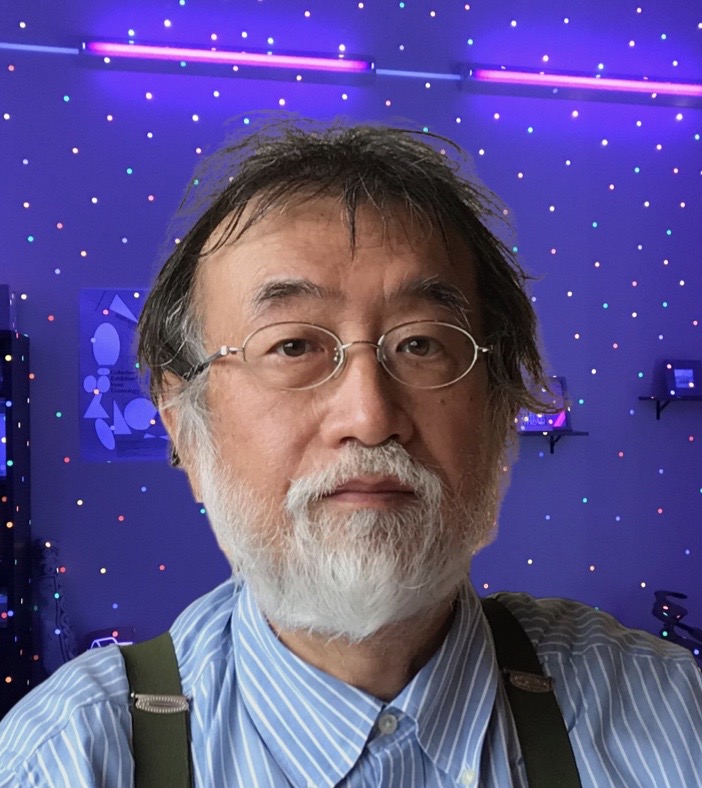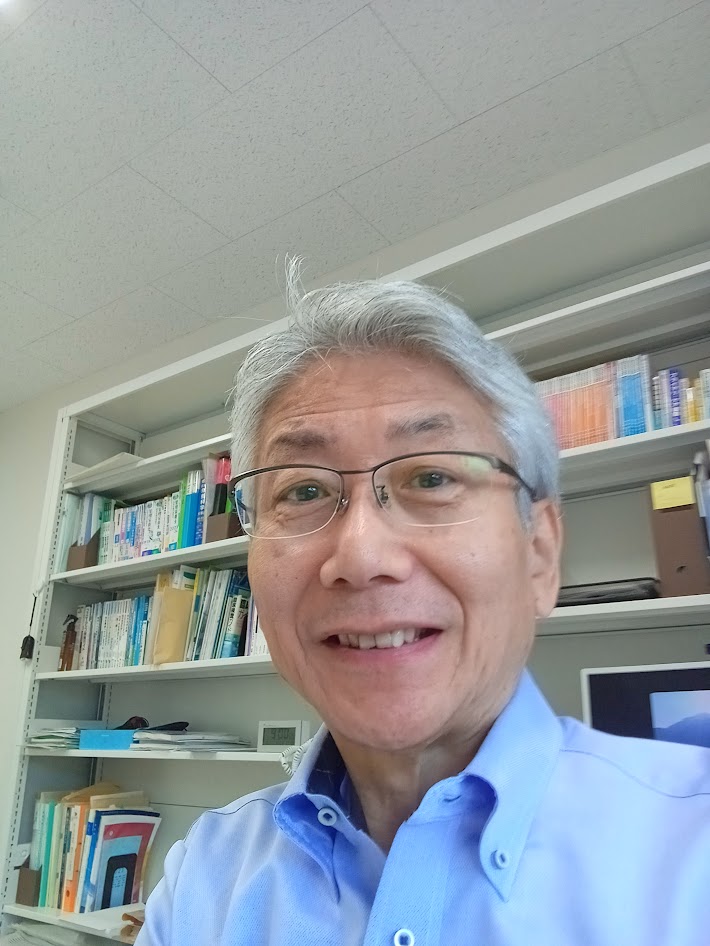福家 悠介特任助教フケ ユウスケ
所属
農学部 応用生物科学科
専門分野
生態学、進化学、生物地理学
キーワード
自然史、群集形成、系統地理、古代湖、海洋島、淡水魚、淡水エビ類
関連リンク
プロフィール
| 出身 | 埼玉県 |
|---|---|
| 生年 | 1994年 |
| 好きな国・地域 | ミャンマー |
| 子どものころの夢 | 研究者 |
| 好きな言葉 | 知らんけど。 |
主な研究テーマ
私が主体となって進めている主な研究テーマをそれぞれ140字ぐらいで紹介します。
淡水エビの在来種と外来種の生態学的相互作用
生物多様性を脅かす大きなリスクのひとつが侵略的外来種です。外来種はしばしば、侵入先に元からいた近縁の在来種と置き換わってしまうことがあります。どのように在来種と置き換わるのか?なぜ外来種の方が強いのか?こうした疑問に答えるべく、カワリヌマエビ属のエビをモデルに研究を進めています。

琵琶湖の淡水エビ類。4種いるのですが、分かるでしょうか。このうちの1種は外来種(シナヌマエビ)です。琵琶湖周辺の多くの場所では、いつの間にか、在来種(ミナミヌマエビ)がこの外来種と置き換わってしまいました。
インレー湖の淡水魚類の進化と起源
ミャンマーの古代湖であるインレー湖には、固有種含む多様な淡水魚類が生息しています。本地域の魚類の固有性がどのように形成されたのかを調べるために、遺伝的アプローチを使って研究しています。浅く小さな湖ながら、インレー湖はなぜ高い多様性・固有性を有しているのか、その謎に迫っています。

インレー湖で漁をするインダー族の漁師。現地では、淡水魚類が主要なタンパク源となっており、市場では様々な魚類が見られます。

インレー湖の周辺には、この地域でしか見られない固有種が数多く生息しています。写真はコイ科のDanio erythromicronという2 cmほどのイチオシ美麗フィッシュです。
野外での新しい発見を論文として報告する
野外調査をしていると、思いがけない発見をすることがあります。例えば、その地域では記録のない種を見つけたり、図鑑に載っていない行動を観察したりなどです。こうした発見を自分だけの思い出にせず、論文として公表することで、科学的知見の蓄積に貢献できます。論文を書いて図鑑を厚くしよう!

深いことは考えず、とりあえず生き物を見に外に出ましょう。自然にはまだまだ未知がたくさんあります。新しい発見をする悦びを味わいましょう。
SDGsの取り組み
社会課題
- 自然環境・廃棄物
- バイオ・ライフサイエンス
- 農林水産業