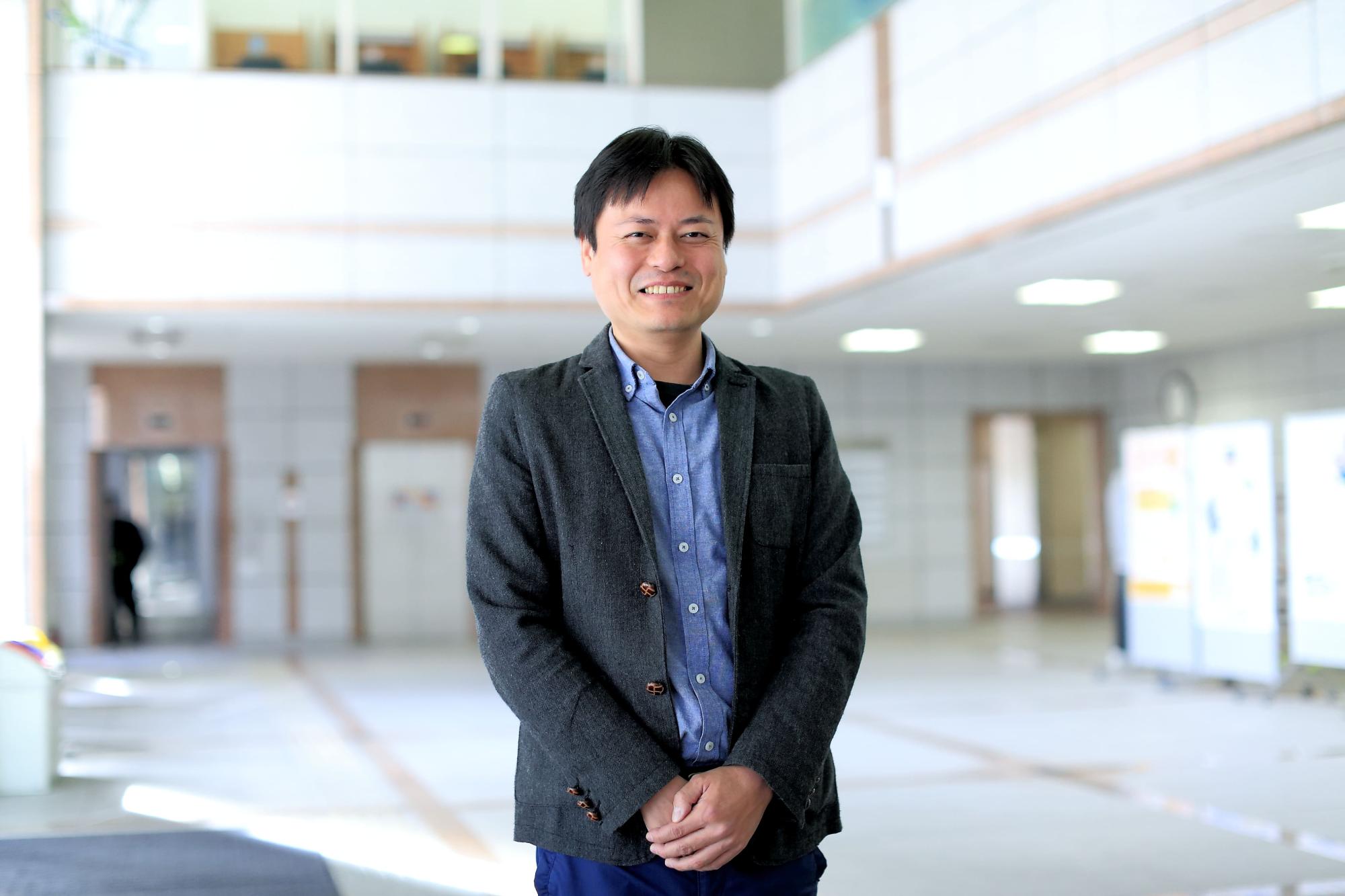本多 康作准教授ホンダ コウサク
所属
法学部 法律学科
専門分野
基礎法学|民事法学
キーワード
商法、約款、基礎法学、J.L.オースティン、発話行為論、ヘイトスピーチ
関連リンク
プロフィール
| 出身 | 山口県 |
|---|
いかなる仕方で何を学ぶのか
法学部ではいかなる仕方で何を学ぶのでしょうか。法学部では通常、憲法、民法、刑法などの「法律」を学びます。我々が住み暮らす日常の世界には、「法律」以外にも様々な規則ないしルールがあります。例えば野球とサッカーにはそれぞれ異なったルールが存在し、それぞれのルールがそれぞれのスポーツの違いを生み出していますし、スポーツのルール以外にも「約束は守るべし」とか食事のマナーなど様々なルールが存在しています。日常のルールを学ぶ際に本(文字)を読み、身につけたという人はいない(少ない)でしょう。しかし「法律」を学ぶには本(文字)を読むという行為が不可欠です。その理由も含め一緒に「法律」を学びましょう。
約款の拘束力
「合意は拘束する」。これは「当事者間の合意に法的拘束力を認めるローマ法の原則」で、今日でも国際法および契約法の原則とされています。この原則が存在するからこそ、国家であれ、個人であれ、合意したという事実から合意された内容に拘束力を認めうるとするのが一般的な理解です。他方、例えば事故や病気に備えて保険に加入する際、「約款」と呼ばれる大量の契約条項を利用し契約を締結します。その際に「約款」を読んだことがある人は殆どいないでしょう。しかし契約者は「約款」に拘束されます。なぜでしょうか。こうした状況をいかに説明するか、あるいは正当化するかをめぐる議論が「約款の拘束力」の問題です。