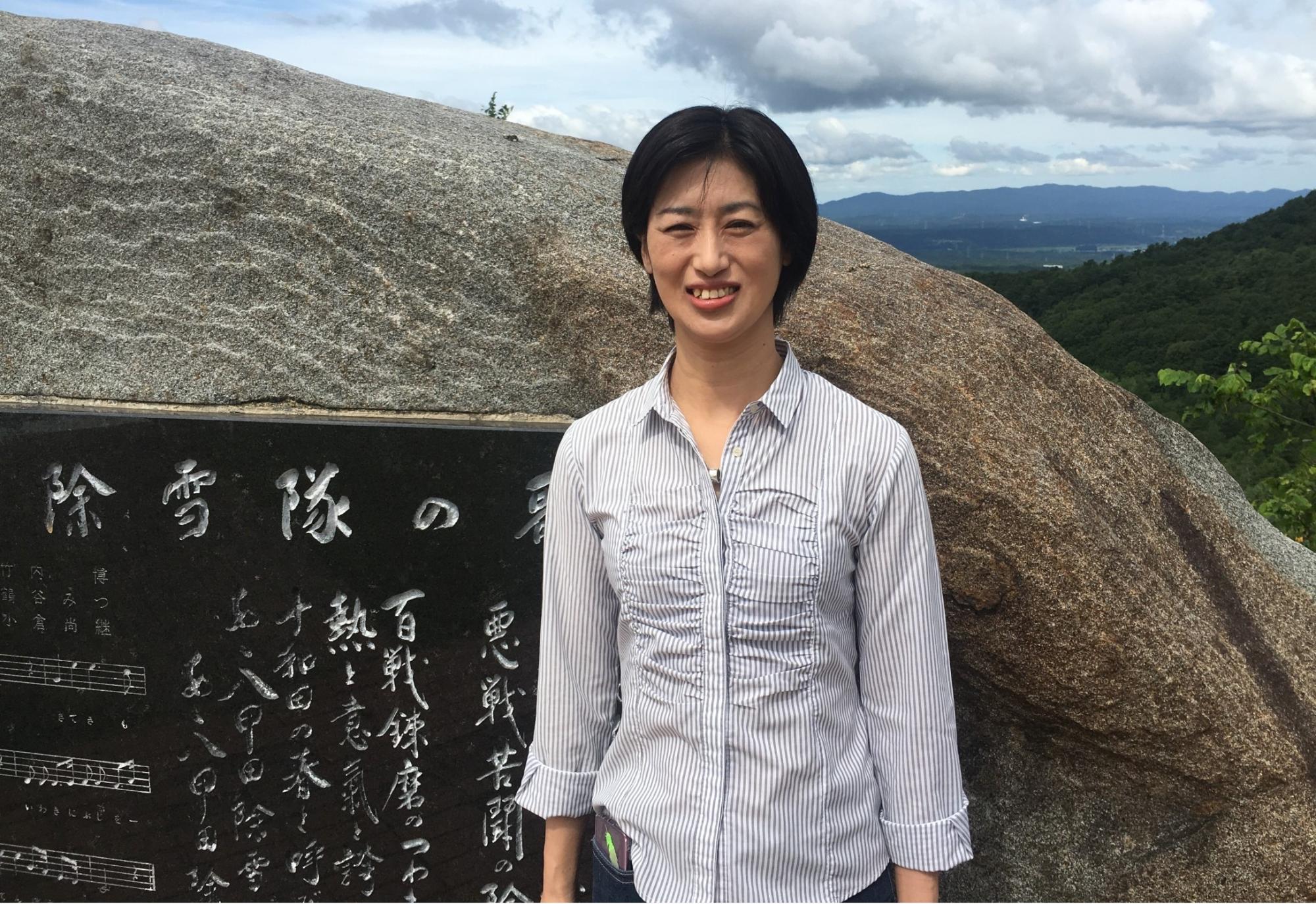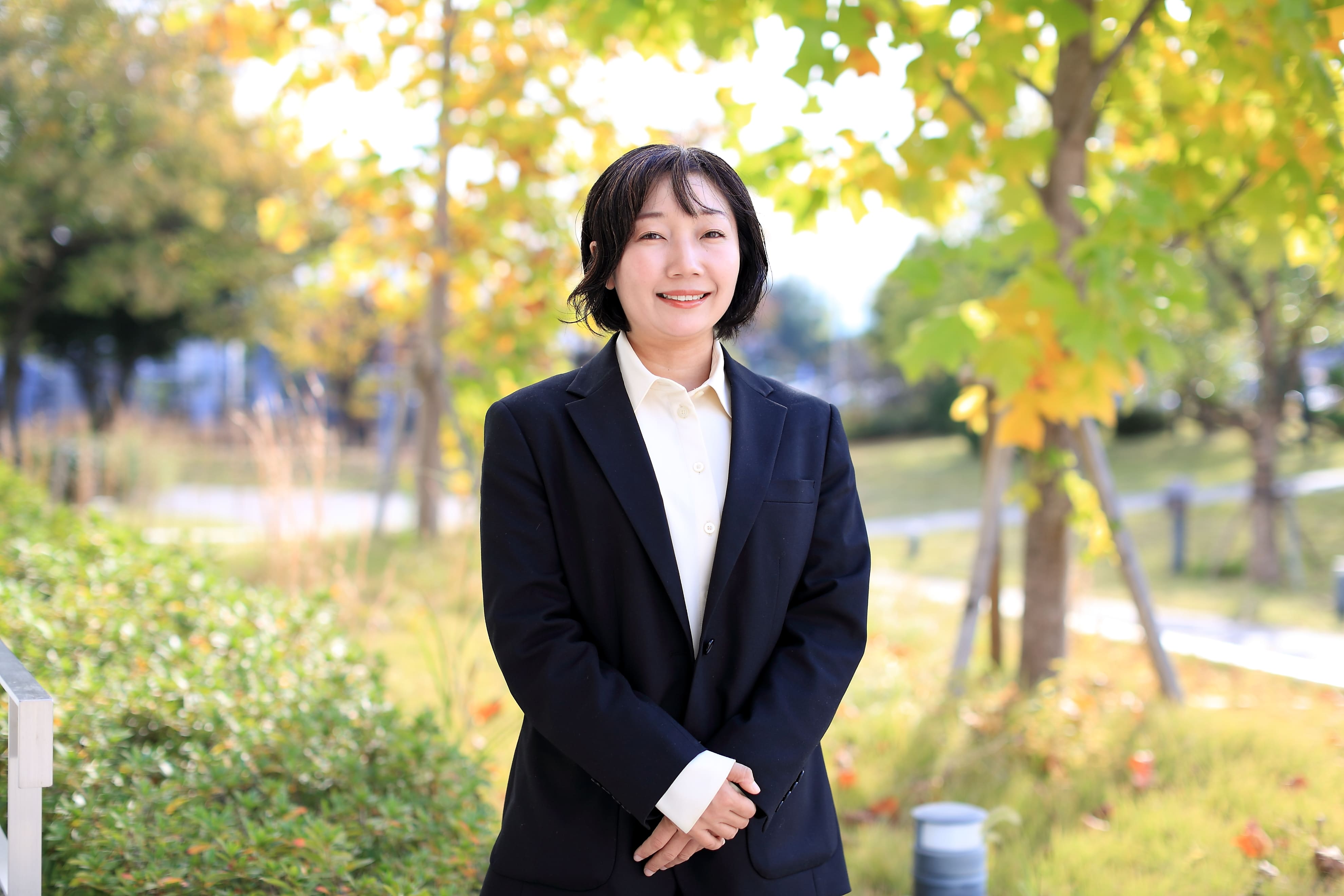國島 大河講師クニシマ タイガ
所属
農学部 応用生物科学科
専門分野
生物資源保全学|水圏応用科学|基礎生物学
キーワード
魚類学、生活史、群集構造
関連リンク
プロフィール
| 出身 | 神奈川県 |
|---|---|
| 生年 | 1990 |
| 好きな映画 | LIFE |
| 好きな国・地域 | 沖縄 |
| 子どものころの夢 | 研究者 |
| 好きな言葉 | 心は水の如し |
自己紹介
幼少の頃から生き物が好きで、大学進学を機に憧れの沖縄へ移住し、亜熱帯の魚類について研究しました。学位取得後は和歌山県立自然博物館で学芸員として約6年間勤務し、標本コレクションの維持管理や生物観察会の講師、企画展の立案実行など、環境教育と研究を両立させてきました。現在は、様々な水圏環境に暮らす魚類とその生息地の保全を目指して、野外での調査を中心に、生活史や生息環境など魚類の生態を研究しています。より詳しく研究内容をお知りになりたい方は、我々の研究室HP(https://setsunanmarinelab.wixsite.com/my-site)や個人HP(https://sites.google.com/site/kunishimalabo/home?authuser=0)をご覧ください。
研究紹介
私の研究は、フィールドに出て生き物を捕まえたり観察することから始まります。捕まえ方も様々で、釣りや投網、地曳網、たも網などを使うこともあれば、市場で購入したり、漁師さんの船に乗せてもらって採集することもあります。そして、フィールドで得られたサンプルを実験室で解剖したり計測することでデータを集め、例えば何歳まで生きるのか、何を食べているのか、いつ産卵するのかといった生態を明らかにしていきます。野外での調査は、イメージ以上に地味で大変なものですが、多様な魚類の生きざまに魅せられて研究を続けてきました。 これまで、淡水魚から海産魚まで幅広い魚種を対象にしてきましたが(時にはサメ類も!)、最近は特に河川へ侵入する海産魚類(スズキやボラ、クロダイなど)の生態に興味を持っており、一緒に研究してくれる学生を募集しています。本学に着任してからは、淡水性のカメ類や甲殻類(サワガニ)、魚類の寄生生物(ウオノエ)、干潟の共生生物系(スナモグリ類)など、学生の興味に沿う形で研究テーマが広がりつつあります。大阪湾の海洋生物や魚類について興味がある学生さんはぜひ気軽にご相談ください。
SDGsの取り組み
社会課題
- 農林水産業
大阪湾はかつて「魚庭(なにわ)」の海と呼ばれるほど豊かな海でした。しかし、環境悪化や乱獲、気候変動の影響を受けて漁獲量は減少の一途を辿っています。人が直接利用する水産資源だけでなく、それらを含めて多様な生物が共存できる健全な生態系を守っていくことは、我々人間が魚介類の恵みを利用していくためにも重要です。そのためには、まずは身をもって現状を知り、問題点を解決していく必要があります。我々は、水産資源そのものや、その生息地の保全を目指し、野外での調査研究を進めています。
 摂南大学を目指すあなたへ
摂南大学を目指すあなたへ