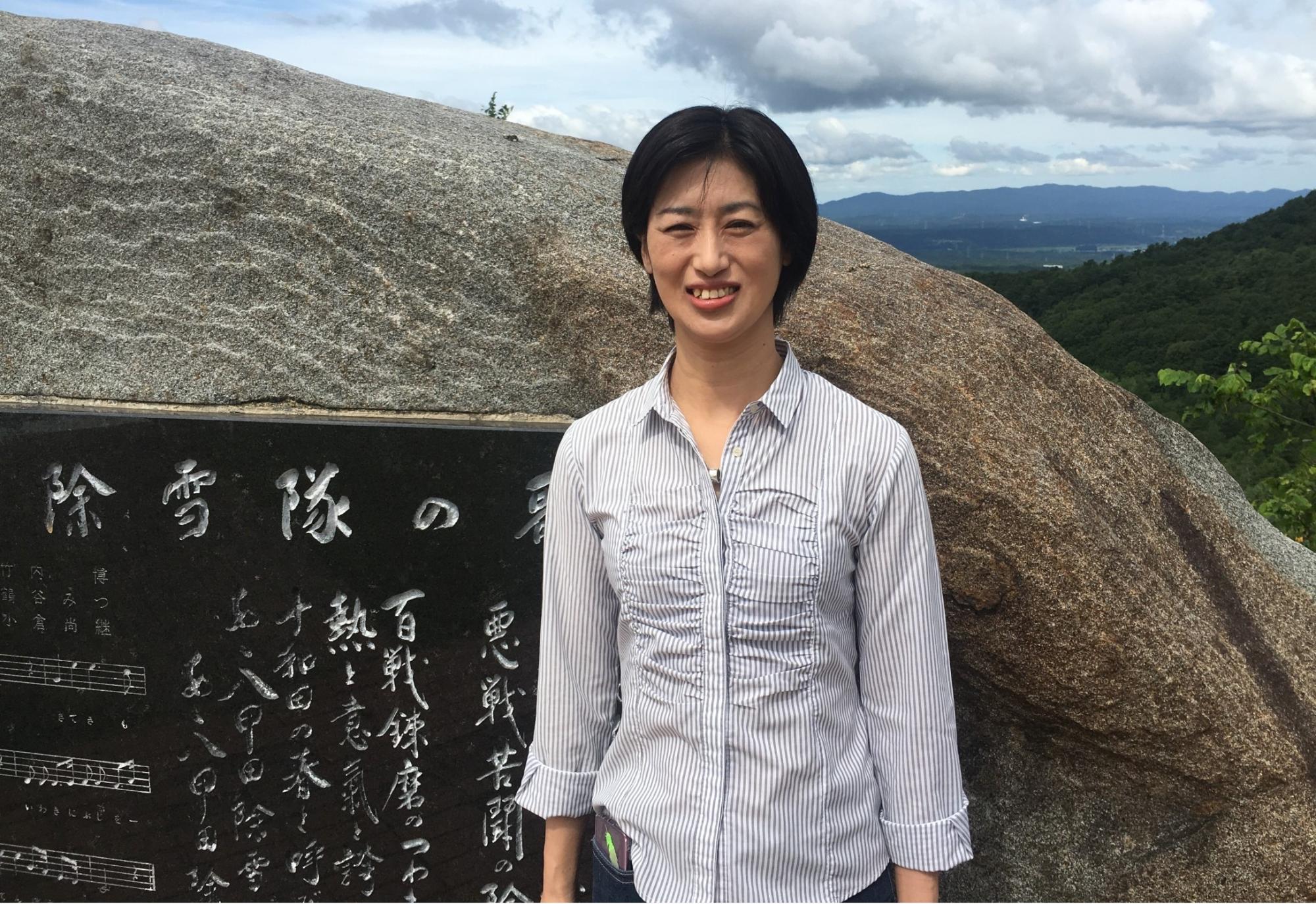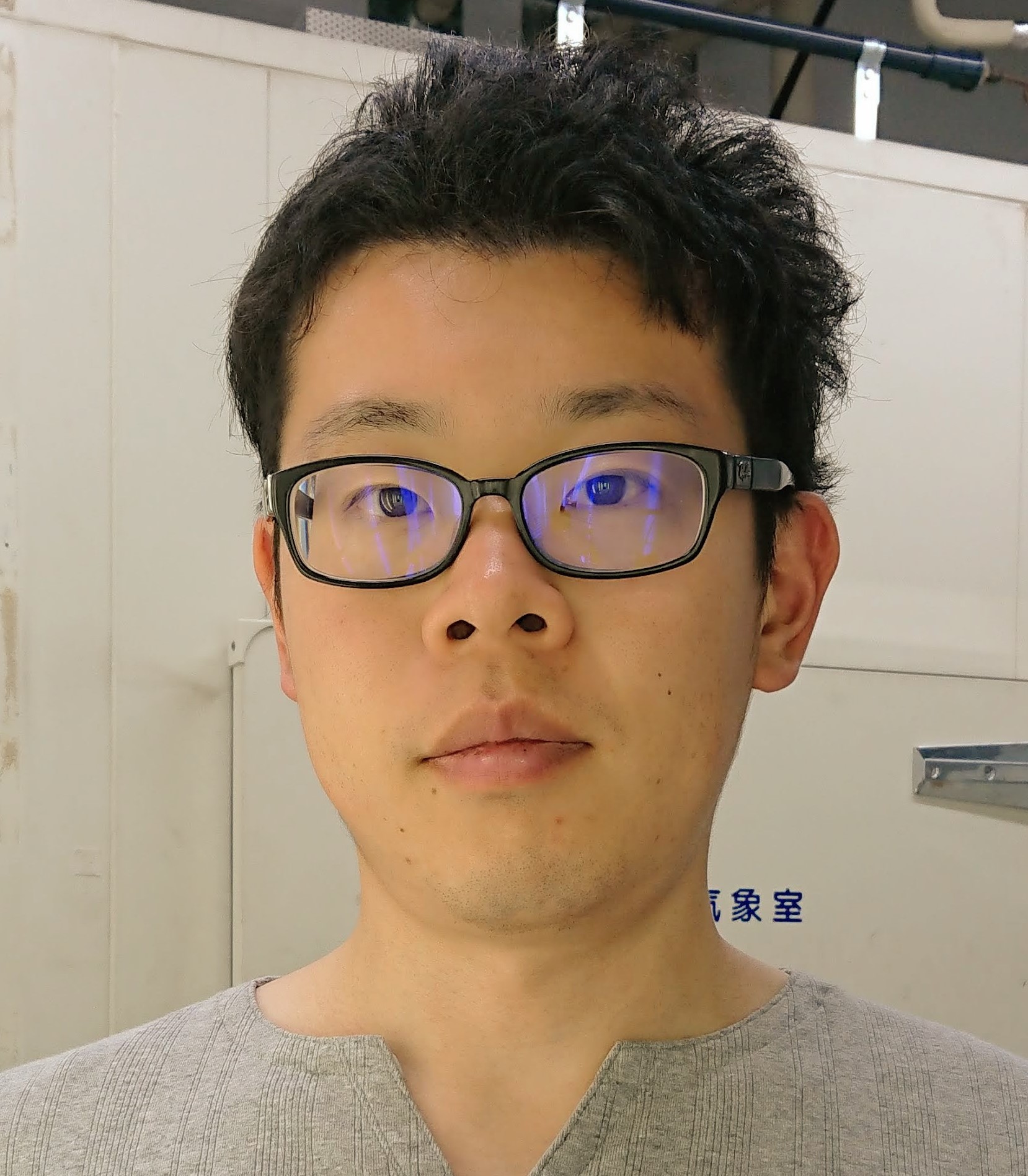
高木 大輔講師タカギ ダイスケ
所属
農学部 農業生産学科
専門分野
植物栄養学、土壌学|作物生産科学|植物分子、生理科学
キーワード
光合成、環境ストレス、植物栄養学、植物生理学、植物生化学
関連リンク
プロフィール
| 出身 | 京都府(長岡京市) |
|---|---|
| 生年 | 32333 |
| 子どものころの夢 | 画家 |
| 休日の過ごし方 | 買い物、おでかけ、筋トレ |
| 学内おすすめスポット | 農学部の圃場 |
| 好きな色 | 緑 |
植物は、どのようにして生きているのか?
植物は、根を下ろしたその場所で様々な環境変化に耐えながら一生を過ごします。動物とは異なり、暑いときに日陰に逃げることも、水が足りない時に自ら歩いて水を取りに行くこともできません。 では、植物は如何にして地球上で最大のバイオマスを維持するにまでに繁栄できたのでしょうか? 環境に適応しながら光合成をうまく制御して生きているその過程には、私たちがまだ理解できていない植物の「賢さ」があるはずです。 農学的に見ても、植物が環境に適応する分子的な機構を理解することは、環境の変化に対して高い適応能力を持った作物を新しく生み出すために重要な情報となります。 私たちは、そのような植物の「賢さ」について、特に光合成機能に着目して分子レベルから生態レベルで研究しています。そして、将来にわたって地球上で持続的かつ安定的に栽培できる作物の開発に貢献しうる知見を残していくことを目指しています。
植物に与える栄養と生長
植物には、C,H,Oを含めて17種類の生育には欠かせない元素があります。これら元素のことを「必須元素」と呼びます。これらの元素が植物細胞内において欠乏すると植物の生長は抑えられますが、逆に過剰な濃度で存在していても、植物の生育を顕著に阻害します。 農業の現場において、これらの栄養素の過剰障害は「毒性」として広く認識されていて、「肥料を作物に与えすぎてはいけない」という経験上の理解はあるのですが、「なぜ栄養をたくさん与えすぎてはいけないか?」という疑問に対する答えは明確にわかっていません。 私たちは、このような背景の下、イネやコムギ、ソバなど多彩な作物を用いて植物の必須元素や土壌金属元素が植物の生理応答に与える影響の解明を進めています。 これらの研究によって、元素の細胞内動態と毒性発症の原因を明らかにできれば、それを調節・克服することでたくさん栄養を吸収しても毒にならず、より元気に育つ作物をデザインできるのではないかと考えています。