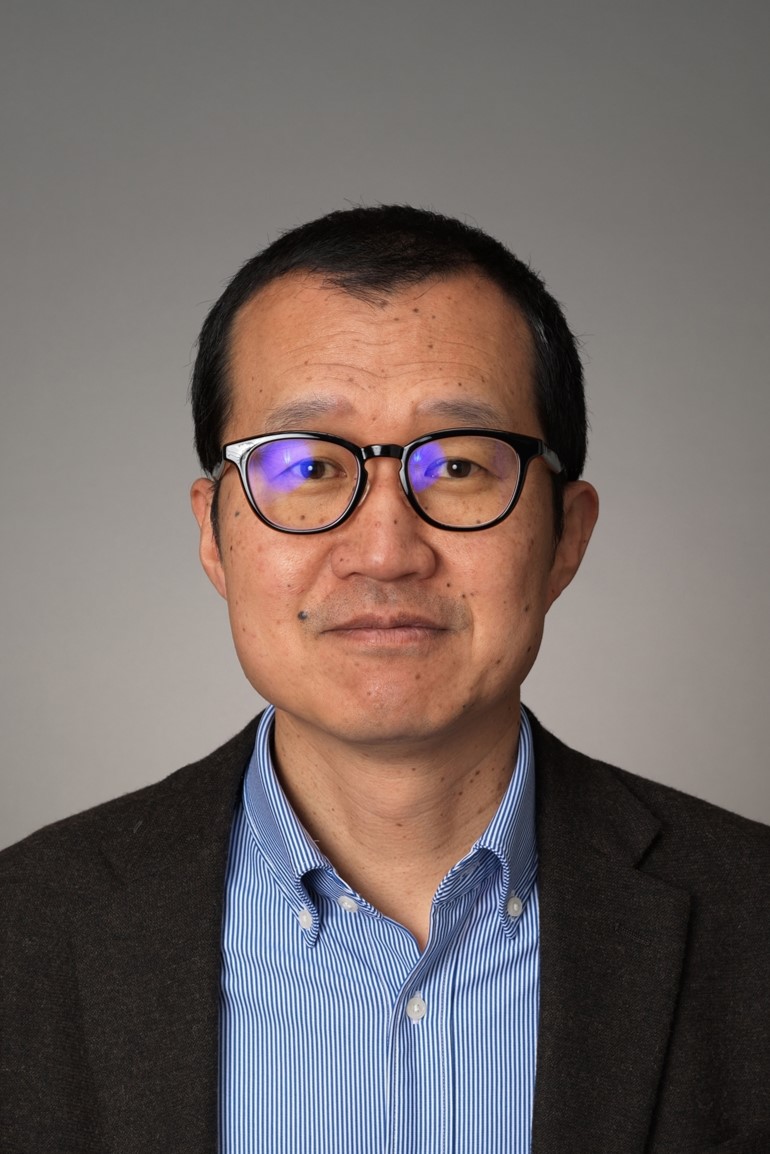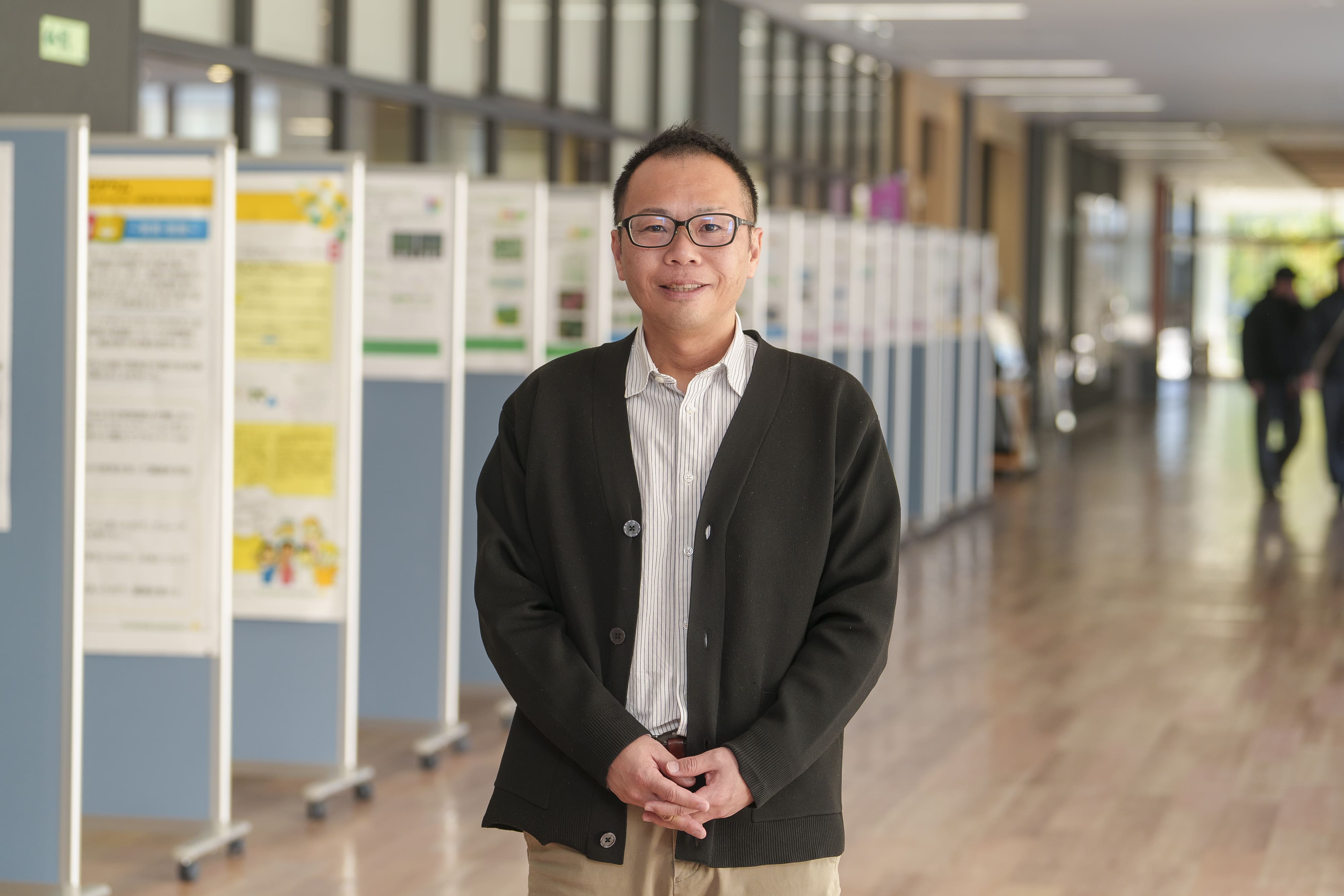畦西 克己准教授アゼニシ カツミ
所属
農学部 食品栄養学科
専門分野
臨床栄養学
キーワード
高齢者 / 低栄養 / 咀嚼 / 嚥下 / 物性
関連リンク
プロフィール
| 出身 | 大阪府 |
|---|---|
| 好きな国・地域 | オーストラリア |
| 子どものころの夢 | 探検家、冒険家 |
| 休日の過ごし方 | 近場の名所めぐり |
| 好きな言葉 | 継続は力なり |
| 学内おすすめスポット | 学食 |
担当科目紹介
疾患と栄養に関わる科目である「臨床栄養学Ⅲ」「臨床栄養学Ⅳ」「臨床栄養学実習Ⅲ」「応用栄養学Ⅰ」を担当しています。また、近年、病院などの医療現場ではチーム医療の必要性が求められています。本学科では薬学部および看護学部の学生との連携授業を推奨しており「セルフメディケーション演習」「臨床医療演習」「臨床医療実践演習」の科目を担当しています。私は、本大学に着任する前は病院のチーム医療に30年以上携わってきました。その経験を活かし、栄養治療におけるより実践的な授業を行っています。授業を通して、学生に医療現場における栄養管理やチーム医療の重要性について、理解が深められるように取り組んでいます。
研究紹介
現在、行っている研究は高齢者の栄養改善です。超高齢社会において、所在数が多い住宅型有料老人ホームに入所されている高齢者の栄養状態を調査したところ、入居高齢者の50%近くが低栄養であることが分かりました。このような民間の高齢者施設には栄養士ならびに管理栄養士の配置義務が設けられていないことから、低栄養高齢者に対し栄養介入を実施し、栄養状態の改善を試みています。栄養介入が延命並びに介護度の維持および低下に繋がり、ADLおよびQOLの改善が期待できると考えられます。一方、歯の損失など咀嚼機能が低下した高齢者は冷凍の肉や魚などを調理した際、硬く、バラつき、パサつきが大きく、食べにくいのが現状です。そこで、市販食品品質改良剤(酵素剤)の使用の有無と調理加熱方法(普通・圧力・低温加熱)の違いから、軟らかく、噛みやすく、食べやすくする研究を行っています。
SDGsの取り組み
社会課題
- 医療・健康
- 社会福祉・介護
 摂南大学を目指すあなたへ
摂南大学を目指すあなたへ