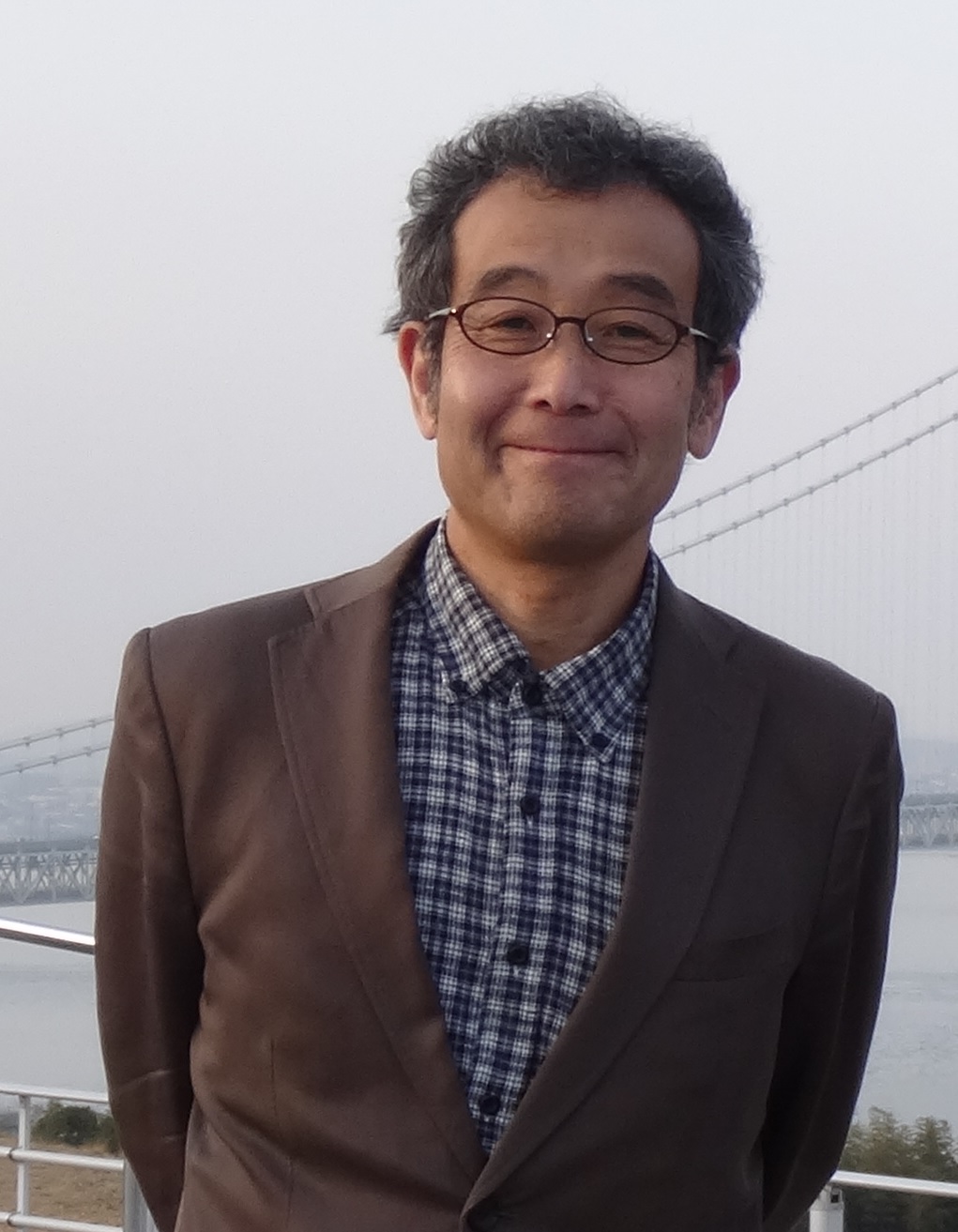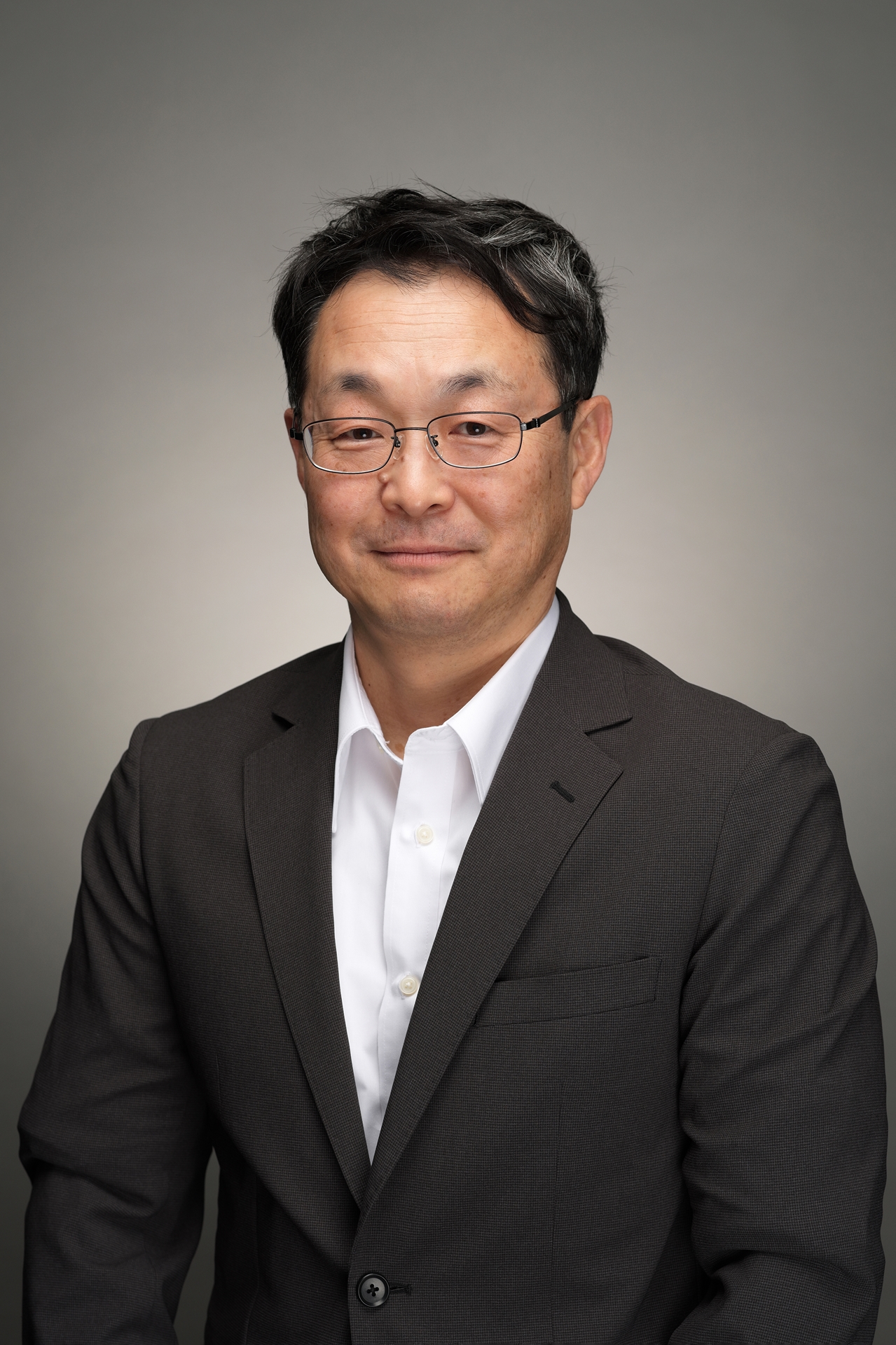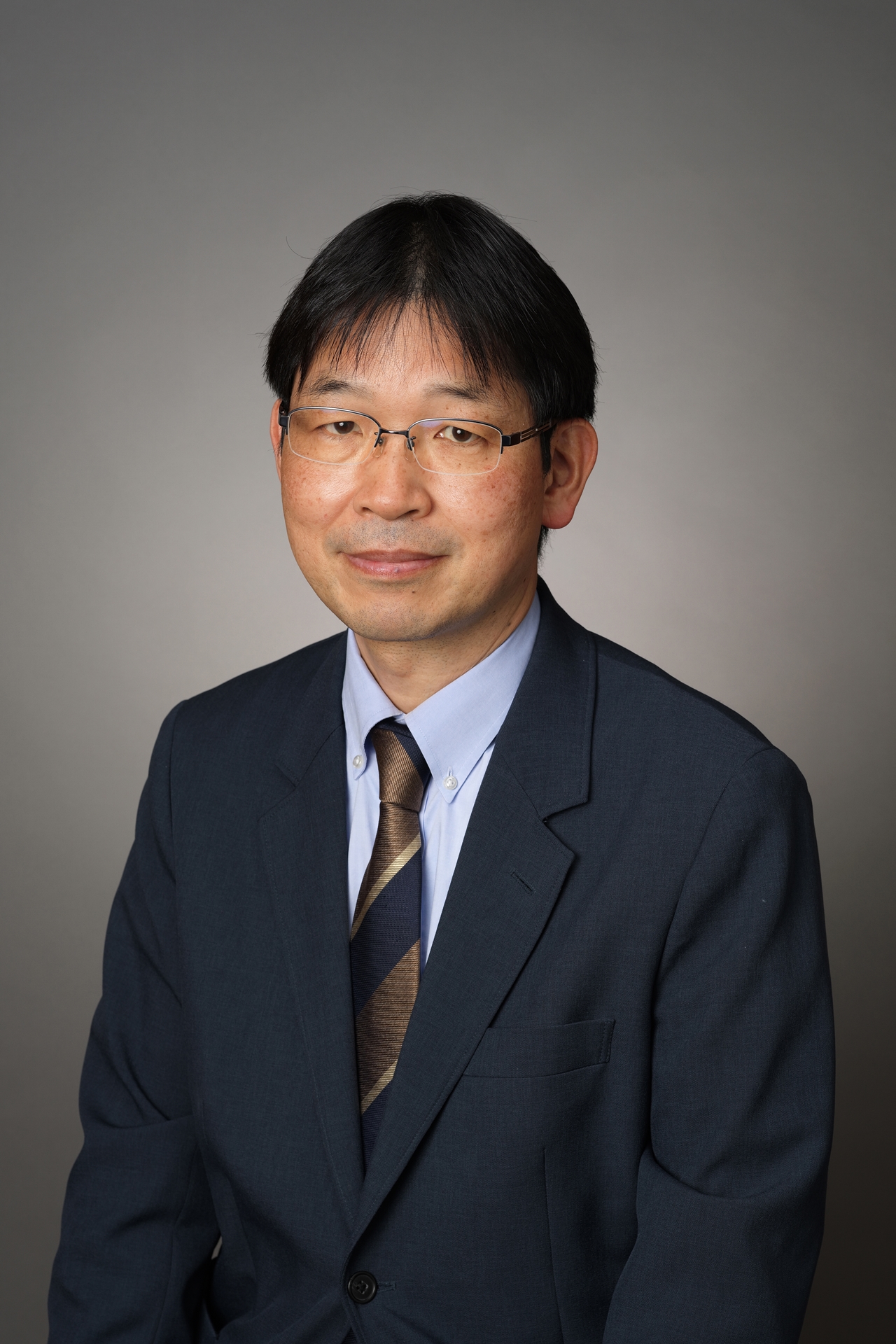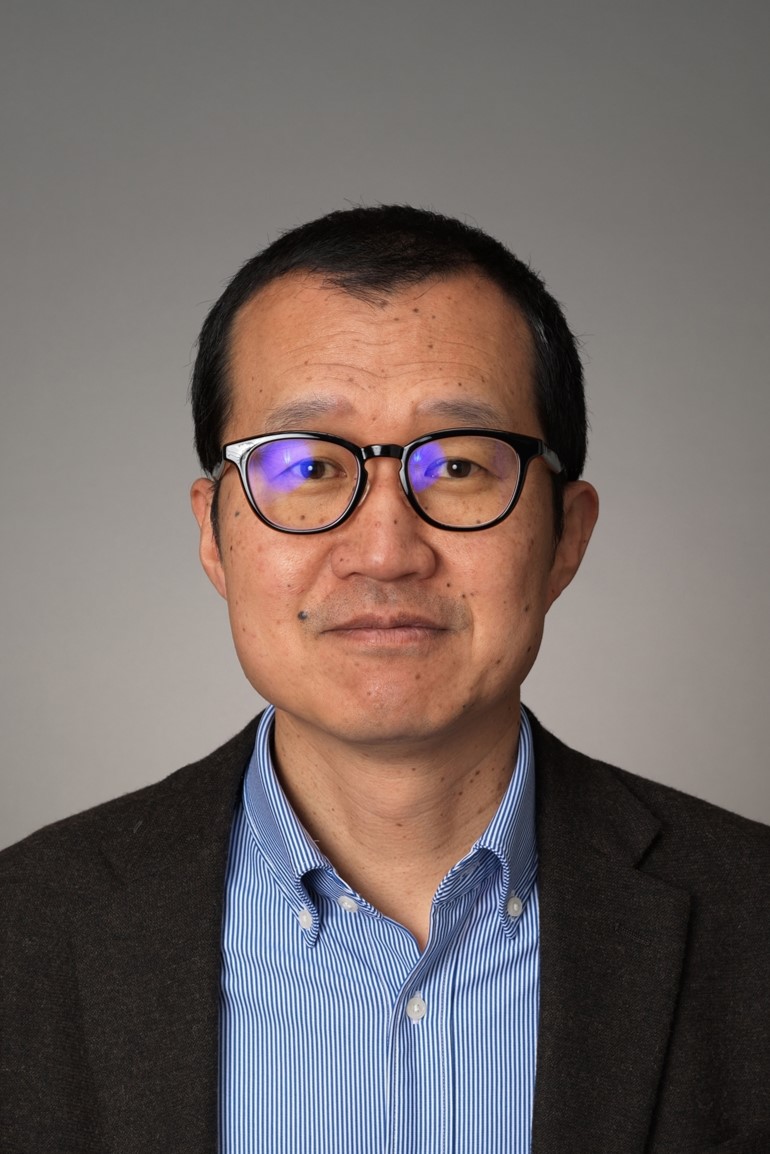
加藤 直樹教授カトウ ナオキ
所属
農学部 応用生物科学科
専門分野
応用微生物学、生物有機化学
キーワード
糸状菌(カビ)、天然化合物、生合成、微生物ライブラリー
関連リンク
プロフィール
| 出身 | 愛知県 |
|---|---|
| 生年 | 1974年 |
研究紹介~糸状菌の生産する新たな天然化合物を見つけたい
微生物の生産する天然化合物は、ペニシリンやストレプトマイシン、アベルメクチンなどのように、医薬品や農薬として広く利用されてきました。この地球上には未知の微生物が多くいます。誰も調べたことのない微生物には、その働きを誰も知らない遺伝子があり、きっと新たな化合物を作る能力をもっているはずです。最近では、新規化合物を発見するのが困難になっています。他の人と同じ方法では、すでに発見済みのものばかりを発見することになるので、探し方を工夫する必要があります。土の中からあまり研究されていない糸状菌(カビ)を集めて探索源とする、というのが工夫の一つで、もう一つは、誰も使っていない道具=酵素阻害剤を使うことです。私たちが独自に発見した阻害剤を用いることで、自分たちが欲しい化合物を効率的に見つけることができるようになりました。この手法を使って新規化合物を探すとともに、手法の拡張にも取り組んでいます。
研究における出会い~研究の転機となった微生物
カビの研究は、大学院博士課程になってから始めました。気がつけばそこからほぼずっとカビの研究をしています。前職の理化学研究所では、所属する研究室に多数の微生物が保有されており、自由に使うことが出来たので、何か上手く使えないかといろいろ培養したり分析したりする中で、あるカビ(ピレノケトプシス)に出会いました。フォマセチンという化合物を高生産する特徴を持っていて、Diels-Alder反応(大学の有機化学で絶対に習う、超有名な化学反応)を触媒する酵素の研究が、このカビを使うことで大きく発展しました。この酵素は、同じ仲間だけど、鏡像異性体を作り分けることができ、構造生物学、天然物化学、有機化学、計算科学の専門家たちと共同で、この謎「どうやって作り分けるのか」の解明に挑んでいます。
担当科目紹介
担当している主な専門科目は、「化学(1年生前期・必修)」、「生化学II(2年生後期・選択)」、「微生物工学(3年生前期・選択)」です。化学の基礎知識を復習し、専門分野を学ぶ上での土台を固める「化学」、生命現象を化学の視点で理解しようとする学問である生化学のうち、特に重要な分野であるタンパク質と酵素について学修する「生化学II」、そして微生物による物質生産に焦点を絞り、微生物機能の活用方法の理解を深める「微生物工学」、と段階的に学びを進め、生物と化学の関係性を分子レベルで理解することを目指します。
SDGsの取り組み
社会課題
- 医療・健康
- バイオ・ライフサイエンス