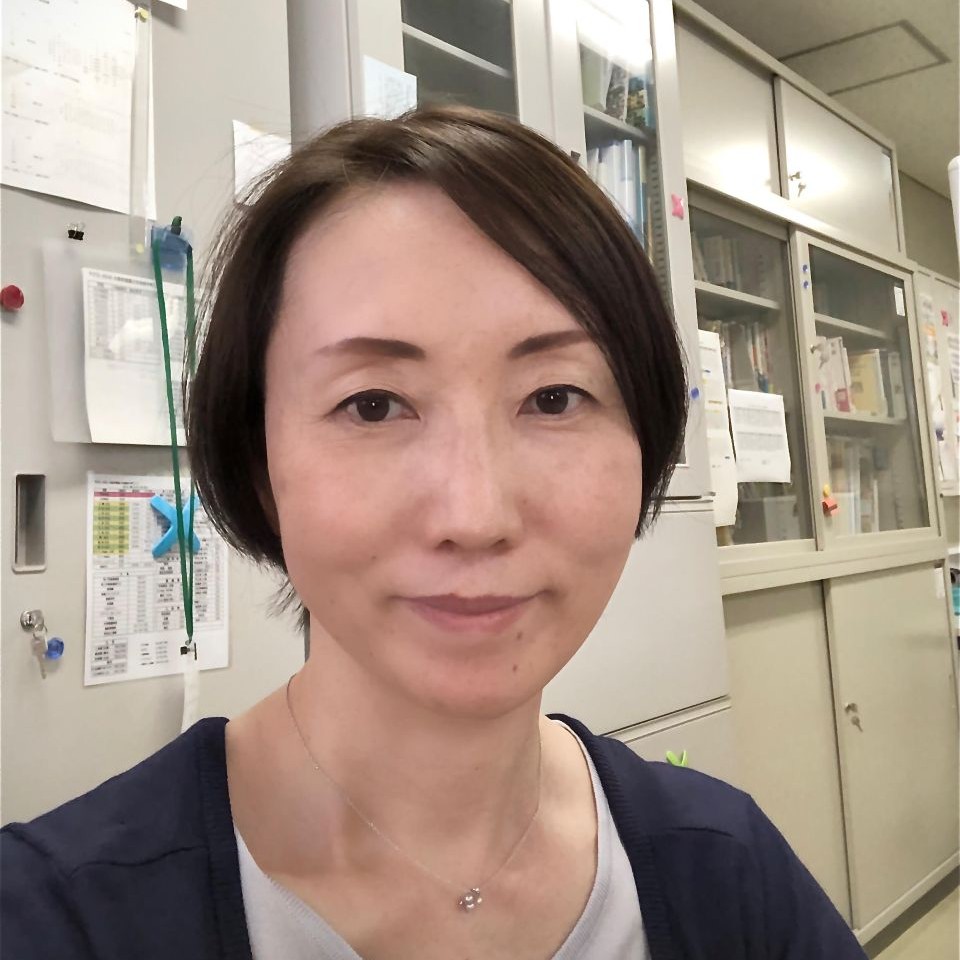熊野 知司教授クマノ トモジ
所属
理工学部 都市環境工学科
専門分野
土木材料、施工、建設マネジメント
キーワード
コンクリート用材料,暑中コンクリート,施工,電磁波吸収
関連リンク
プロフィール
| 出身 | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| 生年 | 1963年 |
| 尊敬する人物 | 江崎 玲於奈 氏 |
| 子どものころの夢 | 海洋開発の技術者 |
| 休日の過ごし方 | ドライブ,ご朱印集め |
| 好きな言葉 | 牛歩のごとく進め |
法則に基づく現象の予測を
私は、大学院修正課程を修了後12年間ゼネコンで勤務した経験があります。工事現場で施工管理を出発点として、技術部や技術研究所などで勤務しました。その間を通じて、一貫して取り組んだ課題は、コンクリートのひび割れの問題でした。当時は、大型構造物を施工した際の温度ひび割れの抑制が社会的な要求となっていまして、温度ひび割れの発生をコンピューターによって予測することが業務の大半を占めていました。熱伝導解析や温度応力解析等、力学モデルに基づいたシミュレーションを行うのですが、重要なのは解析への入力値です。特に時間軸上で変化するコンクリートの引張強度や応力の緩和につながるクリープ係数などは、これまでの経験に基づいた値を入力していました。しかし、これでは、新しい添加材料が開発される度に、入力値を求める必要があります。普遍的な物理法則に基づいて入力値を決定する体系を整備しないと、今後、新たな添加材料がどんどん増えるにしたがって、後手に回ってしまうことになると考えていました。 現在の職に就くにあたって、普遍的な物理法則をもとに現象の予測が行える方法を念頭において研究活動を行っています。コンクリートのクリープ理論への破壊力学の応用、コンクリートの粘性変化へのエネルギー理論に基づく速度論の適応、骨材界面回りの応力解析に基づくコンクリートの弾性係数の推定等です。いずれもまだ、体系化には遠いのが現状です。AI技術の導入などで過去の論文のデータ等をもとに統計的に確からしい入力値を求める方法もあると思いますが、現象の予測を真に高精度に行うためには普遍的な物理法則に基づいた予測手法を体系化する以外にないと考えています。これからも柔軟な思考力を備えておられる若い人たちと研究を続けたいと思います。
失敗を恐れないで
実験の授業で仮説どおりの結果が出なかった場合に「予想したとおりにならなかった。」、「実験は失敗だった。」と悲観的な記述で終わってしまうことがよくあります。また、卒業研究のゼミの打合せでも予想したとおりに値にならないと、そこで止まってしまうこともあります。もちろん、その原因を探ろうとしているのですが、実験操作の記録をほとんどとっていないため追及ができないのです。そのため、失敗を恐れるようになってしまいます。しかし、人は失敗を繰り返すことで経験をつみ、成長していきます。多くの人が言っているように失敗は宝の山なのです。私が尊敬する人物として挙げた江崎玲於奈博士は、半導体研究の分野でノーベル賞を受賞された方です。 ゲルマニウムトランジスタの不良品の解析を行っているうちに新しい電子デバイスの発明につながる発見をされました。つまり、失敗のデータを細かく分析することで後の成功につながったわけです。失敗を宝の山にするためには、記録が必要です。細かい記録がないと失敗の分析ができません。実験だけでなく、普段の授業から細かい記録をつける習慣をつけてはいかがでしょうか。
SDGsの取り組み
社会課題
- 自然環境・廃棄物
 摂南大学を目指すあなたへ
摂南大学を目指すあなたへ